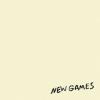MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > bonnounomukuro- Mindows
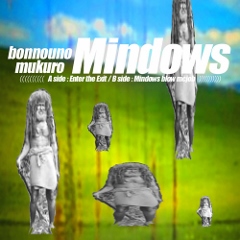
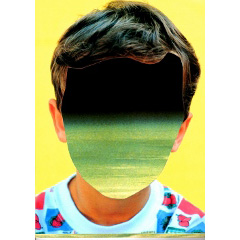
はんぺん忍者:FISH CAKE SYNDICATE (YPY&WOODMAN)
Live Recordings Except From 納涼オナラ祭セッション @ 大阪ミナミ☆東心斎橋アトモスフェーレ
birdFriend
松村正人 Sep 20,2013 UP
ゴート/ボナンザスのメンバーであり、YPY名義でソロでも活動する日野浩志郎がついさきごろたちあげたテープ・レーベル〈birdFriend〉の設立についての一文がふるっている、というか、ふるっていないと思えるほど、いつわらざる気持ちが認めてあって、たしかにそうだと思うのである。
私は日野浩志郎の年は知らないが、一度お会いしたときの肌のツヤを考えると、四十路の私より下であるのは確実なので、彼にとってカセット・テープはなじみがうすいと考えてまずまちがいあるまい。私は幼少期、音楽を聴くとなるとレコードかミュージック・テープ(MT)だった。CDは82年に生産ラインに乗った――大滝詠一の『ロンバケ』が邦盤の嚆矢であったことはあまりに有名である――が、高校のころ、はじめてCDプレイヤーを手に入れたことを考えると、CDで音楽を聴く聴き方が一般化したのは実感として80年代中盤から後半にかけて。その後、カセット・テープはCDの下位媒体として、たとえば、レンタルしたCDをカセットに落とすとか、これはあまり一般的ではないが、4トラのカセットMTR(マルチ・トラック・レコーダー)で宅録するとか、いずれにせよ、書き込めないCDに対する記録メディアとしてずぶとく生きながらえ、数年前、私がサラリーマン編集者としてわがの世の春を謳歌していたころはまだ、インタヴューの収録とかで使っていたのはカセットのテレコだったのである。一方、そんな私とは対照的にカセット・テープは青息吐息であった(いまは私が息も絶え絶えであるが)。データ化が進み、音楽はわざわざ媒体に残すべきものではなくなっていた。受容が落ち込み、コンビニの棚からも姿を消しはじめていた。同じころ、オノ・セイゲンさんに、もう使わないからあげるといわれ、段ボール2箱分、カセットをもらったのも、うれしかった反面、一抹の寂しさをおぼえた思い出である。
そういった記憶が日野浩志郎にはないか、あったとしても近い記憶ではなかっただろう。ここ数年のレコードやカセットへの揺り戻しは、私たち世代にノスタルジーを感じさせるが、その後の世代には発見だった。日本はいわゆる日本的な「和」の意匠を除けば、基本的にスクラップ&ビルドな国なので、ちかぢか店頭に並ぶ、紙エレキング11号で、日野と同じくテープ・レーベル(http://crooked-tapes.com/)を主宰する倉本諒が指摘する通り、アメリカのように、福音伝道師をはじめとしたキリスト教原理主義――これはザッパが容赦なく糾弾しつづけた米国の広大な非都市圏と人口の多数派を構成するものだ――と車社会の隅々に効率よく音を届けるメディアとしてカセットは重宝がられたわけではない。もちろんカセットを聴く層は一定数いるだろうが、私は音楽の根づき方と同じく、ハードにしろソフトにしろ、それが日常の風景の一部になっているとまではいえない。
日野浩志郎は先の一文で、MDやCDの方が接してきた時間は圧倒的に多い、という。彼は日本におけるカセット文化には文脈の切断があり、それが(再)発見をうながす土壌であることに自覚的ではないにしろ模索しはじめている。そこに音楽の旨味が生まれる――かもしれない、と私は期待する。それは倉本諒のレーベルも同じである。彼らはたとえば『EGO』のカセットブックなんか知らないだろうし、インディーズとは呼ばれる前の自主制作盤時代のテープを集めているわけでもないだろう。私はそれで(が)いいというのではなく、USアンダーグラウンドに併走しながら、しかしこの特異な風土が育む、ローファイの一語にたやすくくくれない音が生まれる可能性は棄てきれないと思うのである。
今回〈birdFriend〉の第1弾は2点。〈パリ・ペキン〉〈360°〉の虹釜太郎との共同レーベル〈ICE RICE〉からファーストCD-R『Tape Days』を出した神戸のトラックメイカー、bonnounomukuro、ボンノウボムクロ、煩悩乃骸の『Mindows』はA、B面とも46分テープの片面をフルに使った長尺曲を収録。A面の"Enter the Exit"のBPM130あたりを基調に、音のビートとウワモノをなめらかに構成していく手法はDJ的であり、中域にくぐもりながらうねる音使いの総体的な印象はクラウト・ロック(カンとか何とか)のセッションのアウトテイクのようでもある。反対面の"Mindows Blow McJob"はA面よりも広いレンジでカットアップする音をダブでさらに飛ばすことでサイケデリックな音の場をかたちづくる。ともにコンプがかったテープの音色との相性も見事な名曲である。というより、媒体の制約が音に相乗効果をもたらしている。必要は発明の母であるが、制約のない必要は欲望でしかなく、制約は念に指針を与える、ということは、同じく第1弾であるYPY名義の日野浩志郎とウッドマンとのデュオ「はんぺん忍者:FISH CAKE SYNDICATE」の『Live Recordings Except From 納涼オナラ祭セッション @ 大阪ミナミ☆東心斎橋アトモスフェーレ』の弛緩させるナゾめいた音の場にもあてはまる。その空間性は、テープ・カルチャーの空隙を埋めるだけでなく、その退潮と交錯するように浮上した90年代再考への呼び水となるやもしれぬ、と私はヘッドと磁気テープの擦れあう、機械のフィジカリティともいえるカセット・テープに耳を傾けながら思ったのだった。
松村正人
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE