MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Hair Stylistics- Dynamic Hate
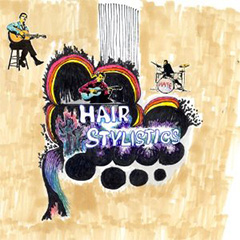
ヘア・スタイリスティックス=中原昌也のビート集、ビート・ミュージックだ。僕はこの27曲65分にも及ぶ、ビート集を聴いて、心の底から愉快な気持ちになった。発売から2ヵ月以上経つが、いまだによく聴いている。いま、日本でもビートメイカーのレヴェルはぐんぐん上がっていて、彼らは海外のムーヴメントのフォロワーとは異なるオリジナリティを獲得している(という物言いそのものが古臭い!)。コンピレーションとしてまとまっている、『Lazy Replay』や『Sunrise Choir - Japan Rap&Beat』は、日本のビートメイカーのいまを知るためのひとつの参考になるだろう。とはいうものの、良し悪しの問題ではなく、やはりLAのビート・ミュージックや、SoundCloudやbandcampにおける世界的なモードは大きな影響力があり、日本のビートメイカーの多くもその時代の空気のなかにいる。
ヘア・スタイリスティックスのビート・ミュージックからはそのような空気と同じ匂いがするが、それは中原昌也が90年代の暴力温泉芸者の頃からずーっとやってきたことがたまたまいまの時代の空気にフィットしただけだとも言える。おそらく、このビート集がもう5年早くリリースされていたら、中原昌也のコアなリスナーには届いたとしても、鎮座ドープネスをフィーチャーした曲(“This Neon World Is No Future”)が収録されるには至らなかったのではないだろうか。3年前から制作がはじまったというこの作品が、2013年に世に出たというのは素晴らしいタイミングだ。いや、タイミングではなく、『Dynamic Hate』が素晴らしいのだ。
好き嫌いといった趣味はあるにせよ、多くのビートメイカーやビート・ミュージック・フリークは、この作品を聴いて考え込むのではないだろうか。「いま“新しい”と言われているビート・ミュージックが果たして本当に“新しい”のか」と。『Dynamic Hate』は、“ビート・ミュージック”という既存の土俵に揺さぶりをかけるビート・ミュージック集だ。中原昌也自身はそんな大それたことを意図していないだろうが、そのような問題提起を孕んだ作品でもある。例えば、アルカの『&&&&&』はたしかに面白いと思うし、いまの時代に支持される理由もわかる。ただ、インターネットの大海原には、アルカに匹敵する才能はゴロゴロ転がっている。僕なんかよりも、SoundCloudやbandcampで日夜ビート・ミュージックをディグっているビート・フリークの諸氏がそのことをよく知っているだろう。カニエ・ウェストが『イーザス』で大抜擢しなければ、アルカがこれほど脚光を浴びることはなかっただろうし、もっと言えば、アルカの分裂的な手法は子供騙しと表裏一体でもある。
中原昌也は、紙版『ele-king vol.11』のインタヴュー「いよいよ脈打つヘイト」で、「ビート=黒人のものっていう図式もなくなってきたじゃないですか。黒人だからいいビートをつくれるわけじゃない。そういった状況は後押しするものがあったかもしれない」と語っている。さらに、「昔はブギ・ダウン・プロダクションズとマイナーなノイズをいっしょに買うと気ちがい呼ばわりされたものです。僕の頭のなかで常に共存はしていましたけど、そういうことを共有できる友だちはいなかったですよね」とも言う。興味深い発言だ。ラス・Gの『Back On The Planet』の土臭くコズミックなビート、アートワークに接すると、やはりいまだアフロ・アメリカンの音楽家には、拠り所にすることのできるルーツや、アフロ・フューチャリズムのような思想が脈打っているのだなと思う。 “ビート=黒人”という図式があったのかは議論を差し挟む余地があると思うけれど、ビートをグルーヴと言い換えれば、たしかに“グルーヴ=黒人”という図式はあったと思うし、いまだに根強く存在すると思う。
僕が『Dynamic Hate』を面白いと思った最大の理由は、いち音いち音の音色のヴァラエティとコンビネーションが耳を楽しませてくれるところにある。耳のチャンネルが面白いように次々に切り替わっていくのだ。資料に拠れば、本作は「Ensoniq SP1200、AKAI MPC3000などのサンプラー、ROLAND TR-808などのリズムマシン、ARP2600などのシンセサイザーなど、数々のヴィンテージ・アナログ機材を使っ」て制作し、カセットデッキに録音しDATに起こしたというから、その音色は想像できるだろう。
一応断っておくと、僕はなにもローファイなサウンドに拘ることが、音への誠実な態度であると言いたいわけではない。グルーヴィーなビートもあれば、グルーヴをあえて否定しているようなビートもある。それが不思議で、興味深くて、何度も聴いてしまう。中原昌也流の諧謔精神ももちろんあるが、そのような態度よりも、とにかくビートのユニークさに耳がぐいぐい惹きつけられる。そして、中原昌也流の分裂的な手法もある。というか、『Dynamic Hate』を聴けば、先ほどのブギ・ダウン・プロダクションとノイズの話ではないが、それが実は分裂でもなんでもなかったことがわかるし、僕自身もいまだからこそその感覚を実感できる。10年前は頭では理解しているつもりでも、実感としてそのことがわからなかった。マントロニクス流のエレクトロ・ファンクとウェルドン・アーヴィンのジャズ・ファンクの名曲“We Getting` Down”をミックスしたような“Empire of Plesure”があり、“No Funk (Tk1)”というタイトルなのに、ベースとキーボートがシンコペーションしているファンキーなビートがある。エキゾ・ブレイクビーツとでも言いたくなる“Music For The Murder Festa”と、シンセサイザーがうなりを上げ、ノイズを撒き散らし、シンプルなビートがズンドコ叩きつけられるタイトル曲からは、中原昌也の気合いと激情が溢れ出しているように思う。手を叩いて大笑いしながらでも、難しい顔をして議論しながらでも聴ける作品だが、いまビート・ミュージックを追っているのであれば、無視できない作品だ。
二木信
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE




