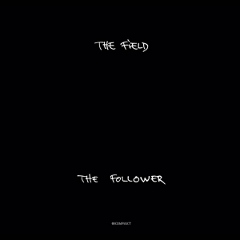MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The Field- Cupid's Head

白よりも黒、光よりも陰、そしてイエスよりもノー……。ザ・フィールドの新作である。
これまで白(正確にはクリーム色だが)を貫いてきたアルバム・ジャケットを真っ黒にする。ただそれだけのことで何か劇的な変化を期待させること自体が、彼、アクセル・ウィルナーのはじめのプレゼンテーションである。そうして乗せられたリスナーはしかし、多くのひとが僕と同じように、アルバム1曲めの“ゼイ・ウォント・シー・ミー”を聴いてこう思うだろう……「えっ同じやん」。ビートは4つを打ち、シンセのフレーズが繰り返され、そこにシューゲイジングな味つけがされ、じょじょに、じょじょに楽曲に熱が帯びていく。幕開けとしてはもちろん最高にスリリングだが、しかし、これは紛れもなくこれまでもわたしたちが馴染んできたザ・フィールドである。いったい「劇的な変化」はどこに? と怪訝なまま、2曲め“ブラック・シー(黒海)”へ。ここでもまたビートは4つを刻み、シンセのフレーズが繰り返され、そこにシューゲイジングな味つけがされ、じょじょに、じょじょに楽曲が熱を帯びていく……これも、ザ・フィールドである。が、トラックが7分に差し掛かるころである。ビートが微妙に乱れ、それまでと別の不穏なリフが底のほうから静かに立ち上がってくる。ハットは16を刻み、吐息のサンプルが左右から飛んでくる。気がつけば、曲が始まった瞬間とはまったく異なる、ダークなダンス・トラックがそこに出現している……ここでようやくこう思うのだ。「こんなザ・フィールドは聴いたことがない」。つまりこういうことだ……ザ・フィールドの新作『キューピッズ・ヘッズ』のスタイルは、これまでと何も変わらない。が、同時に、「これまでと全然違う」。ここで、1曲めのタイトルの巧みさに気がつくのである……「やつらは俺がわからない」。
これはアクセル・ウィルナーによる、「変化」に対する繊細なコメンタリーのようであり、ある種の批評的態度であるように思える。たとえばこんなインタヴューを、あなたは読んだことがないだろうか。Q:新作は前作とかなり印象が異なりますが、これはどういう理由によるものなのでしょうか? A:前作と同じことはやりたくなかったんだ。僕はほら、飽きっぽい性格だから、同じことは繰り返したくないんだよね。毎回違うことをやることが僕の挑戦なんだよ…………とか何とか。そしてこうしたものを読むたびに、「それが「同じこと」なんだよ」とつっこみたくはならないだろうか。わたしたちはそんなありきたりの、お決まりの「変化」を、日常的にじつにたくさん消化している。ザ・フィールドはそんなクリシェを周到に避けるようにして、じっくりと作品に向き合った人間にだけ届くような変身をここで見せているのだ。
前作『ルーピング・ステイト・オブ・マインド(ループする精神状態)』はタイトルにもあるように、自らの音楽スタイルに自己言及するようなアルバムであった。そういう意味で、彼は自分の様式というものにつねに自覚的で、それを対象化し続けている。このアルバム全体で行っている繊細な変化とはそもそも、これまでの楽曲のなかで彼がつねに取り組んできたことでもあるだろう。同じフレーズをひたすら繰り返しながら、しかし何か決定的な違いを混ぜ込んでいくこと……。セカンド・アルバムのタイトル、『イエスタデイ&トゥデイ(昨日と今日)』はまさしく、そんな「わずかな、しかし決定的な違い」に言及するものであったろう。新作に戻れば、タイトル・トラック“キューピッズ・ヘッド”にしても、“ア・ガイデッド・ツアー”にしても大筋は変わらないが、ファースト『フロム・ヒア・ウィ・ゴー・サブライム(ここからわたしたちは絶頂へ)』でザ・フィールドの徴であり人気を集めた要素であった、高揚によるカタルシスは徹底して避けている。そして、本作でもっともチャレンジングなトラックが続く“ノー、ノー...”である。「ノーノーノーノーノーノー」というヴォイス・サンプルが乱れ飛び、ビートも乱れ、しかしあくまで構造としてはループしている。トラック中盤、奇妙に拍を刻みながら気分がずぶずぶと沈んでいくような展開は、間違いなくこれまでのザ・フィールドにはなかったものであり、また他でもなかなかお目にかかれないものだ。クロージング・トラックの“20セカンズ・オブ・アフェクション”の頃には、エクスタシーを迎えないまま酩酊し続けるザ・フィールドの新たな快楽に耳と身体が馴染んでいることに気づく。〈タイニー・ミックス・テープス〉がスタイルを「good sex」とする妙なレヴューを書いてしまうのも頷ける。
前作のレヴューで僕は「反復が持つ可能性のより奥へと分け入ることに成功している」と書いたが、ウィルナーはなかば求道的にさらにその奥にここで進もうとしている。もはや、これは茶道とか華道とかで言う「道」に近い領域に突入しているようにすら思えるがしかし、これはあくまでダンスも含んだ快楽のあり方のひとつである。その、さらなる複雑な領域をフレーズの繰り返しとともにウィルナーは探り当てようとしている。ノーノーノーノーノーノーノーノーノー……
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE