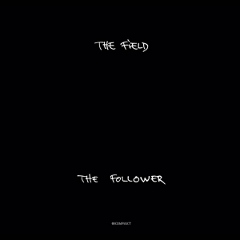MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The Field- Looping State Of Mind
進んでも進んでも気がつけば同じ場所に戻っている。ザ・フィールドの音楽は一言で言えばそれである。
反復という手法はもちろんダンス・ミュージックの基本だが、それがリズムやフレーズの徹底したループという意図的なものになると、それはもはやひとつの表現形態で、大げさに言えば人間が生きることのアナロジーになり得ると思う。永劫回帰とか輪廻転生とか大それたことでなくても、寝て起きて、ほとんど同じような毎日を繰り返し続ける生活のことを「リズム」だと呼ぶ感覚を言い当てているのではないだろうか。ほかの反復音楽を聴いていてもそんな風にはあまり思わないのだが、ザ・フィールドの音楽の叙情性、というか「ヒューマンな」感触はなぜだか僕にそんなことを思わせる。そしてそれは、ダンスフロアやベッドルームなどの特定の場所ではなく、もっと日常の生活に近いところにある。
あるいは僕の場合、ループという言葉を聞くとごく初期の任天堂のマリオのゲームを思い出す。正しいルートを選ばないと同じ地形を延々と繰り返す単純なトラップにループと名前がつけられていたのだ。そしてそこで、僕は敢えて間違ったルートを選んで遊んでいた記憶がある。するとテレビに映るのは延々と同じ画面の流れの繰り返しで、それはいまにして思えばある意味サイケデリックな体験だったと言えよう。
本作のタイトルの「ループする精神状態」は、そんな不毛さと快感に同時にはっきりと言及する。ザ・フィールドはループそのものをコンセプトとして意識的に掲げたアクセル・ウィルナーによるプロジェクトであり、無地のクリーム色を背景にアーティスト名とタイトルだけが簡素に記されたジャケットが3作続けられたことにも表れているように、ミニマリズムをその美学としている――のだが、ミニマル・テクノと呼ぶにはどこか、そこからはみ出すニュアンスをつねに孕んでいる。それは例えばタイミング的にもネオゲイザー勢とシンクロしたシューゲイジングな味付けであったり、音の丸い輪郭による柔らかい質感であったり、上モノのメロディが持つセンチメントだったりするのだが、作を重ねるごとにそうした細部により神経を使っていることがわかる。ループという「効用」があるとして、それをフィジカルなものとしてよりもメンタル面にいかに作用させるか、にウィルナーは関心を抱いているのではないだろうか。ザ・フィールドの音楽の手触りはいつも、機械の冷たさではなくどこか体温を感じさせるものである。
この3枚目に顕著なのは何よりも生音のドラムとベースであり、それらによる僅かなエディットのズレやリズムの揺れ、有機的なグルーヴである。基本的に拍は4/4を刻みながらも、裏の拍にビートが入ったりリズムが微妙にシンコペートしたりする複雑さも実は張り巡らされている。半音階がやたら入ってくるシンセの和音。それらによって醸されているエモーションもまた、上り詰めもせず沈み込みもしない単純に喜怒哀楽に分けることのできないもので、デビュー作『フロム・ヒア・ウィ・ゴー・サブライム』においてわかりやすいブレイクやフランジャーで演出された高揚感を思えば、反復が持つ可能性のより奥へと分け入ることに成功していると言えるだろう。
もちろん、ザ・フィールドのひたすら繰り返される音楽のなかにも様々な展開は用意されている。オープニングの"イズ・ディス・パワー"では順序良くドラムが入り、ベースが入り、そして6分ほど経ったところでようやくがらっと風景を変える得意のテクニックを使ってオープニングをソツなく演出しているし、"バーンド・アウト"では途中でやたらメロウな歌が入ってきたりする。そう言えば前作『イエスタデイ&トゥデイ』ではコーギスのカヴァーを唐突にしていたが、それよりも遥かに自然なやり方で歌を自分の音楽に溶け込ませている。ただ、「アルペジオされる愛」と洒落たタイトルがつけられた"アルペジエイティッド・ラヴ"で10分同じフレーズを繰り返しながら次第にギターのノイズが降り注いでくるときの渦巻くようなサイケデリアや、タイトル・トラックにおいてやはり10分かける反復のなかで細かい電子音のフレーズを差し込んでくる周到な快楽への誘いこそが、本作の聴きどころでありザ・フィールドの真骨頂だろう。基本的なやり方は変えずとも、ウィルナーは高揚よりも陶酔の方に向かっている。ラスト・トラック"スウィート・スロー・ベイビー"のやたらに崩した奇妙なリズムだけは新しい手法に貪欲に挑んでいると言えるが、通して言えばザ・フィールドというコンセプトの着地点がこのアルバムだろう。
そして、それは徹底して心地良いものとしてある。作り手によって意図的になされたループを通してそれが達成されるならば、それは不毛な繰り返しであるかもしれない生活を緩やかに肯定し、そこに寄り添うものとなるだろう。同じところをぐるぐる回っているようでも、ひょっとすれば螺旋状に上昇はしているかもしれない。生きることには「リズム」が欠かせないのだと、そのサイケデリアからじわじわと聞こえてくるようである。
木津 毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE