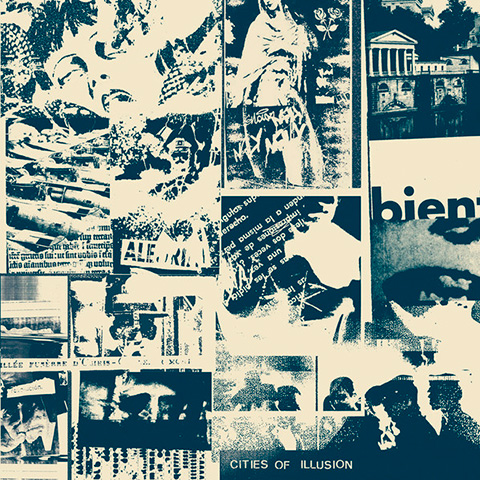MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Various Artists- Music For Shut Ins
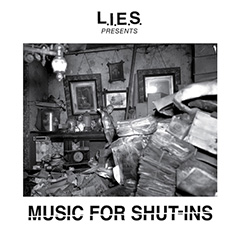
あたかも極限状態を試すかのように、このところハウス・ミュージックばかりを聴いている人間が日本に少なくとも5人いるはずである。彼らは日夜『HOUSE definitive 1974-2014』のため、なかばマゾヒスティックなまでに4/4キックドラムを浴びているのだ。雪が降ろうと快晴だろうと、腹が減ろうと満たされていようと、外へは一歩も出ずに……
長年音楽を聴いてきて、大衆音楽史においてもっとも大きな分水嶺となっているがディスコ/ハウス・ミュージックだったというのは確信がある。数ヶ月前も、たまたまある場所で、ある高名な音楽評論家と目があった瞬間に「俺はクラブは嫌いだから」と言われたが、こういうことは西暦2014年になろうが珍しいことではない。ノイズ/インダストリアルの愛好家でも、80年代半ばにそれがディスコを意識するようになってから離れていった人は少なくないが、僕も最初からディスコ/ハウス・ミュージックを素直に受け入れたわけではないので、その気持ちがわかる。10代~20代前半の若い頃は、ダンス・ミュージックなんてものはナンパで軽くて、低俗だと思っていた時期がある。恥ずかしくて聴けたものではないと。たんに自分がその超然とした優雅さを理解できなかっただけのことだが。
ディスコは一時期商業的に大ブレイクしたので、1975年までのアンダーグラウンド時代を、そして流行が終わった後のアンダーグラウンド回帰時代(代表的なのがアーサー・ラッセル)を顧みずして、先入観や偏見だけで出来上がってしまったイメージがまだある。ダンスがうまくて、やたらキラキラしたイメージだ。実際は、音響装置の実験もあり、また、ゲイの運動家たちの拠点としての政治的な側面も併せ持っていたりと多様だが、たぶんどんな人にもざっくりとしたイメージがあるだろう。ところがハウス・ミュージックには、ディスコほど明確なイメージがない。ハウスはディスコから来ているが、しかしそれが出てきたとき、ディスコと違って匿名的で、つまり妖しく、より異質に見えた。
ラリー・ハードの超名曲がほのめかしたように、ハウス・ミュージックは「ミステリアス」だった。ジョン・サヴェージが言うように、80年代半ばのレアグルーヴ(昔のファンク崇拝)が支配するダンスフロアにとっては、あり得ない何かに思えたものだ。この日常世界のどこかには、自分たちのまだ知らない感性による何かが始動している。まだ知らない世界がある。〈トラックス〉や〈DJインターナショナル〉、〈ニュー・グルーヴ〉のレーベル面の素っ気ないロゴ、ラフなデザインと印刷もそうだが、クレジットには初めて見るような名前ばかりが印刷されている。同時代のニューウェイヴ・ディスコの洒落たデザインとは対極で、しかも事前の情報もなく、ただそこに1枚の12インチがある。
そこには好き勝手に録音された得体の知れない音が彫られている。ときにはセクシャルなトーチ・ソング、ときには狂ったかのようなドラッギーな反復、ときにはディープな思いを誘発する音が、名も無き人たちによって作られる。世界のどこかで醸成されるその「ミステリアス」さ、これがハウスと括られるジャンルの大きな魅力だった。
かつて、ベルリンのベーシック・チャンネルというレーベルは確信犯として、その「ミステリアス」さを継承した。アーティスト名が読めないくらいがちょうど良いのだ。誰が作ったかという情報を明記するよりも、どんな音がそこにあるのかということへの関心を高めるほうが、このジャンルでは最高の効果を果たす。今日、東欧(ルーマニアやブルガニア、ロシアなど)のミニマルなハウスが異常に人気なのも、「ミステリアス」さと大いに関係があるのだろう。そしてNYのレーベル〈L.I.E.S.〉もまた「ミステリアス」であることに自覚的だ。
本作は、昨年末のリリースで、レーベルにとって2作目のコンピレーションとなる(1枚目は『ピッチフォーク』いわく「スクリレックスの口のなかに尖った棒をぶっ込んでいるかのような」作品。どんなものかわかるでしょ?)。先日、NYでクリス&コージーがライヴを披露したときにサポートしたのがこのレーベルだったというが、彼らの音は明白なまでにアシッド・ハウス寄りで、ガラージ・ハウスもしくはディープ・ハウスなどよりはノイズ/インダストリアルに近い。ディスクロージャーではなく、ファクトリー・フロアやBEBの側……いや、それ以上に衝動的な何か。レーベルを主宰するロン・モレッリは、自身の作品はノイズ/インダストリアル系の〈ホスピタル〉から出している。
紙エレキングで島田嘉孝氏が書いているが、〈L.I.E.S.〉は、昨年から日本でも人気レーベルなっているそうだ。レゴヴェルトはテクノ・リスナーにはそこそこ知られているだろうし、昨年話題になったトーン・ホークもこのレーベルから出している。が、基本「リリース経験の乏しい名の知れないようなアーチストばかり」の作品を出しているというのに売れているのは、レーベルへの信頼度や極めて衝動的(ガレージ・ロック的)であるがゆえの楽曲のユニークさもさることながら、そこで何が起きているのか知りたいという欲望が駆り立てられているからなのだろう。ハウスは難しい音楽ではないが、これが意外と気持ち良ければいいって音楽でもない。『Music For Shut Ins』には挑戦的な若々しさ、毒々しさ、激しさがある。
NYは、ディープ・ハウスよりの〈Mister Saturday Night〉も調子が良い。NYは、アレックス・フロム・トーキョーによれば、のぼり調子だという。なにせ新しいNY市長ビル・デブラシオへの期待が大きい。民主党から(左よりの)NY市長が当選するのは24年ぶりだそうだ。前々市長のジュリアーニや富裕層を優遇した前ブルームバーグ市長に真っ向から対立する低所得者層支援の政策を掲げている彼は、これまで日常化していた警察の職務質問まで緩和させる方向らしい。デブラシオはイタリア系で、ディスコもディスコティックのイタリア語風の読みだし……。何にせよ、ウォール街のデモは無駄ではなかったわけだし、NYのクラブ・カルチャーも盛り上がるわけだ。〈L.I.E.S.〉の流通をベルリンのハードワックス(マーク・エルネストゥスが経営する世界的人気のレコ屋)が手がけるということも島田氏のくだんの原稿に書かれているが、さすがに鼻のきく連中だと感心する。時代の風向きはここにあるのだ。
そういえば、ディスクロージャーのリミックス・アルバムの人選にラリー・ハードの名前があった。EDMとの違いを見せつけているが、それが通って話ではなく、読者にはハウス・ミュージックの「ミステリアス」さに注意を払って欲しい。これはレトリックの問題でもあるが、アティチュードと音楽性に関わる話でもある。ハウス・ミュージック以降の電子音楽の実験系でもそれは踏襲されている(3~4年前のOPNもそうだった)。「ミステリアス」とは辞書的に訳されるところの「神秘的」ということではない。「より多くを知りたくなる何か」であり、「咄嗟に説明の付かない何か」であり、それは安易に長いものには巻かれないことで保たれる。ま、『Music For Shut Ins』は僕のようないい歳の人間が聴くにはドラッギー過ぎるのだが、この1週間、ディープ・ハウスばかり聴いていたので、口に直しにはちょうど良かった。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE