MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Otto A.Totland- Pino
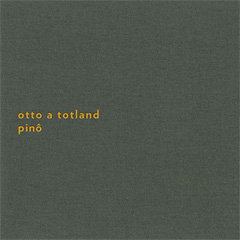
ポストクラシカルは、00年代的なアンビエント/ドローンのヴァリエーションである。ポスクラ特有の素朴な旋律はプレテクストな側面が強く、リスナーはエレクトロニカの電子音を摂取するように、生楽器(ピアノや弦楽器)の響きに耳を傾ける。ゆえにピアノのメロディは口実のように綺麗なアルペジオを奏でるし、弦楽器は音響的なレイヤー感を添えるのだ。
結果、まるで西欧の片田舎のフォーク・ミュージックのような瀟酒な音楽が奏でられることになるのだが、しかしここにおいて歴史は(初めから)剥奪されている。先に書いたように、メロディや和声は一種の口実でしかない。聴き手は「響き」のアトモスフィアを味わう。その意味で、一種のポスト・モダン・ミュージックですらあった。歴史の無化と動物的な音響聴取。それこそエレクトロニカ以降のリスニング環境の特徴だろうし、ポストクラシカルとエレクトロニカはその点において繋がっている。そして、エレクトロニカ的なアンビエントにはチルアウトという意味もない。ただ、気持ちよい音を摂取すること。それゆえエレクトロニカ以降のアンビエントはドローンへと接続される。同じことはポストクラシカルにも言える。旋律やリズムが響きの中に溶け合うような感覚があるからだ。
だが同時にポストクラシカルにはアンビエント/ドローンとは違う「わかりやすさ」がある。ピアノで奏でられるメロディは、多くの人の耳に届きやすいものだ。そもそもアンビエントとBGMの境界はつねに曖昧だ。ポストクラシカルのわかりやすさは時にBGM的な(一種のカフェ・ミュージック的な?)わかりやすさへと落ち着いてしまう。そこでは響きへのフェティッシュは、聴き取りやすい旋律の後ろに後退する。ヒーリング・ミュージックに安易さ/危険さに隣接すらしてしまうだろう。ポストクラシカルがエレクトロニカ以降の音楽的発展の中で反動的に聴こえてしまうのもカフェ・ミュージックとヒーリング・ミュージック特有の問題/危険性を内包しているからだ。
しかし、ここ数年、ニルス・フラームら北欧の音楽家たちの活躍によって、ポストクラシカルは(ようやく?)、このような危うさから脱却しつつあるように思える。音楽と音響のちょうど良いバランス(と過激さ)を確立しつつあるのだ。重要な作品は、ニルス・フラームの2011年『フェルト』だろう。『フェルト』は、一聴、ローファイな録音だが聴き込んでいくと、ピアノ内部のハンマー音、鍵盤にタッチする音、ピアノと演奏者を取り囲む環境音などが渾然一体となっており、その素朴な精密さには聴き込むほどの感動がある。つまり密やかな音の中に、環境音やノイズを過激なまでに取り込んでおり、一筋縄ではいかない作品に仕上がっているのだ。現代のポストクラシカルは、単に素朴で綺麗なメロディを奏でるだけの音楽ではない。エレクトロニカ以降の、カジュアルなノイズ聴取環境以降に存在する音楽としてあるのだ。
そこで、ようやく本盤の話だ。オット・A・トットランドのピアノ・ソロ・アルバム『ピノ』。この作品こそポストクラシカルの現在を考える上で重要なアルバムのように思える。
オット・A・トットランドはノルウェイのアンビエント・ユニット、ディーフセンターのメンバーだ。ディーフセンターは、闇の中のカーテンから漏れる光のようにロマンティックな音楽性が特徴のユニットだが、ピアノ・アルバムである本作には彼(ら)の音楽に見え隠れする良質なセンチメンタリズムが前面に出た仕上がりになっている。リリースはポストクラシカル作品をリリースしつづけるベルリンのレーベル〈ソニック・ピーシズ〉から。初回盤は、いつものように限定450部のハンドメイド・ブック型ジャケットである(セカンド・プレス以降はカード・ホルダー・タイプ)。
アルバムを再生すると、微かなノイズのむこうで鳴っているピアノの旋律が聴こえてくる。まるで90分ほどの小さな映画のテーマ曲のようなささやかな幕開け。録音マイクはピアノの中にあるハンマーの音から、その周辺の環境音までも繊細に捉えている、その儚くも優しい、しかし確かな存在感を感じる音。ああ、この音はどこかで聴いたことがある。ニルス・フラームの『フェルト』だ。事実、このアルバム『ピノ』はニルスのスタジオで録音されており、彼も制作に関与しているという(ちなみにディーフセンターの2011年作品『アウル・スプリンター』の録音にも、ニルス・フルームは関わっており、そのメランコリックな空気をさらに親密なものとして録音していた)。
それにしても、なんという録音か。そのピアノの音はどこで鳴っているのだろうか。ほんの少し離れた隣家からか。それともこの部屋で、誰かが傍らで演奏しているのか。それとも数十年も昔に録音されたテープからか。それとも、未来からか。微かなノイズと、遠くにあるようで、しかし、自分の傍らで鳴っているようなピアノの音。どこか聴いたことがあるようで、まるで聴いたことのない音。夕方から夜にかけての光のようにメランコリックな旋律と残響。響きが溶けあうようなアンビエンスの芳香。やさしくて、優しくて、ささやかで、個人的な音。〈ソニック・ピーシズ〉はこれまでも素晴らしいモダン・クラシカル作品をリリースしてきたが、本作はその中での最高傑作ではないか。楽曲と録音と演奏が、極めて独自のレヴェルで共存/存在しており、そこから近年、なかなか聴くことのできない、極めて純粋な(個人的な)音楽が鳴っているように思えるからだ。
同時に、この音は世界に対して開放されている。音楽をとりかこむ環境=音響を自然の共演者のように迎え入れているからだろうか。アルバムを聴く進むほどに、ピアノの残響は深く、音を包み込む。旋律が環境のアンビエンスに溶け込む。とくに11曲め“ジュリー”においては、(たぶん)録音していた部屋に入ってきたであろう鳥の鳴き声が見事に音楽の中に取り込まれているのだが、その瞬間こそ、ミュージックとアンビエントが見事に融合した瞬間である。そのアンビエンスは聴く者の耳に鮮烈な驚きすら与えてくれるはずだ。
最後になったが、オット・A・トットランドの作曲家としての才能にも注目したい。はじめに書いたように、ポスクラにとってメロディは一種のプレテクストであり、それゆえ即興によるアンビエント効果を狙いすぎる傾向もある。しかし、本作の場合は、素朴ではあっても決して安易な雰囲気に逃げることなく、自分だけの旋律と和声を持った楽曲が、しっかりと作曲されている。もはやメロディは音響摂取のための口実ではない。これはとても重要な変化に思える。
このアルバムは「作曲家オット・A・トットランド」が、自らの楽曲を世に問うた最初のアルバムなのだ。そのメランコリックで美しい楽曲の数々は、一人の才能あふれる作曲家の誕生を告げている。ささやかで、慎ましやかで、美しく、親密で、そして儚い曲の数々。だがしかし、たしかに、ほかにない静かな野心が蠢いている作品でもある。その独特の録音が、それを証明している。旋律、ノイズ、環境、響き、融解。これらのおぼろげな交錯の場としてのピアノ・アルバム。まさに、ニルス・フラーム『フェルト』以降、ポストクラシカルの豊穣な達成がここにある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE


