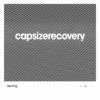MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kangding Ray- Solens Arc
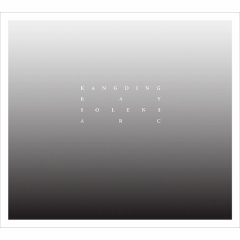
カンディング・レイ、待望の新譜である。リリースはもちろん〈ラスター・ノートン〉から。アルバムとしては前作『OR』(2011)から3年ぶりだが、その間も、12インチ・シングル盤を〈ストロボスコピック・アーティファクツ〉や〈ラスター・ノートン〉などからリリースしていたので、久しぶりという気はしない。むしろこの3年、これらのシングル盤で実験・展開された要素が、ついにアルバムにまとめられたという感覚がある。実際、この新作アルバムでの音響的交錯や、その変化は、シングルで追及されたフロア向きのトラックの集大成といった趣である。重低音に響くキック。短いシーケンス・フレーズのレイヤー。そしてノイズ。そのむこうに、うっすらと聴こえるミニマルなメロディ。そしてこれらの特徴は近年のインダストリアル/テクノの潮流ともリンクする。たとえば、本作の隣に置くべき盤は、実験的な電子音響作品ではなく、ヴァチカン・シャドウとすら思えるのだ。このような作品をカンディング・レイが、ひいては、〈ラスター・ノートン〉がリリースしたこと自体、90年代末~00年代中盤までの状況を考えれば驚くべき変化といえる。文脈が混じりあう現在の最先端電子音楽の状況を象徴するアルバムともいえよう。
カンディング・レイ、本名デヴィッド・ルテリエ。ベルリンのエレクトロニクス・サウンド・アーティストである。2006年に〈ラスター・ノートン〉からファースト・アルバム『スタビール』をリリースし、2008年にはセカンド・アルバム『オトンヌ・フォールド』、2011年はサード・アルバム『OR』を発表した。デビュー・アルバム『スタビール』、セカンド・アルバム『オトンヌ・フォールド』までのカンディング・レイの作風は、〈ラスター・ノートン〉的なマイクロ・スコピックなグリッチ・ノイズに、エレクトロニカ以降の叙情性やダークなアンビエンスがレイヤーされていく楽曲を制作してきた。その楽曲の幅は電子音響からエレクトロニカ、ヴォーカル〈ヴォイス入り)のトラックまでじつに幅広い。彼は建築家でもあり、そのアトモスフェリックな雰囲気に加えて、どこか建築=構築的思考から生まれる土台と、上部構造が強固なトラックも大きな魅力であったように思われる。そして、2011年の『OR』においてはある変化が導入された。それが、ニューウェイヴ的ともいえるダイナミック曲調(ロック的ともいえる)への移行である。もちろん、NWな曲調は以前からも感じられた。たとえば『オトンヌ・フォールド』のヴォーカル入りトラック“ワールド・ウィズイン・ワーズ”などを聴けばそれがわかる。だが、『OR』では、よりテクノなビートが強調されているのだ。その変化によって彼の音楽は、インダストリアル化していくテクノの潮流ともリンクしていくことになる。とくに、『OR』以降にリリースされた、ルーシー主宰〈ストロボスコピック・アーティファクツ〉からリリースされた『モナド XI』(2012)や『Tempered Inmid』(2013)などの12インチ・シングル盤などはその象徴だろう。また〈ラスター・ノートン〉から2012年にリリースされた12インチ盤「ザ・ペンタキ・スロープス(The Pentaki Slopes)」も重要である。
このような変化は、彼自身、「自分のルーツはテクノではなく、ナイン・インチ・ネイルズ」などと語っていることからわかるように、ある種、必然でもあったのだろう。そして、この新作アルバムにおいては、これまで彼の重要な個性でもあった「緻密さ」をも捨て去り、どこかEBM的なダイナミックかつラフなトラックメイキングへと接近しているのだ。わたしは、このさらなる変化にとても驚いた。ここには彼の肉体的衝動が、電子音のシーケンス/ループの中に胎動のようにあらわれているように聴こえたからだ。
これまでのカンディング・レイの作風は、彼自身が語っているように、何度も何度もヴァージョンを作り直し、より高い完成度へと至るように練られていく、という緻密なものであった。しかし本作のトラックはまるで彼の初期衝動がそのまま楽曲へと転化しているような音楽/音響に仕上がっていたのだ。音響のレイヤーの緻密さ、ビート・プログラミングの複雑さ、という意味では前作のほうが遥かに高いかもしれない。だが、これも重要なのだが、本作のダイナミックな(EBM的な)トラックの方には、強烈に「いま」の空気を感じるのである。彼が、本作のようなアルバム(トラック)を作ったのは、現在の潮流に対する鋭敏な感性があったからのように思える。この変化には、〈ストロボスコピック・アーティファクツ〉からのリリースや、世界各地で行われたクラブ・フロアでのライヴ経験が、確実に反映されているはず。自身の音楽/音響が鳴り響く場所を、明確にクラブ/フロアに定めたのだろう。エクスペリメンタルで叙情的な電子音響/エレクトロニカから、肉体的な衝動が暴発する強烈なリズムのEBMへ。そして、ノイズとビートで世界の闇に抵抗/拮抗するインダストリアル/テクノへ。
だからこそわたしは、このアルバムにヴァチカン・シャドウとの距離の近さを聴きとってしまうのだ(昨年、ヴァチカン・シャドウはファースト・フル・アルバム『リメンバー・ユア・ブラック・デイ』をドミニク・フェルノウ自身が主宰する〈ホスピタル・プロダクション〉からリリースした)。ヴァチカン・シャドウ=ドミニク・フェルノウは、もともとはパワーエレクトロニクス/ブラック・メタルの文脈で作品を制作・演奏をしてきたアーティストである。ドミニク・フェルノウは、ヴァチカン名義でもプルリエント名義でも、4つ打ちのテクノを基調としながら、ブラック・メタルとパワーエレクトロニクスの文脈をダイナミックに混合させていくのだが、このコンテクスト混合によるノイズの復権は、まさに2010年代的なテクノを語る上での重要なエレメントといえよう。わたしはそこにエクスペリメンタルな電子音響を経て、テクノの文脈と交錯した近年のカンディング・レイの姿を重ね合わせてしまうのだ(カンディング・レイのこの新作は、ヴァチカン・シャドウへの応答ではないか?)。重いキックの4つ打ちとシーケンス・ループを基調としてスタイルにも共通性を感じる。もちろん、これはなにも、このふたりだけの共通性ではない。〈モダン・ラブ〉のデムダイク・ステアやザ・ストレンジャー、アンディ・ストット、〈ストロボスコピック・アーティファクツ〉のルーシーやダダブなどにも共通するスタイルに思えるのだ。
それらはそれぞれ違う出自や個性を持ちながらも、「テクノ」というフォームに、ノイズやインダストリアル、EBMを導入することで、新しい時代のエレクトロニクス・ミュージックの潮流を生み出しているのだ。そして、その流れに〈ラスター・ノートン〉が加わっていくことには、当然の帰結を感じる。なぜなら〈ラスター・ノートン〉の本質はインダストリアル性にこそあるのだから。カールステン・ニコライをはじめとする彼らは90年代から00年代にかけて、(ポスト・)デジタル・ミュージック=電子音響時代のインダストリアル・ミュージックを生み出してきたのだ。言うまでもないが、昨年リリースされたエンプティセットやセンキングのアルバムも、インダストリアル/テクノのひとつのカタチである。
カンディング・レイのこの新作は、そんな〈ラスター・ノートン〉が放つ、「2014年最新型のインダストリアル/テクノ」である。そして故にここには音楽/アートのもたらすリズムとビートとノイズによる速度が凝縮されているのだ。2枚組アナログ盤では、各面(A面・B面・C面・D面)それぞれが、ひとつの(大きな)「弧」を描いているという。アルバム名そのものように、貝殻の曲線のごとき弧を、である。その貝殻の曲線こそ、本サウンドのスピード、リズム、ビートではないか。そしてそれこそ現代の音楽の速度ではないか、とわたしは思う。本作収録の“ブランク・エンパイア”のPVが、20世紀中盤頃のモノクロ・レーシング・カー映像というのも、アイロニカルに「速度」という問題を描いているように思えて興味深い。必見である。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE