MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Thomas Ankersmit- Figueroa Terrace
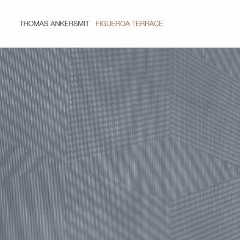
トーマス・アンカーシュミット。ベルリンのサウンド・アーティストである。1979年生まれ。彼はサージ・アナログ・モジュラー・シンセサイザーを用いて音の運動/残響を作品として提示する音響作家だ。演奏活動をはじめる以前からインスタレーション作品を中心に創作してきたアーティストでもあった。しかも彼はサックス奏者でもある。
録音作品としては、ジム・オルークとのスプリット盤『ウェールジン/オシレータズ・アンド・ギターズ』(2005)、ライヴ盤『ライヴ・イン・ユトレヒト』(2010)、人気レーベル〈パン〉からヴァレリオ・トリコリとの競演盤『フォーマII』(2011)などをリリースし、電子音楽家としても知る人ぞ知る存在であった。昨年、フィル・ニブロックとともに来日し、ライヴ演奏を繰り広げたことでも知られる。
今回のリリースは、UKの実験音楽レーベルの名門〈タッチ〉から。ジョン・ウォーゼンクロフトによるクールかつ瀟洒なアートワークに包まれてはいるものの、音の方は極めてハードコアな電子音楽作品に仕上がっており、マニアには堪らない作品といえよう(今回は彼の演奏するサックスは入っていない)。その電子音の快楽は、ノイズ・ミュージック・ファンにも十二分にアピールできるはずだ。
本作は、2011年から2012年にかけて、ロスアンジェルスのカルアーツ・エレクトロニック・ミュージック・スタジオに招かれたトーマス・アンカーシュミットが、完全復元されたブラック・サージなるシステムを用いることで演奏・録音された。よって、このアルバムには、サージ・アナログ・モジュラー・シンセサイザーの音しか(たぶん)入っていない。ここにあるのは電子音マニアを狂喜させるノイズの横溢だ。アルバムは計36分52秒、長尺1トラックのハードコアな構成となっている。
この電子音・ノイズの運動/生成が、あるシステムに則ったコンポジションなのか、それともあるルールの上でのインプロヴィゼーションなのか、それはわからない。デジタル・エディットはされていないという。しかし音は複雑に変化と変形を重ね、いくつものノイズが折り重なっていくのである。まるでエディットされているかのように精密に、かつ大胆に。となれば、これはサージ・アナログ・モジュラー・シンセサイザーの機能をフルに活用し、生まれたサウンドだといえるはずである。
では、この作品はサージ・アナログ・モジュラー・シンセサイザーのパフォーマンスを録音として凍結した一種のパフォーマンス・アート作品なのだろうか。音の実験・実験の音のように、である。だが、電子音楽の聴き手であればあるほど、本作を再生した瞬間から溢れ出てくる、鋭く、透明な電子音の横溢に、これは「ノイズ/音楽」であると確信するはずだ。
ループされる電子音に、透明で強靭なノイズがレイヤーされ、その電子音が生成し拡張する。何かを握り潰すような音、早回しのモールス信号のような音、暴風のようなノイズ。砂の音のようなサラサラと乾いた音。静謐な響き。ノイズによる耳のマッサージ。さらに後半に差し掛かると、鏡に反射する光のようにさらなる電子音が生成しはじめる。ああ、これは単なる音の運動ではない、音響的聴取を目的とした「演奏」であり、その「録音」であり、「音楽」だ。即興の生成と音の構築が同時に行われているのだから。まさに、電子の「ノイズ/音楽」!
デジタル・エディットを使わずに制作されたというが、その音の運動には圧倒的な情報量が圧縮されているように思えた。そして、これが重要なのだが、ポスト=デジタル・ミュージック以降の精密な聴取にも耐えうる密度と運動感を備えているのだ。
そう、1979年生まれのトーマス・アンカーシュミットは、70年代のアナログ・シンセサイザーを用いながらも、2000年代以降の電子音響、つまりポスト=デジタル時代のエレクトロニクス・ミュージックを生み出している。本作が「現在進行形の電子音楽作品」たるゆえんはそこにある。その情報量の圧縮と速度感において(音楽のフォームはまるで違えども)、shotahiramaの『post punk』を思い出した。時代と共に疾走するような「音楽」を生み出すためには、即興と作曲が同時に巻き起こり、ノイズと速度が拮抗しあうような密度が必要になるからだろうか。私見だが、この2作品はまるで兄弟のように似ていると思う。
もしかすると現在においては、「ノン・エディットによって生まれる情報の圧縮感覚」は重要なタームなのかも知れない。情報の圧縮と解凍の速度こそが、本作を旧来の電子音楽やノイズ・ミュージックを分け隔てる点ではないか。
さらにはノイジーな音響に挟まれるように、静謐な響きへと変化するパートも素晴らしい。まるで澄んだ空気のような、もしくは美しく乾いた砂時計のような美しい高音の持続。もしくは虫の音のような響き。そしてアクセントのように鳴り響くノイズ。この時間が凝固と解凍を往復するようなクリスタル/ノイズなアンビエンスは、アルバム全体に横溢する電子音の中で特別なきらめきを持っているように思えた。
同時にそのような持続感覚を楽曲=演奏の中盤に持ってくるトーマス・アンカーシュミットの音楽家=演奏家としてのセンスのよさにも唸らされた。また後半、サウンドがダイナミズムを再生する展開も、単なるノイズの暴発になっていない点はさすがだ。
もしかすると本盤は、ここ数年の間に〈タッチ〉がリリースした作品の中で、もっともハードコアかつ重要なアルバムかもしれない。あのブルース・ギルバート&BAW『ディルーバイアル』(2013)に匹敵するほどに。つまりは本年のエクスペリメンタル・ミュージックの重要作という意味だ。実験電子音楽に興味をお持ちの方ならば絶対必聴の盤である。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE

