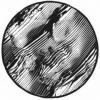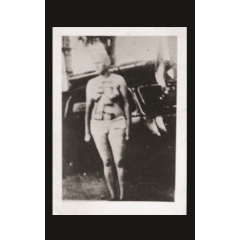MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Form A Log- For The Records
これは2014年のギャグ・アルバム、No.1でしょう。マティアス・アグアーヨやメリディアン・ブラザーズなど、ここ数年、南米に持っていかれっぱなしだった笑いをアメリカに取り戻した3人組。フィラデルフィアからプロフライゲイト(Profligate)ことノア・アンソニー(Noah Anthony)、コンテナー(Container)ことレン・ショーフィールド(Ren Schofield)、ディナー・ミュージック(Dinner Music)ことリック・ウィーヴァー(Rick Weaver)によるスラップスティックの玉手箱です。アナログ盤としては『ザ・トゥー・ベンジーズ(The Two Benji's)に続く2作めで、笑いの角度が少し内側に向くことで弾けるような攻撃性よりもじわじわと効いてくるタイプに発展途上しています。最近のコメディ映画でいえば『なんちゃって家族』よりも『俺たちニュースキャスター』か。感傷性の裏打ちではなく、フォックスTVの右傾化を揶揄しまくった毒のある感じを思わせる。
〈ノット・ノット・ファン〉からデビューしたプロフライゲイトは基調がどこまでもインダストリアルだったし、〈スペクトラム・シュプール〉から2枚のアルバムをリリースしているコンテナーはインダストリアル・イタロ・ディスコとでもいいたくなるテクノ未満の強迫的なビートの反復がメイン。しかし、同じようにアンダーグラウンドに沈みきっていてもカセットばかり出しまくるディナー・ミュージックは奇怪な作風に振り切れまくり、何が中心にあるかもわからない存在なので、アンソニーもショーフィールドもこの人の磁場に引きずりこまれて、いつしか接点がお笑いになってしまったと考えるのが自然なのだろうか(リリー・フランキーやピエール瀧が集まると老人殺しの映画になる感じ?)。
ある意味、ディナー・ミュージックの八方破りな音楽性はこれでもひとつの方向性を持つようになったといえ、少しは掴みどころというものができたというか。かつてゼロ年代にウルフ・アイズやバーニング・スター・コアといった混沌から最終的にはアンビエント・ドローンが導かれていったパターンとは異なる混沌からちがう種類のものが生まれつつあるのかもしれない。どこから来るのか、その余裕。ジャケットがどうして法廷なんだろうと思ったら、実際にニュー・ヨークの法廷でライヴ録音されたものだという。3人とも演奏しているのはテープのみ。
オープニングはそれこそディナー・ミュージック。ジャズ・ピアノの響きと木槌を叩く音と傍聴席のざわめきにはじまり、ハーシュ・ノイズにグルーヴィーなベース・ライン、さらにはギター・ソロのループに各種のブリープ音と容易には把握しきれない音楽性の洪水がつづく。ただし、グジャグジャではない。リズムもシャッフルを効かせたものが何曲か。ジャド・フェアーとマウス・オン・マーズを足してミュージック・コンクレートで割った感じだったり、ピエール・アンリとディーヴォをアレックス・パタースンがマッシュ・アップしているようだったり、もしくはバットホール・サーファーズがノイエ・ドイッチェ・ヴェレと化したとも、ハーバートがフライング・リザーズをリミックスしたとも(あ、なんで、それないんだ?)。ポップ・ミュージックではよく「なんでもあり」という形容がされるけれど、実験音楽でそのような状態になったものと思えばいいのかもしれない。つーか、ポップ・ミュージックと実験音楽の境すらないに等しいかも。千変万化のおもしろさです。
ベルギーのフィオーク(Fyoelk)やナスラックス、アメリカのナッティマルに日本の食品まつり……笑わせてくれる人はみんな好きだなー。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE