MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Deerhoof- La Isla Bonita
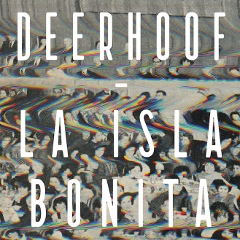
「あー残念」というタフさ木津毅
「オー、バマー」と、このアルバムの最終曲のタイトルを口にしてみるときの、この脱力感をどう消化すればいいのだろう。たしかに6年ほど前、この言葉はもっと威勢よく、熱狂とともに短く「オバマ!」と発音されていたはずだ。だが、バンドの顔であるサトミ・マツザキ本人の手による対訳には、“Oh Bummer”の横に日本語で「あー残念」とはっきりと書いてある。あー残念……。結局軍需産業から逃れられない政府の下で暮らしていたら、こう言いたくなる気持ちもわからないではない。これがちょっとしたシャレであったとしても、いま、「オー、バマー」と言うことのアンビヴァレントな感覚は簡単に冗談で済まされないところもある(『安倍ンジャーズ』という風刺画を描くのとはわけが違う)。「オバマ!」とかつて大きく叫んだひとほど、先が見えづらい時代だ。
ディアフーフは新譜が出るたびに「こんな音だったっけ?」と思わせる、独自の訛りを持ちつつもさりげなく新しい語彙を挿しこみ続けてきたバンドだが、それは彼女らがどんなトレンド=熱狂にも大きくは与してこなかったことが関係しているのだろう。サウンドの同時代性とは関係のないところで、あくまでマイペースに、外界とは異なる時空の流れで冒険を繰り広げるのがディアフーフの飄々としたサヴァイヴであった。前々作『ディアフーフvsイーヴィル』というタイトルそのものが、そうした自分たちのあり方の宣誓のように聞こえたものだ。
結成20年となりますます結束が固くなっているであろうバンドの新作『ラ・イスラ・ボニータ』はそして、おそろしくソリッドな音が張り巡らされているように聞こえる。鉄線のように固く同時に肌をこするようにざらついたエレキ、タイトでキビキビとしたリズム、単刀直入に垂直に入ってくる各パート。チャイルドライクと形容され続けてきたサトミ・マツザキの声は変わらずチャーミングだが甘えた響きはなく、ときおり驚くほどドライに放たれている。攻撃的で、ミニマルかつエキセントリックで、怒りすら感じられる。バトルスの『グロス・ドロップ』とザ・フレーミング・リップス『エンブリオニック』の合いの子、ソニック・ユースとESGとボアダムスが集まって繰り広げるパーティ……。これまでもディアフーフはノイジーで獰猛だったが、その野性が極めて冷静に、かつダイレクトに放出されたアルバムである。
アメリカに対して、いや、「アメリカで暮らすこと」に対して辛辣な視線が向けられている歌詞も相まって、その攻撃性が鋭く感じられるのかもしれない。“ドゥーム”(この曲名は「破滅」と訳されている)では「東海岸でどう暮らしたい? 西海岸でどう暮らしたい? 真ん中でどう暮らしたい?」と問いかけながら、オチで「それとも貯金してオランダかスカンジナビアにいく?」と明かせば結局そこに大した差はないという諦念が漂っているし、流行の移り変わりに言及していると思われる“ラスト・ファッド”の「悲しみのドル札で壁を覆いつくすんだ」という言葉も示唆的だ。アルバムでも一、二を争うスラッシーさのノイズ・トラック“イグジット・オンリー”では、「訪問ありがとう/いますぐ出て行ってくれ」と現在のアメリカの排他的なあり方を皮肉っているように聞こえる。直接的にポリティカルな言葉はなくとも、サトミ・マツザキの異邦人としての視点とバンドのアイロニカルな知性とが交錯し、たっぷりと含みが込められている。
しかしながら、それでも『ラ・イスラ・ボニータ』は愉しいアルバムだ。先述した“ドゥーム”で「拒絶」を意味する「deny」が「ディナ、ハハイ」とサトミ・マツザキの独特のリズム感で発せられるとき、そこにはディアフーフ的、としか言いようのない脱臼感のあるダンスが生まれている。“ビッグ・ハウス・ワルツ”では「ディアフーフが君にカオスをプレゼントしたい」と叫ばれ、ヘヴィなギターが降り注ぐ。「耳をあそばせよう/解き放て/感じて/盛り上がろう」。
現在の日本での息苦しさとアメリカでの暮らしづらさは単純に比べられるものではないだろうが、それでも「あー残念」と言いながら混沌とノイズを積極的に楽しもうとするディアフーフのサウンドには、ビリビリとした刺激を感じずにはいられない。この20年を生き抜いてきたディアフーフのタフさとはつまり何なのか、が明快に差し出されていて気持ちいい。
文:木津毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE
