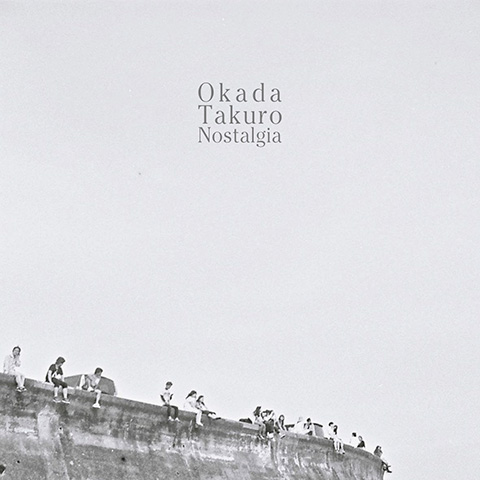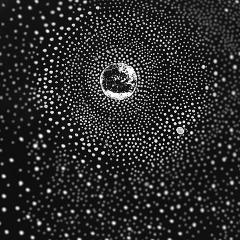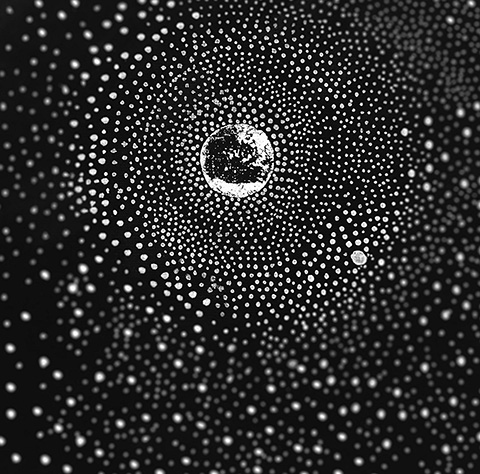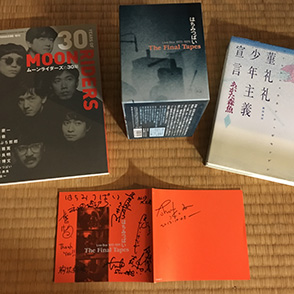MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 森は生きている- グッド・ナイト
ドリーミーだからといって逃避的なわけではない。必ずしも。森は生きているはいくつかの矛盾を抱えたバンドである。アメリカの田舎の風景を幻視するようでありながらあくまで日本の都市に立脚していると感じさせ、玄人的としか言いようのない多様な音楽的語彙に支えられながらもポップスとしての人懐こさもあり、牧歌的であると同時に不穏さもあり、老練なようでいてどこか青臭く、そして、サイケデリックでありながら意識は覚醒している。いや、これらはそもそも相反するようなことではないのだろう。そうしたことが緩やかに音楽のなかで共存しているコミュニティが森は生きている、である。
コミュニティ……森は生きているはザ・バンドの21世紀における日本語ロックのヴァージョンというよりは、聴いていると自分にはアメリカのフォーク・ロック周辺で6、7年前に起こったことを総ざらいしている感覚に陥る。“フリー・”ではなく純然なフォーク感覚があること、戦前にまで遡るルーツ音楽を発掘しながらそれを現代の音楽的文脈に乗せること、多楽器によって生み出されるチェンバー・ロック要素が強いこと、非西洋の音楽がふんだんに盛り込まれていること、そして緻密なコーラス・ワークとアンサンブルによる“ハーモニー”すなわちコミューナルなムードがあること。それはアメリカにおいては、保守的に偏狭になっていく国と時代に対する、意識的あるいは無意識的な抵抗でありオルナタティヴの表明だった。森は生きているはこの国においては独自なように見えるが、日本でいま起こっていることを思えば、(彼ら自身が自覚的であるかは別としても)若い世代からのようやくの、そしてごくまっとうな意思表明だと言える。
セカンド・アルバムとなる『グッド・ナイト』はまず、手の込んだ録音によって音響が飛躍的に厚くなり、そのことによって隠喩ではない「森」の響きに近づいている。鍵盤とフルートの響きがどこまでも清廉としたワルツ“磨硝子”の後半2分半の音々のがちゃがちゃとしたざわめきは、木々の葉の隙間からこぼれる陽光以外の何物でもない。それはずっとここに留まっていたい……と思わされるピースフルなものだが、そこはひとりで引きこもる場所ではなく、多人数によって生み出されたものなのである。「森」はさまざまな生命が息づく総体であり、それが「生きている」。たしかに音楽的要素は多様ではあるが、多くのバンドのセカンド・アルバムのように前作の反動的にいろいろやった、という風な印象は受けない。バンドのアイデンティティを深めたアルバムだ。
アルバム中の音楽的な白眉は間違いなく組曲形式となった“煙夜の夢”だろう。エキゾチックでジャジーなサイケ・ジャムはどこまでも上りつめ、しかし「あちら側」には行かず、メロウなフォーク・ロック、ソフト・ロックへと帰還し、柔らかな陶酔をゆっくりと広げていく。コーラスと悪戯っぽく微笑みを交わす、よく響く鍵盤打楽器はそれ自体が雄弁にアンサンブルに光を注いでいる。また、オルタナ・カントリーなんて言葉をつい思い出してしまう、ウィルコの諸作を彷彿させる“青磁色の空”における時間を引き延ばすかのようなギターの音の余韻は、現代の日本においてめったに聴けないものだ。彼らは彼らのボヘミアニズムを、音の鳴りの良さでこそ説得力のあるものへと高めている。
「星座なんて知らないほうが 空は不思議に見える」
夢も同じことで 不思議なままでいい
“気まぐれな朝”
ファースト・アルバムから頻出した夢というモチーフはここでも何度も繰り返される。たしかに、森は生きているのサイケデリアは白昼夢的だが、しかし彼らが鳴らす「夢」がある目的――たとえば、現実を直視したくないから逃げ込むためのものといったような――に向かってのみ取り出されているようには、どうしても思えない。それは都市であらためて夢想される「森」のようなものであり、そこで降り注ぐ陽光であり、ここで言うように「不思議なままでいい」ものである。「知らないほうがいい」というのはイノセントであることを標榜しているのではなく、想像の余地を残しておくことで夢のスケールを広げるということだ。
森は生きているの音楽は、コミューナルなアンサンブルを掲げ、想像上の「森」を作り上げてしまう。いまは60年代でもないし、ここはアメリカでもない。閉鎖的な21世紀の日本においてそれをやってのける、若々しく凛々しい眼差し。これを理想主義と呼ばずして何と言うのだろう。
だからアルバムのタイトルは「グッド・ナイト」、夢を見る合図なのである。ラストのタイトル・トラックはワルツだ。夢のなかの舞台のための舞踏音楽で、バンドはこんな風に語りかける。「ねぇ 今どこにいるの ねぇ? さぁ? まだ夢の続き さぁ」。その通り、僕たちは夢の続きにいる。
木津毅
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE