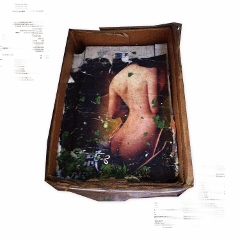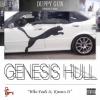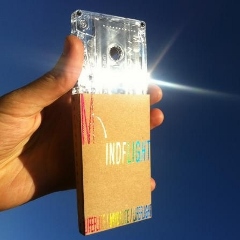MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > D/P/I- MN.ROY
「私は死にたいのに、命がせまってくる」とはマリリン・モンローの言だけれど、これでもかという不協和音の連続に「僕は耳をふさぎたいのに、音楽とは違う何かがせまってくる」という感じか。いや、というよりも、これは本当に不協和音なのだろうか。たとえば「ドミソ」は平均律が確立された17世紀には耳をふさぎたくなるような不協和音とされていたらしい(その前に教会は近世まで和音そのものを禁じていた)。言ってみれば、ある種の音の組み合わせが快か不快かはそれぞれの時代の集団的な思い込みでしかないということで、金本位制度が停止してからのマネーの信用度と同じく、「みんな」があると思わなければ、その制度は崩壊するのと同じといえば同じである。ということは21世紀よりも17世紀に近い18世紀のモーツァルトが現代と同じ感覚で人々の心に入り込むことはなかっただろうとも思えてくるし、メスメリズムで無意識を書き換えでもしなければ、モーツアルトが実際にはどんな聴かれ方をしていたかは現代人にはわからないということにもなる。あるいは、それを現代の先取りだったと言い換えて済ましてしまえば済むことでもあるし、実際に当時の人たちから熱烈に歓迎されることがなかったからモーツァルトは35歳で野垂れ死んでしまったわけだし(ちなみに12音技法で平均律を打破したと思ったシェーンベルクがむしろ観客に訴えられるというラン・オーヴァーも西洋音楽史は経験している)。
ヴェイパーウェイヴとミュージック・コンクレートの境界を巧みに縫い合わせてきたアレックス・グレイによるアブストラクト・サイドの6作めにして初の正規CD作は、いままでの彼の試行錯誤を違う方向に振り向けはじめた意欲作に思える。それこそいままでの作品がヴェイパーウェイヴと捉えられてきたことに反発心でもあるのか、『MN.ロイ』は全体に硬い表情を貫き、DJパープル・イメージの出発点がアヘンで気持ちよくなっちゃった状態をそのまま投げ出したような『ヘッド・ティアー・オブ・ザ・ドランケン・サン』(2012)だったことを思うと、この変化は軸足をミュージック・コンクレートに移し、ピエール・アンリの現代版をつくりあげようという気迫の産物としか思えない。少なくともサンプリングの元ネタに食われてしまったというのか、スノビズムの泥沼にはまってしまったとしか思えないヴェイパーウェイヴとははっきりと距離を置くようなところがあり、そのようにして生まれたポピュラー・ミュージックとの距離感は初期の〈メゴ〉作品を想起させるところが多々ある。誤解を恐れずにいえば、OPNがフェネスならD/P/Iはピタといったところだろう。考えてみれば〈メゴ〉からミュージック・コンクレートの復活を告げた『ザ・マジック・サウンド・オブ・フェン・オ・バーグ』がリリースされてからまだ15年しか経っていない。ミュージック・コンクレートのアップデートはいまだ生成変化を繰り返す途上にあり、オーストリーよりはアメリカでガッツを見せていると。
ミュージック・コンクレートを復活させたのは明らかにサンプラーの出現だった。しかし、そこで拾われる音源はかつて具体音とされたものからTVやインターネットといった電子メディアからの供給物へと様変わりし、オーソドックスな「楽器」から離れるという動機はあっさりと空無化している。あるいはそういったインプットの方法論に依拠するよりも、現在はネット上に音楽を流すというアウトプットの過程でそれぞれの文脈は捏造されるという環境に取り巻かれているため、等しくバンドキャンプで音が流されるにしても、差異化の欲望は、それらがさらにどこに向かって着地するかというコミュニケイションの質の部分に向かっていくことは必然だろう。ネット上で誰もが音源を流せるということは、単純に全体の質は低下するということでもあるから、サルヴェージの力学を相変わらずマスに置くか、コミュニティに委ねると仮定したチルウェイヴ、そうでなければ、そのようにして数を担保にすることから離れて批評言語の価値を上げることで(唯一性に基づいていた美術と同じように)作品ごとに新たな文脈を練り上げるしかない。そして、当然のことながら批評言語も数が増えれば全体の質は低下するしかないので、意地悪く言えば反知性主義の文脈で成立する音楽文化もあちこちで成立していることは想像にかたくない。そのひとつをヴェイパーウェイヴと呼ぶことに僕は抵抗をなくしてしまったけれど、そのような音楽観の存在の仕方はパンクにもあったし、レイヴにもあった。D/P/Iがこのような言葉のエンクロージャーから逃れるかどうかはわからないけれど、少なくとも彼はディレッタンティズムとは手を切りたいと願っているとしか思えない作品をここでは作り上げた(つーか、70年代のキャンプと同じ趣旨でディレッタンティズムを標榜しているのがヴェイパーウェイヴか)。ブルース・ハークやピエール・アンリがかつてテープ操作に持ち込んでいた無秩序な感性をラップ・トップに置き換えることができる才能だとしたら、この変化は必然だろう。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE