MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Wolf Eyes- I Am A Problem: Mind In Pieces
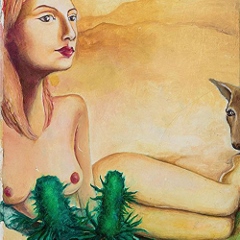
ネイト・ヤング、ジョン・オルソンにギタリストのジェイムス・バルジョーが加わり、3ピース編成の新生ウルフ・アイズとして発表した2013年の『ノー・アンサー/ローワー・フローア』に続く本作はなんとホワイト・ストライプスのジャック・ホワイトのレーベル、〈サードマン(Third Man Records)〉から。
〈アメリカン・テープス(American Tapes)〉や〈ハンソン・レコーズ(Hanson Records)〉などのミシガン・ノイズ・(ノット・)ミュージック・シーンにおいて、つねにアイコン的存在でありつづけるウルフ・アイズ。アーロン・ディロウェイ、マイク・コネリー、ネイト・ヤングにジョン・オルソン、彼らがアメリカン・ノイズの歴史と言っても過言ではない。カタログ・ナンバーは999番で止まっているが、総リリース数は余裕で1000を超える──ディスコグスで見たら998番が11枚もある!──〈アメリカン・テープス〉を主宰するジョン・オルソンが近年声高に唱える「ノイズは死んだ。われわれはトリップメタルである」とはいったいどういうこっちゃ?
90年代初頭に田野幸治氏のMSBRに触発され音楽活動とレーベルを開始したオルソンにとって、それらは単なるDIYに根ざした方法論でしかなかった。それは身の回りのガラクタで積み上げる壮大な実験であり、80年代のヨーロッパやフロリダのデスメタル等で盛んに行われたテープ・トレーディングのカルチャーと同様だ。しかしDIYゆえに生まれるミステリーとロマンがそこにはあった。多くの人間はたしかにそれらを「ノイズ」と捉えるかもしれないが、それらは極度に抽象化したロックであったり、フォークであったり、テクノであったり、音楽そのものであったのだろう。
「誰でも作れるけども唯一の音楽、誰でも作れるが唯一の形。それはコミュニケーション・ツールだ」。ジャック・ホワイトもそういったカルチャーに熱心なファンの一人であり、今回のリリースに繋がったようだ。
前作の『ノー・アンサー〜』から完全にジャムを止めてソングを奏でるようになったウルフ・アイズ。ネイトとオルソンによる超抽象ブルース・ユニットであるステア・ケース(Stare Case)にジェイムズが加わるような形でいまのウルフ・アイズは成り立っている。ジェイムズのリフを中心としたソング・ライティングの展開、またネイトとオルソンいわく、もはやドラッグや酒でハイになってジャムる年齢ではないことから、自然とコンポジションとメロディが際立つ本作は、なによりもミシガンや中西部のロックを強く感じさせる。オウサム・カラーからネガティヴ・アプローチ、果てはMC5からストゥージスまで……。
オルソンが自称するトリップ・メタルには正確な定義はない。それは単に彼の美意識に共鳴するものであれば何でもいいわけである。それは過去数年間で多くのノイジシシャンがなんちゃってテクノをプレイすることへの皮肉とも捉えられるし、メディアとツールの発達から生じる現在のアマチュアリズムが、彼がこれまで愛してきた「誰でも作れるけども唯一の音楽、誰でも作れるが唯一の形というコミュニケーション・ツール」という「ノイズ」を殺したということかもしれない。アンダー・グラウンドDIYカルチャーに社会性を与えることはけっして悪いことではないし、ネットを通じて自分の自分による自分のための超一方通行の作品発表を行うことこそ今日的な方法論であることはわかっている。しかし僕はこのアルバムを聴きながらウルフ・アイズがこれまで築いてきた膨大なアナクロの山に思いを馳せている。
倉本諒
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE


