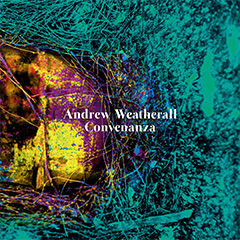MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Andrew Weatherall- Convenanza
音楽を聴き続けている者として、ひとつの好奇心、興味、関心のあり方として自分と同年齢の者がどのような表現の変遷、作家活動を辿るのだろうか、というのがある。ぼくより年下の人にもぜひ意識することをオススメしたい。自分と同じ歳で共感できるミュージシャンを探すことである。自分が25歳のときに、同じく25歳のあいつはこんな音楽を作って、35歳のときはこんな音楽を作ったと。そういうふうに聴いていると、なにかと考えさせられることがある。ときには励みにもなる。
ぼくと同じ歳のミュージシャンというと、──ミュージシャンというよりDJだが──、デリック・メイとジェフ・ミルズがいる。この人たちは、しかしこう言ってはナンだが〝ハイパー〟なので、じつはそれほど同年齢意識を持っているわけではない。日本では菊地成孔がまったく同じ歳で、辿ってきた音楽体験が違いすぎるのだけれど、やはり、わかるところはすごくわかることがある。彼の近著『レクイエムの名手』がまさにそうだった。
アンドリュー・ウェザオールもぼくと同じ歳である。今年で53歳という、立派な中年だ。そしていま〝中年〟であること、それはぼくがウェザオールに抱く関心のひとつとしてある。
そもそも、アシッド・ハウス/テクノを直撃した世代の多くは、いま中年期に差し掛かっている。現役でがんばっているDJの多くも中年になってきた。この中年期は、ひとの人生においてじつにむずかしい。以下、エドワード・W・サイードの文章を引用する。
中年期という年頃は、より明快に定義された二つの時期や事柄の間に挟まれたものの常として、かくべつ有益なものとはみられてこなかった。もはや将来を嘱望された青年でもなく、かといって敬われる老人でもない。不惑を過ぎてなお反抗的な若者ぶってもしばしば愚かしく、いっぽうで早くから老いた重鎮のようにみなされてしまうと、おぞましい尊大さや制度そのもものの厳格さを背負うことになりかねない。(中略)中年期は不確実性と、ある種の喪失性、身体的な弱さ、心気症、不安とノスタルジーの時期である。大多数の人びとにとって初めて死を意識するようになる時期でもある。
いずれにしても、いま述べたことは経験にもとづいた現実の一部である。(中略)しかし誰であれ実際に中年にさしかかった者にとって、喜ぶよりは考えさせることのほうが多い。過去を繰り返すことなく(いっぽう悲しくもありがちないように)過去を裏切ることも避けながら、そこから学びつつあらためて来し方行く末を思い、猪突猛進してきたそれまでのエネルギーを新たな現実に合わせて修正しなければならないからである。あらゆる決まり文句が示唆するとおり、野暮ったく退屈な、色褪せた状態にもそれなりの真実はある。そしてそれが中年というものなのだ。
エドワード・W・サイード『サイード音楽評論』二木麻里訳
なんの反論もない。思春期はたしかに人生においてむずかしい季節だが、中年期もすごくむずかしいのである。そのむずかしい季節をアンドリュー・ウェザオールは試行錯誤しながら生きている。ぼくと同じようにだ。
そのアンドリュー・ウェザオール、彼こそはアシッド・ハウスにイングランドのゴシック趣味を注いだ張本人、彼こそは誰もがスニーカーを履いていた時代にラバーソウルを履いてDJをしていた男、彼こそは誰もが太陽を歌った時代に雨と霧を愛した人物である。近年流行っているゴシック/インダストリルの美学なんぞは、90年代の愛(バレアリック)の季節から表現し続けている。凡庸なDJがそんなことをすればただの異端児だが、ウェザオールという男は、その手の掟破りを最高に格好良く思わせてしまうのだ。彼の才能は、迎合しないその非凡なセンス、それをやってしまう思い切りの良さ、きわめて英国的な目利きにある。
ロッターズ・ゴルフ・クラブとは彼のレーベル名であるが、この「ゴルフ・クラブ」という言葉を持ってくるところがいかにも彼らしい。ゴルフ・ファッションの元となったラウンジ・スーツは、19世紀つまりヴィクトリア朝時代の後期に流行っている。それはその時代のアウトドア・ファッションである。また最近の彼は顎ひげを生やし、ワークシャツを着ている。これも19世紀から20世紀初頭にかけての英国のスタイルだが、こうした服装からも読み取れることは、彼が〝現在〟に対して深い疑問を抱いているということだ。
ファンションの問題もあるだろう。近年のウェザオールには見習うべきところがある。もしぼくが40代〜50代をターゲットにするファッション誌の編集者だったら、間違いなくこの男を特集するだろう。多少やり過ぎのところはあるが、もっともむずかしい中年期の身だしなみを彼になりに表現しているからだ。
とはいえ、完璧な人間などいやしない。ウェザオールは、いまから12年前、中年期を目前としながらロカビリーを取り入れたことがある。41歳において過度に若者ぶったのだが、この気持ちもわかる。この年頃にありがちな、俺はまだいけるんだという、最後のあがきなのだ。そういう意味でウェザオールの作品からは、人生を生きるひとりの人間としての迷いや恐れといったものを感じるし、今作が7年ぶりになったのは、やはりこの歳のむずかしさがあったのだろう。誰もがいつでも時代に乗れるわけではない。
俺たちは川に蹴りを入れている
流れを止めようとして
無理そうな気がしてきたんだ
俺が願うほうには流れていきそうにない
“Kick In The River”
先日書いたYuri Shulginのレヴューからも続く話だが、アンドリュー・ウェザオールがアシッド・ハウスのなかに注いだゴシック(リヴァイヴァル)運動は、ヴィクトリア朝時代の産業革命への抵抗の表れだった。いま起きている現実の変化こそ悪夢にほかならない。19世紀のテクノロジーの革新による変化をうながす原動力は資本主義だったが、それは現代にも通じる話であり、ゴシックという名の警鐘がいままさに打ち鳴らされていることはここ数年の音楽シーンをみればよくわかる。ゴシックの作家たちが150年前の最新テクノロジーを有効利用したように、彼らもデジタルを使いながらデジタル化社会を批判する。
しかし、アンドリュー・ウェザオールという、その知性と趣味の良さ、アティチュードによって、長きにわたってDJカルチャーのトレンドに多大なる影響を与えてきた人物の最新ソロ作品は、ハウスでもテクノでも、トリップホップでもない。場末のライヴハウスで10人の客を相手に演奏する、誤解を恐れずに言えばうだつのあがらないバンドのようだ。強烈なまでにくみしたいと願うダンス・ミュージックのスタイルがいまの彼にはないのかもしれない。これもまた一考に値することだが、泉智のレヴューのように長くなってしまったので、先を急ごう。
場末のライヴハウスで10人相手にするようなバンドは、ある意味では自由である。世間からのプレッシャーもなければ、自らを追い詰めるようなオブセッションもない。過去を美化するノスタルジーもない。曲が出来て、歌詞が書ければ、楽曲は生まれる。『コンヴェナンザ』は、いまのアンドリュー・ウェザオールの気持ちをもってして生まれた誠実な作品である。「野暮ったく退屈な、色褪せた状態にもそれなりの真実はある」とサイードが言うように、ここには若さゆえの勢い、老境ゆえの悟りにはない真実がある。
どうかこの手紙を許して欲しい
難破した魂が綴ったんだ
残骸の専門家 砕けた石のなかで失われた名前
どんな祈りも僕を救えなかった
もう一度亡霊を呼び出そう
“Ghosts Again”
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE