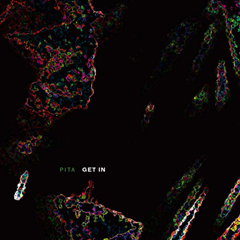MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kassel Jaeger & Jim O’Rourke- Wakes On Cerulean

カッセル・イエーガーとジム・オルークのコラボレーション・アルバム『ウェイクス・オン・セルリアン』が、〈エディションズ・メゴ〉からリリースされた。近年のこの種の音響作品にあって、特筆すべき出来栄えであり、このアルバムを機にカッセル・イエーガーという稀有なサウンド・アーティストの名は、さらに広まっていくことになるのではないか。
そこでまず、カッセル・イエーガーについて、若干の素描を試みたい(ジム・オルークについては、いまさら説明する必要もないだろう)。彼は、1981年生まれのフランス人サウンド・アーティストである。INA-GRMのエンジニアとしても知られている。INA-GRMは、フランス国立視聴覚研究所・音楽研究グループ(Le Groupe de Recherches Musicales)のことで、あのピエール・シェフェールによって1958年に設立されたことでも知られる組織・機関(1975年にフランス国立視聴覚研究所と統合)。フランソワ・ベイル、リュック・フェラーリ、ベルナール・パルメジャーニ、ヤニス・クセナキスら錚々たる音楽家たちがメンバーとして関わってきたことからも分かるように、電子音楽やミュジーク・コンクレートの歴史においても極めて重要な機関である。と、書くだけでもINA-GRMのエンジニアであることがいかに特別な存在であるかが分かってくるだろう。
カッセル・イエーガーは、フランソワ・ボネ名義で〈エディションズ・メゴ〉傘下でGRMの電子音楽再発レーベル〈リコレクション・ジー・アール・エム〉のコーディネイションからエンジニアリングにまで関わり、困難であろう数々の再発に尽力してきた。いわば2010年代において「電子音楽/ミュジーク・コンクレート」の歴史を、われわれに再発見させてきた重要人物のひとりである。
むろん、ソロ・アーティスト、カッセル・イエーガーとしての活動も活発である。ジュゼッペ・イエラシ主宰〈セヌフォ・エディションズ〉や、フランスの実験音楽レーベル〈シェルター・プレス〉、老舗〈エディションズ・メゴ〉などから着実にアルバムなどのリリースを重ねてきた。昨年は〈シャルター・プレス〉から発売されたステファン・マシューやアキラ・ラブレーとの共作『ザウバーバーグ』も傑作であった。
カッセル・イエーガーのサウンドは、ミュジーク・コンクレート的な技法を主体としつつも、どこか不可思議な空気感が特徴である。どこか謎めいた物語性を感じる音響構成とでもいうべきか(『ザウバーバーグ』は、トーマス・マンの小説をモチーフにした作品だった)。
その意味で、本作『ウェイクス・オン・セルリアン』におけるジム・オルークとの共演は、個性の近いアーティストの共作といえる。オルークの音響作品もまた物語性が濃厚だからだ。ただ、カッセル・イエーガーは、物語性が音響のレイヤー=縦軸から生まれていくのに対して、オルークは、音楽の進行=横軸によって生まれるという差異がある。本作においては、その差異が良い方向に作用している。縦軸と横軸、つまりレイヤーと時間の交錯が、とても濃厚なのである。音楽的な旋律の欠片、環境録音、アンビエントな持続音、それらが縦軸と時間軸に絶妙にコンポジションされていくことで、とても充実した音響空間と音楽的時間が生まれているのだ。
本作『ウェイクス・オン・セルリアン』は、ミュジーク・コンクレートであり、アンビエントであり、ドローンであり、フィールド・レコーディング作品でもある。泡のように飛び散る電子音、遠くのカモメのような鳴き声、水の音、時間の結晶のような持続音が交錯し、結晶していく。まるで「映像のない映画」のように、美しくも、どこか物悲しい音響世界。そこには、地中海的な「海」的なものへの詩的な感覚があるようにも思えた。「紺碧の目覚め」にふさわしいサウンドスケープが、ここにある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE