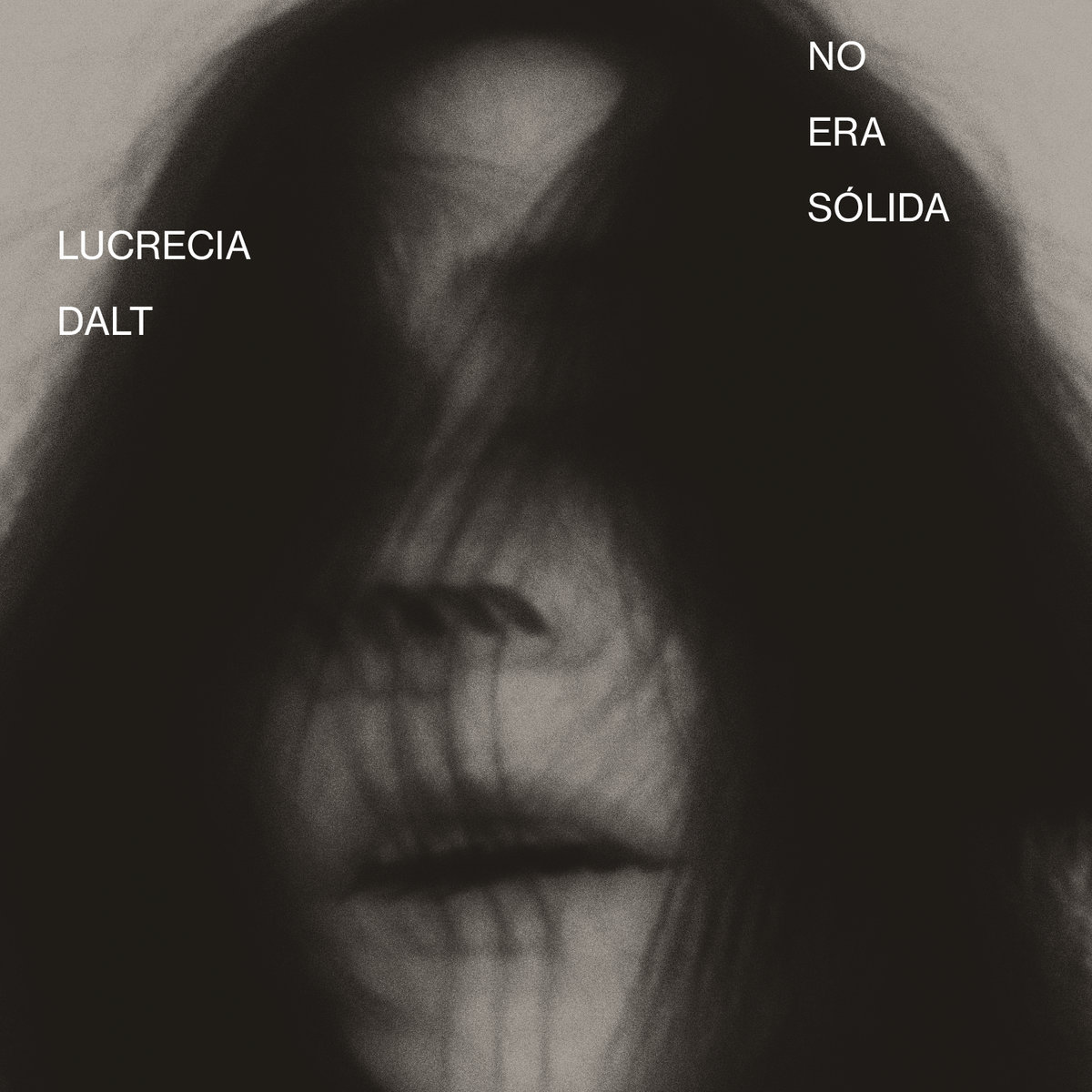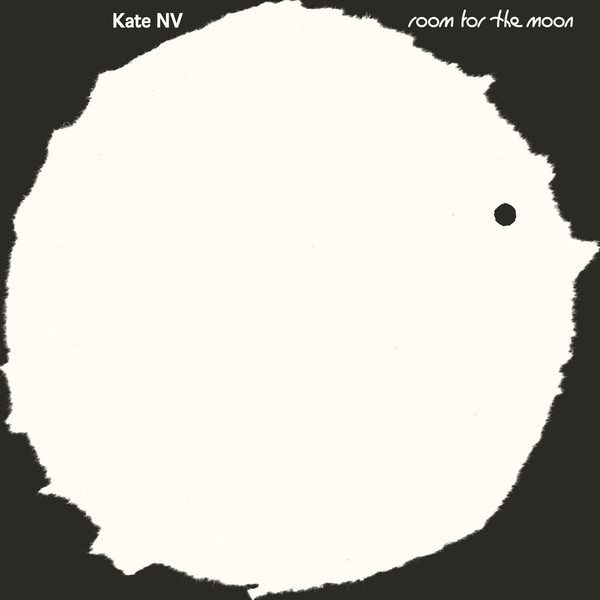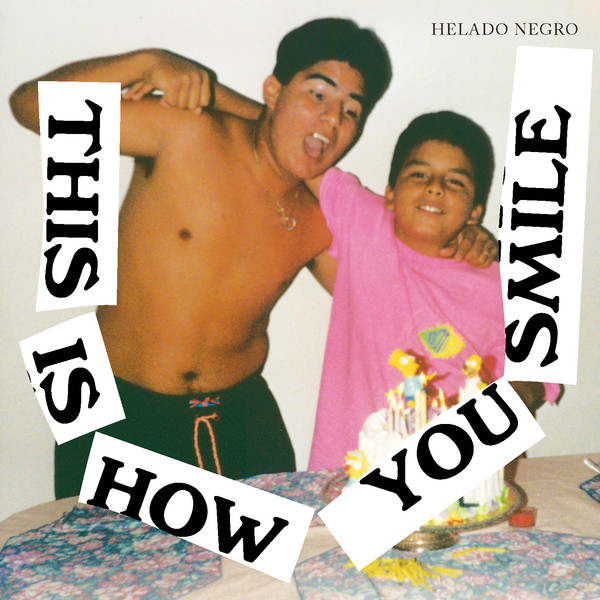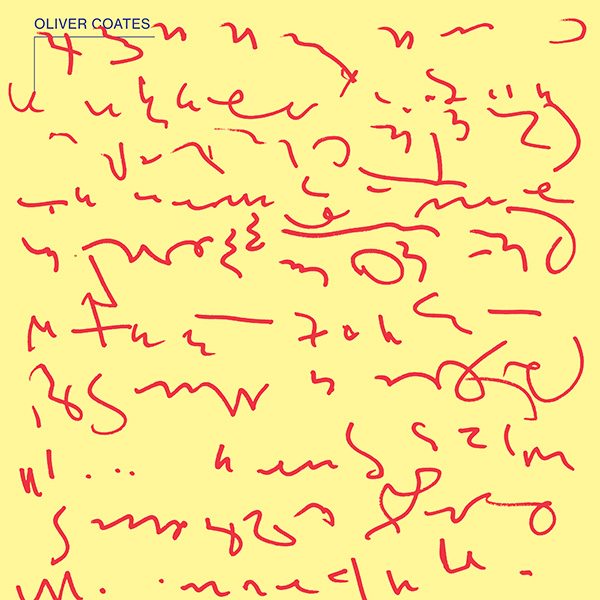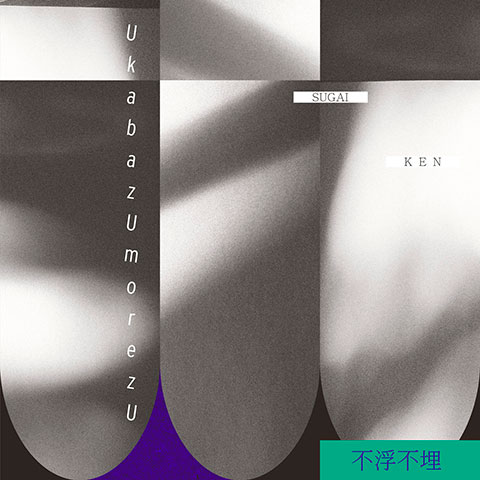MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kate NV- для FOR
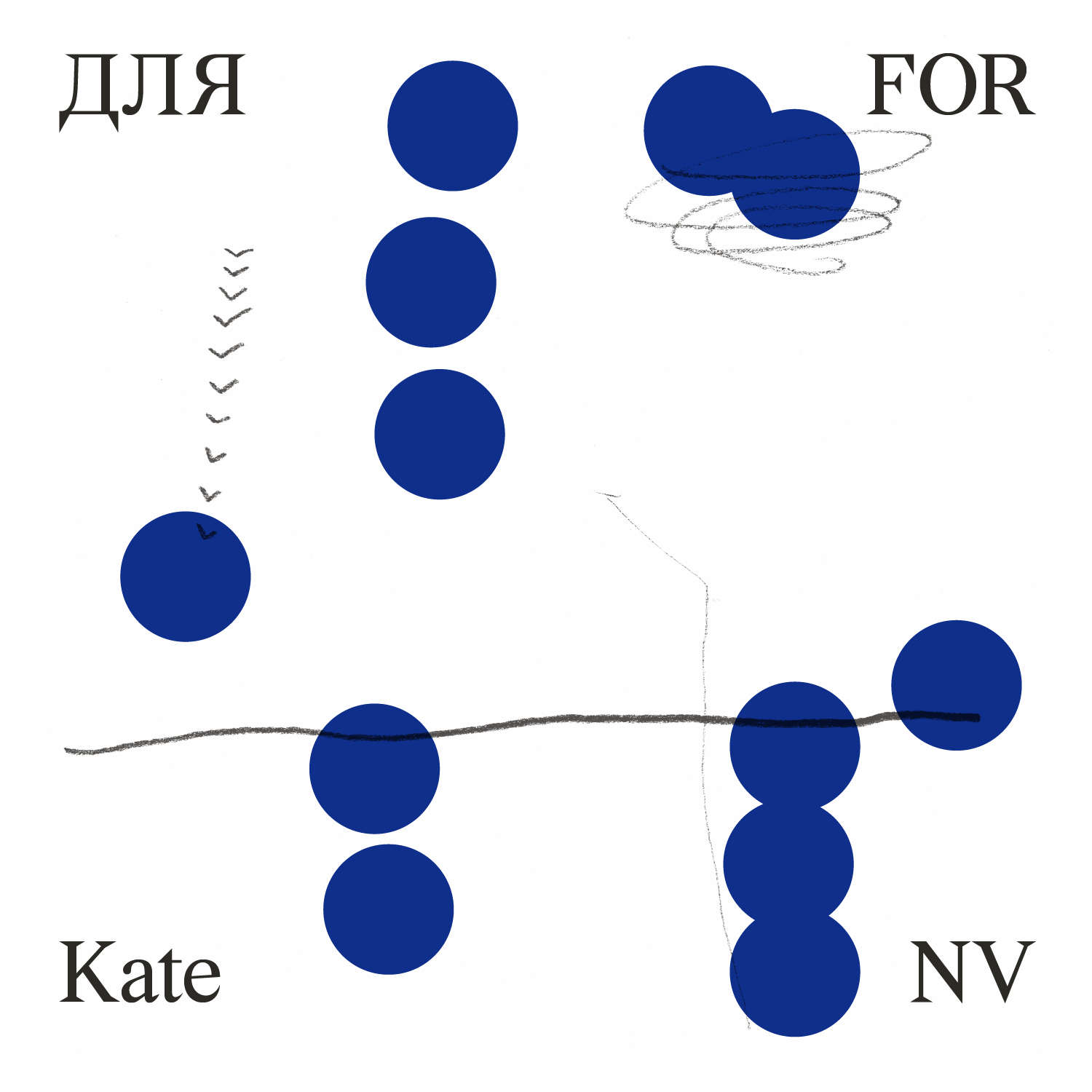
近年のニューエイジ的な音楽の評価の背景には、00年代末期以降に普及したサウンドのテクスチャーを重視したアンビエント/ドローンから10年代的なインダストリアル/テクノとエクスペリメンタル・ミュージック、80年代音楽のリヴァイヴァル、80年代から90年代初頭の音楽をアナーキズム的にリサイクルするヴェイパーウェイヴなど、複数のコンテクストが幾層にも重なり合っている。
なかでも参照元として重要な音楽は、ブライアン・イーノのアンビエント・ミュージック概念から派生した80年代初頭以降の環境音楽である。たとえばアムステルダムのレーベル〈ミュージック・フロム・メモリー〉によるジジ・マシンの再評価、吉村弘、高田みどり、芦川聡、尾島由郎、イノヤマランド、そして細野晴臣など日本産の80年代アンビエントの再発見などだ。このリヴァイヴァル・ムーヴメントは、とりあえず「ニューエイジ」と呼称されることが多いが、思想的な意味は脱色され、いわゆる未知の環境音楽として評価されている点も特徴である。
こういった静けさと実験性が同居した80年代音楽が求められているのはなぜだろうか。00年代においてアンビエント/ドローンが普及した結果、聴き手側の意識と環境が整ってきたという点と、80年代と同じように社会全般にさまざまなノイズ(音/情報)が一気に浸食してきたとう環境変化の両方の意味合いがあるのではないかとも考えられる。80年代初頭も高度資本主義による商業・広告のシステム化が整い始め、われわれの欲望が管理され始めた時期だった。都市の音環境が猥雑になり、聴覚を圧迫し始めた時代でもあった。2010年代、いわゆるSNS以降の社会も、80年代と同じくシステム化されたノイズが蔓延し、知覚を圧迫している時代である。
そう考えると70年代末期から80年代初頭にかけて都市の騒音をノイズによって塗り潰そうとしたメルツバウとイーノのアンビエント・ミュージックは、同じく「騒音化する都市・社会環境を音楽/音響によって変化させたい」という聴覚的欲求の象徴/表象/発露だったといえなくもない。となると2010年代において、ノイズ/エクスペリメンタルな音楽と、こういったニューエイジ/環境音楽が音楽のモードとして同時に聴かれている状況も同じような理由ではないかと想像できる。いま、世界は騒がしい。無駄なノイズに満ちている。1980年代と2010年代は、社会環境の速な変化によるノイズの発生という点で似ているのだ。
ロシアのKate NV(ケイト・シロノソヴァ)も同様に、そんな現代的かつ同時代的なニューエイジ/アンビエントにしてエクスペリメンタルな環境音楽家であり、2010年代後半のポップを体現するアーティストである。
ケイトはロシア・モスクワの出身で、ソニック・ユースなどの影響を受けバンドを始めたという。彼女は2013年にジャパニーズ・ポップスや90's R&Bなどの影響を受けたEP「Pink Jungle」を発表し注目を浴び、その3年後の2016年、あのGiant ClawとSeth Grahamによって主宰・運営される〈オレンジ・ミルク〉からファースト・アルバム『Binasu』をリリースするに至る(当時はNV名義)。ヴェイパーウェイヴ以降ともいえるそのサウンドは、斬新であり、奇妙であり、ポップであり、世界の各メディアから注目を浴びたのも当然かつ必然であった。このファースト・アルバムでケイトは音楽家としての存在感を確立したわけだ。
そして本年、現代のニューエイジ/アンビエントの総本山であるニューヨーク〈RVNG Intl.〉から本作『для FOR』をリリースした。音楽性はよりミニマルになり、環境と空間を意識させる独自のエクスペリメンタル・ミュージックへと変貌した。それはどこか80年代の日本のアンビエント・ミュージックを思わせもする音でもある。
じっさい、ケイト・シロノソヴァは細野晴臣や吉村弘などの80年代日本産アンビエント作品などから影響を受けているようだ。確かに『для FOR』を聴いていると、8月にニューマスター・エディションとしてリイシューされた細野晴臣プロデュースのイノヤマランドのアルバム『DANZINDAN-POJIDON』(1983)や、無印良品の店内音楽として制作しカセットブックで刊行(リリース)された細野晴臣『花に水』(1984)、昨年2017年にヴィジブル・クロークスのスペンサー・ドローン主宰の〈エンパイア・オブ・サイン〉からリイシューされた吉村弘『Music For Nine Post Cards』(1982)、今年「ピッチフォーク」の80年代ベストに選ばれた高田みどり『鏡の向こう側』(1983)、さらにはコシミハル、矢野顕子、dip in the pool、初期ピチカート・ファイヴまで1980年代初頭から中期にかけて日本で花開いた鏡のようなアンビエントやテクノ・ポップ音楽の系譜を感じてしまう。日本とロシア、1980年代初期と2010年代後期という距離と時間差がありつつも。
https://www.youtube.com/watch?v=iQ8DxYC4E0w
むろん、最近、話題にされることが多い海外からの70年代~80年代の日本ポップ音楽の再発見には「欧米から特異な場所として認識されたニッポン」というオリエンタリズムは少なからずあると思うし、この時代、過剰な「日本すごい」論は慎まなくてはならない。しかし、一方、外国文化の発見には異国への憧れは必然でもあるし、ヴィジブル・クロークスやKate NVの音楽を聴いていると、良いレコードや音楽は時代と国境を超えるという投瓶通信的な可能性を感じてしまうことも事実だ。それは一種の誤解であっても芸術による相互理解の発芽でもある(80年代末期のワールド・ミュージック・ブームのように資本主義下の搾取でおこなわれている問題はあるにせよ)。しかも現代はインターネットによって国と国との感覚的距離は消えてかけている。じっさい、本作にもロシア、日本、80年代、00年代、10年代、アンビエント、ポップ、オルタナティヴ、エクスペリメンタルなど、文脈上のさまざまな興味深い混合が聴き取ることができるのだから。『для FOR』日本盤ボーナス・トラックとして収録されている食品まつり a.k.a foodmanによるリミックスもその一端を示しているといえよう。ちなみにケイトは今年日本に来日している。そのツアーの様子を捉えたドキュメント映像「ケイト、東京の夏」も必見だ。
https://www.youtube.com/watch?v=piM7Itf1L24
さて、それらを踏まえたうえで音楽的に大切なことは、80年代のミニマリズムとミレニアム世代以降のミニマリズムの共通性に思える。
それはスティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスの60年代のミニマル・ミュージックとも違う「間と偶然のリズミック・ループ・ミニマリズム」ではないかと私は考える。その偶然性の感覚/導入ゆえ、やはりブライアン・イーノの系譜を継ぐといえなくもない(ケイト・シロノソヴァはイーノが関わりのあったコーネリアス・カーデューを再構築する「モスクワ・スクラッチ・オーケストラ」のメンバーであったというのだからイーノとケイトの音楽的な出自は意外と近い)。イタリアのミニマル作曲家ピエロ・ミレジやダニエル・バカロフを敬愛するケイト・シロノソヴァらしく、自分(の世代?)なりのミニマル音楽を追及・実践しているのだろう。
じじつ、このアルバムに収録された曲は、どのトラックも作為と偶然の境界線が消失しているのだ。簡素なフレーズはループされ、リズミックなミニマルなサウンドを形成する。それぞれのフレーズのレイヤーとループは丁寧だが、あからさまな作為は感じられない。自然だが普通ではない。いわば偶然と構築のバランスが絶妙なのである(そこにカーデュー~イーノの系譜の継承があるのだろう)。結果、独特の微かなズレと反復とでもいうべき「間」が生まれているのだ。その意味でマリンバ的な音によるリズミックなトラックM2“двA TWO”とM3“дуб OAK”は、本アルバムを象徴するトラックといえる。どこかタンゴのエッセンスをミニマル・ミュージックのループに抽出したような音楽性は、時空間が浮遊するように美しい。
M4“как HOW”、M9“пес DOG”のベースラインや入り方も絶妙だ。特にアンビエントなムードのなかで風鈴のような乾いた音は鳴り響き、絶妙なタイミングでベースがレイヤーされる“пес DOG”は本当に気持ち良い。さらには「ワシリー・カンディンスキーのポエム」を歌にしたヴォーカル・トラック“вас YOU”は、まるで〈YEN〉や〈ノン・スタンダード〉を継承するようなミニマルを基調とした21世紀型アンビエント・ポップ・ミュージックの可能性を感じてしまったほど。たとえば8月にリリースされたイノヤマランドの『DANZINDAN-POJIDON』のニューマスター・エディションと続けて聴いてみても何の違和感もなく繋がっていくように思える。
ループとズレ。反復と逸脱。均衡と不均衡。差異と反復。グリッドのしなやかな崩壊。鏡の向こうの鏡のような音。Kate NV『для FOR』には、そんな1980年代初頭から連なる2010年代後半的なミニマリズムがある。そう、文字どおりニューエイジによる環境音楽/ポップなのである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE