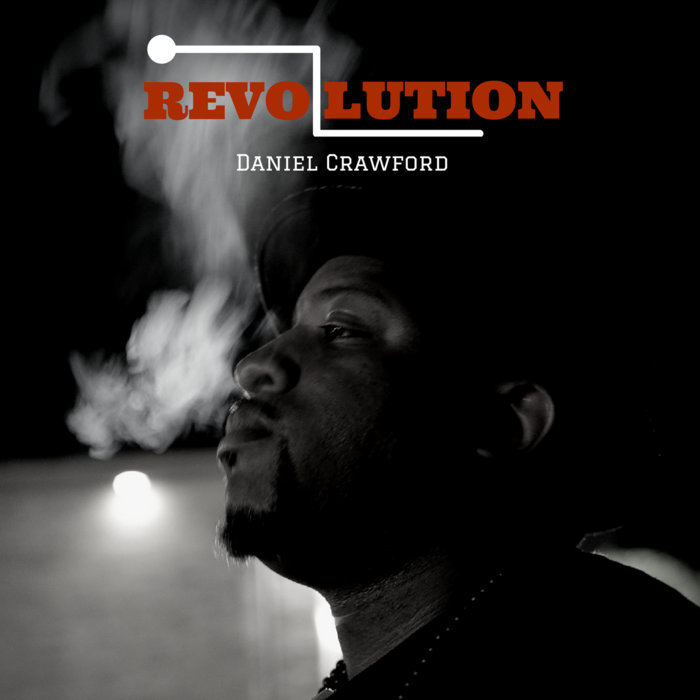MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Daniel Crawford- Revolution
ロバート・グラスパーの成功以降、ジャズとヒップホップやR&Bを同列に演奏し、その間を自在に行き来するジャズ・ミュージシャンも普通となってきた。クリス・デイヴやマカヤ・マクレイヴンのように、ビートメイカーやプロデューサーも兼ねるミュージシャンも増えている。西海岸であればスヌープ・ドッグやケンドリック・ラマーらと一緒に仕事をするテラス・マーティンとか、ニュージーランド出身で現在はロサンゼルスを拠点とするマーク・ド・クライヴローなどが、そうしたプロデューサー・タイプのミュージシャンの筆頭だろう。ロサンゼルスのサウス・セントラル出身のダニエル・クロフォードも、同じくマルチ・ミュージシャン/プロデューサーのひとりだ。5才からピアノを始めた彼は、ハイ・スクール時代の仲間とワイルド・バンチというヒップホップ・バンドを結成し(マッシヴ・アタックの前身のワイルド・バンチと同名だが、全く別のバンド)、その活動をきっかけにラファエル・サディークやメアリー・J・ブライジなどと共演するようになった。ヒップホップ、R&B、ソウル、ファンク方面の多くのセッションに参加してきた経歴は、グラスパーやクリス・デイヴなどのそれと被るところもあり、実際に彼の作品はロバート・グラスパー・エクスペリメントの影響が強い。2012年にリリースしたファースト・アルバム『レッド・ピル』では、RGEの“ムーヴ・ラヴ”を自身のピアノでリミックス(というかカヴァー演奏)しているが、ジャズ・ピアノとヒップホップ・ビートの融合から、ヴォコーダーを用いた演奏、メドレー形式やインタールードを挟んだスタイルは、まさにRGEの『ブラック・レディオ』を彼なりに咀嚼したものと言える。
2014年にはセカンド・アルバム『ジ・アウェイクニング』をリリースするが、こちらはアンプ・フィドラー、ヴィクター・デュプレ、クリーヴランド・P・ジョーンズらをシンガーとしてフィーチャーし、インストのジャズ×ヒップホップ集だった前作から格段に音楽性の幅が広がっていた。その音楽性の拡張にはアフロやブロークンビーツなどの要素の導入もあり、ダニエル・クロフォード自身もいちミュージシャンではなく、総合的な音楽プロデューサーへとステップ・アップした姿が伺えた。『ジ・アウェイクニング』は日本でもCDリリースされ、新世代ジャズ・ミュージシャンのひとりとして来日公演も行ったのだが、基本的に彼はbandcampで自主リリースを行うスタイルをとっている。ミックステープやリミックス集、Jディラへのトリビュート作品などリリース自体はとても多いものの、グラスパーやテラス・マーティンなどに比べればまだまだアンダーグラウンドな存在である。そんなダニエル・クロフォードの『ジ・アウェイクニング』以来、4年ぶりとなるニュー・アルバムが『レヴォリューション』である。
『レヴォリューション』は『レッド・ピル』『ジ・アウェイクニング』から続く最終章という位置づけで、ソウルの影響が色濃いジャズに、アフロビート、フュージョン、R&B、ヒップホップなどのエッセンスを融合したもの。今回は前2作に比べてずっとゲスト・ミュージシャンが増えて、DJジャジー・ジェフ、ダイン・ジョーダン、マイモウナ・ユセフ、カイディ・テイタム、オスンラデ、ジメッタ・ローズ、オマリ・ハードウィックらが参加。この中で注目すべきはUKのカイディ・テイタムだろう。そもそもカイディは、ミュージシャンとプロデューサーを結ぶスタイルや音楽を1990年代からやってきた大ベテランで、現在の南ロンドンのジャズ・ミュージシャンにも多大な影響を及ぼすひとりだが、ダニエル・クロフォードにとっても指針とすべきアーティストであることは、今回の共演を見ても明らかだろう。ジャジー・ジェフ、ジメッタ・ローズ、マイモウナ・ユセフらはダニエルとヒップホップ~R&B~ネオ・ソウルとの結びつきを示すのに対し、オスンラデの参加はアフリカ音楽との結びつきを示す。ダイン・ジョーダンはジャジー・ジェフと同じくフィラデルフィア出身の若手ラッパーで、ジェフと一緒に作品リリースも行っている。カイディ・テイタムのニュー・アルバム『イッツ・ア・ワールド・ビフォア・ユー』には、ジャジー・ジェフの息子のアミール・タウンズも参加していて、『イッツ・ア・ワールド・ビフォア・ユー』のミックスを手掛けたエリック・ロウは『レヴォリューション』でも1曲ミックスを担当しているので、そうしたピープル・ツリー的な人物相関図も浮かんできそうだ。
“レヴォリューション・イントゥルース”は自身のヴォイスも交え、アフロフューチャリズムを通過したジャズ・ファンクを展開。オープニング的なこのナンバーは、後に“レヴォリューション”として再登場。本編はより土着性の強いアフロ・ジャズとなっているが、こうしたアフリカ色濃厚なバック・トゥ・ザ・ルーツ的な色彩がアルバムを通じてのひとつのトーンとなっている。“ケイピン”や“チェックリスト”は、プログラミング・ビートと鍵盤のコンビネーションによるジャズとファンクの融合。ハービー・ハンコックの『セックスタント』や『ヘッド・ハンターズ』以降、ジャズにおけるアフロフューチャリズムにはスペイシーな感覚がつきものだが、ここではエッジ感のあるギターと共にキーボードがそれを表現する役割を担っている。“クミコ(スペンド・ザ・ナイト)”はブロークンビーツ調のナンバーで、中盤以降のピアノ・ソロも交えたコズミックな展開はカイディ・テイタムの作品に通じる。一方、そのカイディがフルート演奏で参加した“テレパシー”は、マイモウナ・ユセフのヴォーカルをフィーチャーしたネオ・ソウル的ナンバー。メロウネス漂う中にも土台にはアフリカ音楽のリズムが横たわっている。ジメッタ・ローズが歌う“サイレンズ”も同系のオーガニックなソウル・ナンバーで、彼女の歌声からミニー・リパートンやロータリー・コネクションなどに繋がるところも感じられる。
ジャジー・ジェフとダイン・ジョーダン参加の“イルージョン・オブ・インクルージョン”は、ヒップホップのビートメイカーとしてのダニエルの側面が表れた作品だが、あくまでキーボードを含めたジャズの生演奏が基本となっている点はRGE同様だ。“サイレンス・イズ・コンプライアンス”や”ビフォア・ザ・ストーム“では、ジャズ・ピアニストとしてのダニエルのプレイを堪能できる。美しいピアノ・ソロが大々的にフィーチャーされる“サイレンス・イズ・コンプライアンス”は、RGEではなくロバート・グラスパー・トリオの方に近い演奏だろう。終盤で俳優のオマリ・ハードウィックによるスポークン・ワードも披露される。オスンラデがヴォーカルで参加した“オール・カムズ・ダウン・トゥ・ワット”は、彼が普段やっているようなディープ・ハウスではなく、土着的でゆったりとしたアフロ~カリビアン・リズムとジャズやファンクが結びついた作品。“マーチ・オブ・ザ・ガラ”もカリブ色が強く、ディーゴ&カイディあたりに近いブロークンビーツ経由のジャズとなっている。ちなみにガラとはサウス・カロライナ州とジョージア州の海岸沿いのことで、アフリカ系アメリカ人やクレオールが多く住み、アメリカにおけるアフリカのルーツが色濃く残された地域である。この曲から次曲の“レヴォリューション”へと続く流れは、アフリカ系アメリカ人であるダニエル・クロフォードのディアスポラな意識がもっとも強く表われた場面だろう。エンディングの“13”は彼の父と兄弟も参加し、亡くなった祖父や親類たちへ捧げている。ファミリーや一族のルーツを示したこの曲は、アルバム全体のテーマを象徴しているだろう。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE