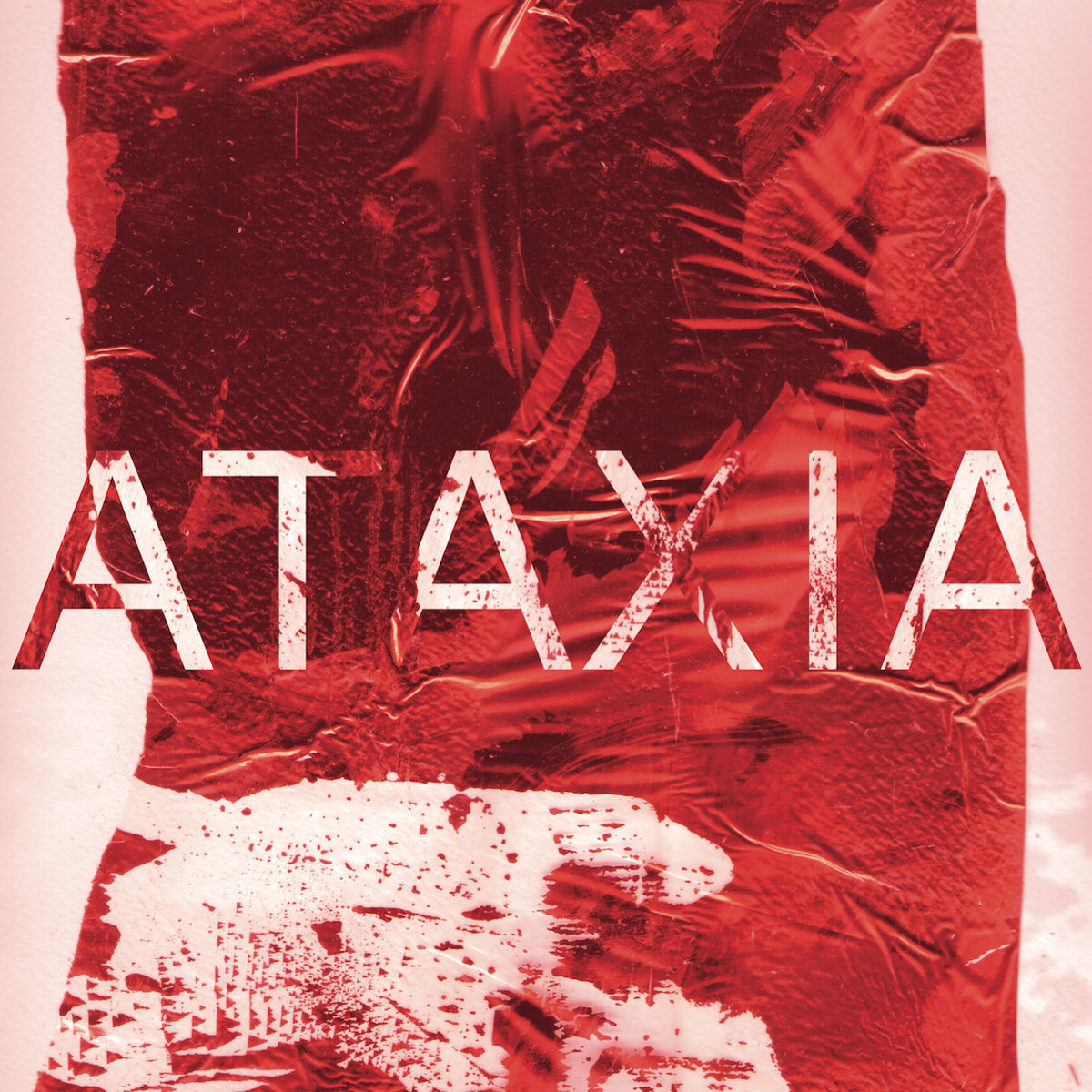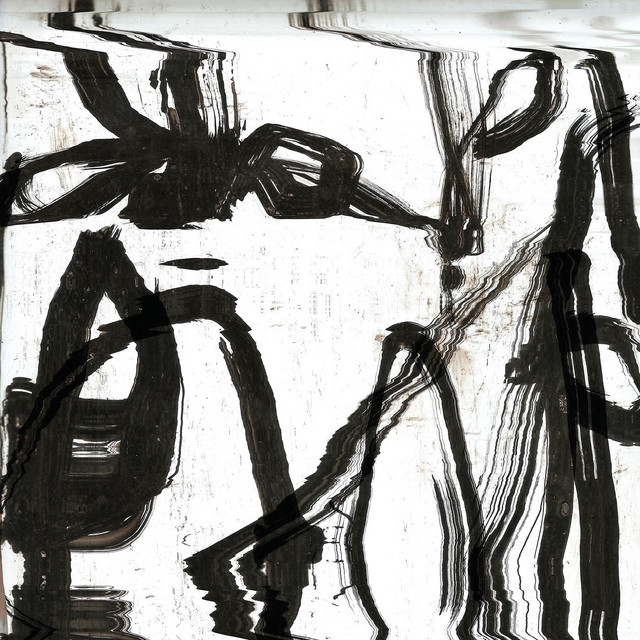MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Rian Treanor- Ataxia
2015年に〈ザ・デス・オブ・レイヴ〉からリリースしたデビュー・シングル「A Rational Tangle」がいきなり耳を引いたシェフィールドの鬼才。その時はグライムの変化形として僕は認識していたものの、イクスペリメンタル・スピード・ガラージだとかアブストラクト・グライムだとかイギリスでの呼ばれ方はもうグッチャグチャで、新鮮なサウンドに対する興奮が良くも悪くもそこからは読み取れた。続く「Pattern Damage」(16)は似たような内容のものだったので、悪くいえば二番煎じか、良くいえばオリジナリティを不動にした瞬間だったということになるだろうか。〈ワープ〉のサブ・レーベルに移ってリリースされた「Contraposition」(18)からは必ずしもダンス・ミュージックの範疇であることを前提としなくなり、ここでおそらくはファン層もザクっと入れ替わったに違いない。それまでになくダイナミックな発想が、そして、〈プラネット・ミュー〉からとなったデビュー・アルバム『Ataxia』では全面展開されている。アルバム・タイトルは「運動失調」の意で、コントロールの喪失という意味をトレナーは持たせたかったようだけれど、ダンス・ミュージックに対する独特の距離感が示されているようで「失調」という表現はなかなか興味深い。それはそもそも〈ザ・デス・オブ・レイヴ〉というレーベルが最初から持っているものなのかもしれないけれど。
初期の作風に比べて重厚なムードも加えるようになった『Ataxia』は「ジャンルの横断」と評された彼の資質をそのまま具現化したような内容で、これまでになかった要素もスプロール化してひしめき合っている。エイフェックス・ツインをスピード・ガラージ化したような前半からヴォイス・サンプルをカット・アップした“ATAXIA_B2”ではベリアルを暗闇から引きずり出して人工太陽で照らし出したかのようであり、ハイハットの過剰さはジャム・シティも凌いでいる。隙間だらけのドラムはむしろジャズを引き合いに出した方がすっきりしそうだけれど、やはり根底にあるのはUKガラージであり、ドラムンベースに違いない(彼自身は初期には即興だったものが、ここでは幾何学を応用してつくり上げたリズムだと発言している)。そういう意味では、これはブリティッシュ・サウンドのメインストリームだと断言していいだろう。コンガやベルなど複数の打楽器をUKファンキーのフォーマットに押し込んだ“ATAXIA_C2”もかなりユニークな曲で、後半はどれもがダンス・ミュージックの新境地を切り開いた作品群だといえる。
彼が重視しているのは、考え抜かれているけれど、考えすぎではないということ。シェフィールドの先輩であるマーク・フェル(Snd)とも交流が深いようで、これまでにチェロの即興で知られるオキュッグ・リーをフィーチャーした『A Pattern For Becoming』(15)に参加したり、マーク・フェルの曲をポルトガルのパーカッション・アンサンブルが演奏した『Intra』(18)やウルフ・アイズとハイエログリフィック・ビーイングのコラボ曲をエディットするなど、彼の存在感はクラブ・カルチャーよりは実験音楽のフィールドと親和性が高い。彼自身も自分はコンピューター・プログラマーではなくヴィジュアル・アーティストだと言い切っており、リーズで「エンジョイ」というアートスペースのキュレーションを行うなど、それなりに作品は発表しているようだけれど、どう考えても彼はマシュー・ハーバートがデビューしてきた時の驚きに匹敵する才能だと思うので、クラブ・ミュージックに実験的な精神をもたらす存在として僕としては高く評価したい。それこそいまごろ彼は、僕がこのところ夢中になっているDJカンピレが主宰するフェスに出ているらしいし(それはしかし、なんというマッチングだろうか!)。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE