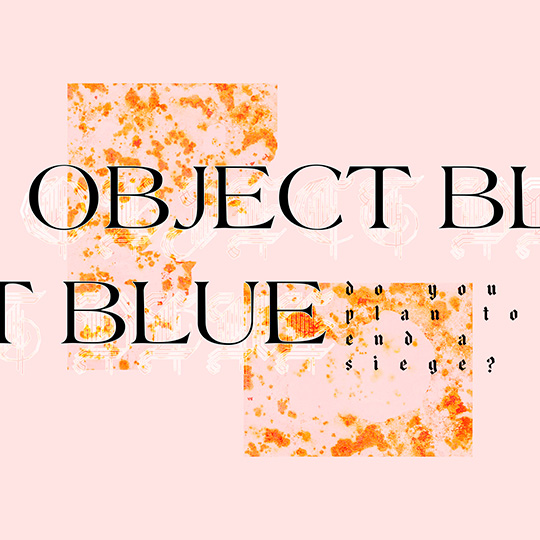MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Tribe Of Colin- Age Of Aquarius
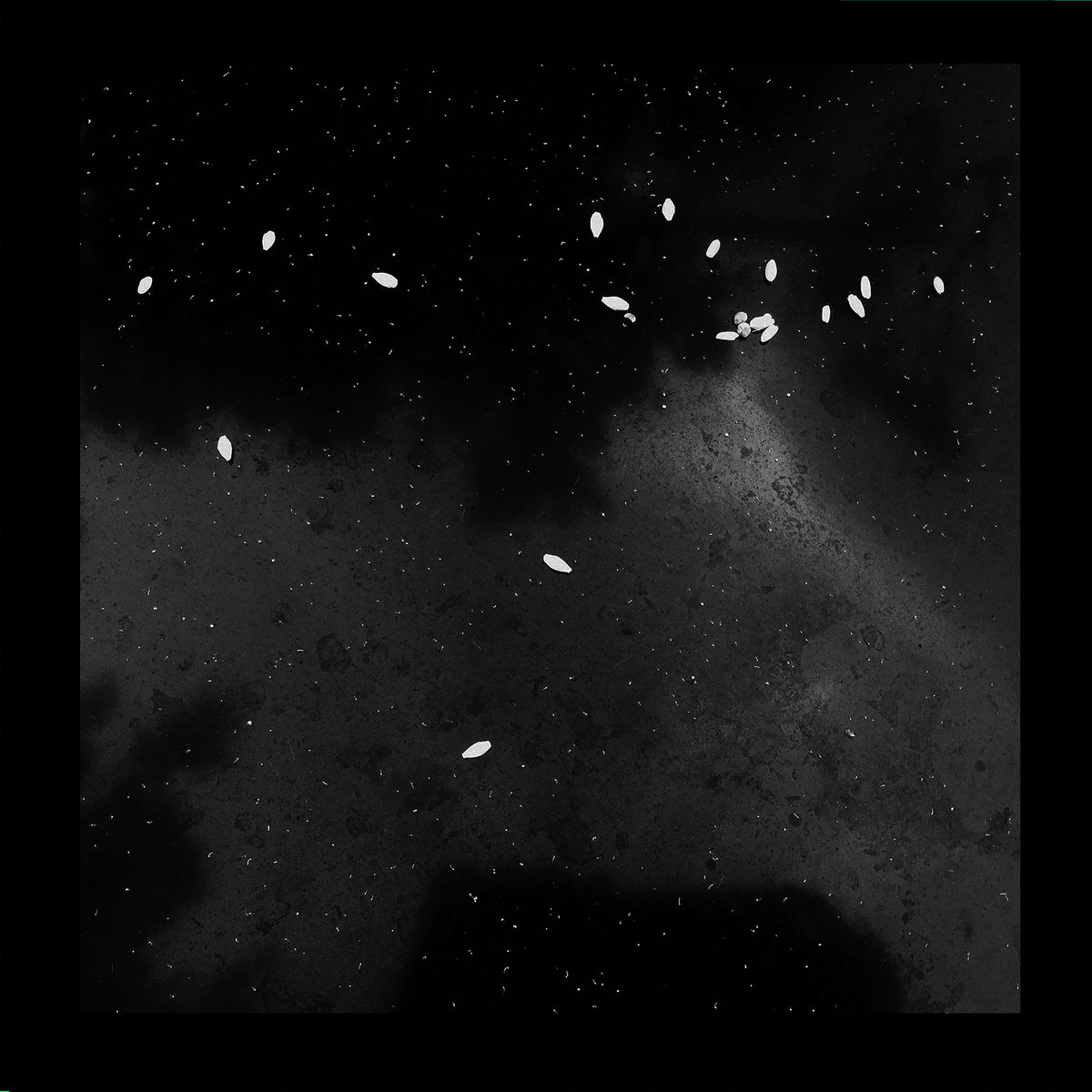
正体を不明にしておくこと。それは一見、ネット上に氾濫する膨大な匿名の投稿たちとひじょうに親和性が高いようにも思われる。しかし彼はねらーでもなければクソリプラーでもなく、表現を発信する側の人間だ。であれば通常は、ころあいを見計らってバズを生成し、しかるべきタイミングで大きな花火を打ち上げる、本人のキャラは立っていればいるほどいい──となるわけだけれど、彼のやり方はそのような SNS を意識した昨今の戦略とは真逆の発想といえる。
トライブ・オブ・コリンなるこの特異なプロデューサーは、ほとんど素性を明らかにしていない。おそらくは男性であり、どうやらロンドンを拠点にしているらしいことは推測できるが、それ以外はこれまでのリリース履歴を辿ることができるのみ。ジョン・T・ガストの〈5 Gate Temple〉からデビュー作を発表していること、そのガストと一緒にドーサイルというユニットを組み、〈The Trilogy Tapes〉からシングルを送り出していること、ほかにいくつかの12インチやCDで高い評価を得ていること、NTS に幾度もミックスを提供していること、そして今回の新作が〈Honest Jon’s〉からリリースされていること。わかるのはそれくらいである。あるいは『FACT』誌での貴重な発言によれば、父親がナイジェリア出身でレコード蒐集家であること、その父からの影響が大きいこと、ローランドの SP-404 を使用していること。あとは音を聴いて判断するしかない。
一言でいえばテクノでありダブだが、この『Age Of Aquarius』では、その枠組みじたいを押し広げるような果敢な試みが数多くなされている。音響的にはアクトレスやディーン・ブラント以降を強く感じさせ、低音はよりフロアを意識したつくりになっている。くぐもったキックとハットとアシッドの反復がベースラインを際立たせる “Creator God” は、情報ではなくサウンドの強度でもって彼の特異性を世に知らしめる、ある種の宣言のようなトラックといえる。“Woman Of Amazon” のアフロ・ミニマリズム、“Paradise Lost” におけるトラップを崩したビートとスペイシーな音空間との両立、“Frequency Interference” の擬似ダンスホールなども興味深いが、よりひきこまれるのはデトロイトからの影響を独自に昇華した部分だ。
最後の “Cradle To The Sunset” なんかはまさに「マシン・ソウル」と呼ぶべきトラックだし、ジャジーにしてインダストリアルな “Self / Distance” はセオ・パリッシュとドレクシアの両方を同時に想起させる。中盤に差しはさまれる旋律が不思議な違和効果をもたらす “Eye Of Ra” も、ありえたかもしれないドレクシアのべつの可能性を探っているかのようだ。“Alan” 冒頭のフィールド・レコーディングによくあらわれているように、アルバム全体をとおして水中を意識したような音響処理が施されているのも、かの不世出のデュオのコンセプトが念頭に置かれているからにちがいない(曲名も神話的だし)。その点で本作はトゥ・ローン・スウォーズメンの『Stay Down』を彷彿させもする。ホープ・ウィ・ネヴァー・サーフィス。なるほど、正体を明かさないわけだ。バズとかキャラじゃねえんだよと、つまりはそういうことだろう。ここには矜持がある。アンダーグラウンドの底力を再確認させてくれる、想像性に満ちたアルバムである。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE