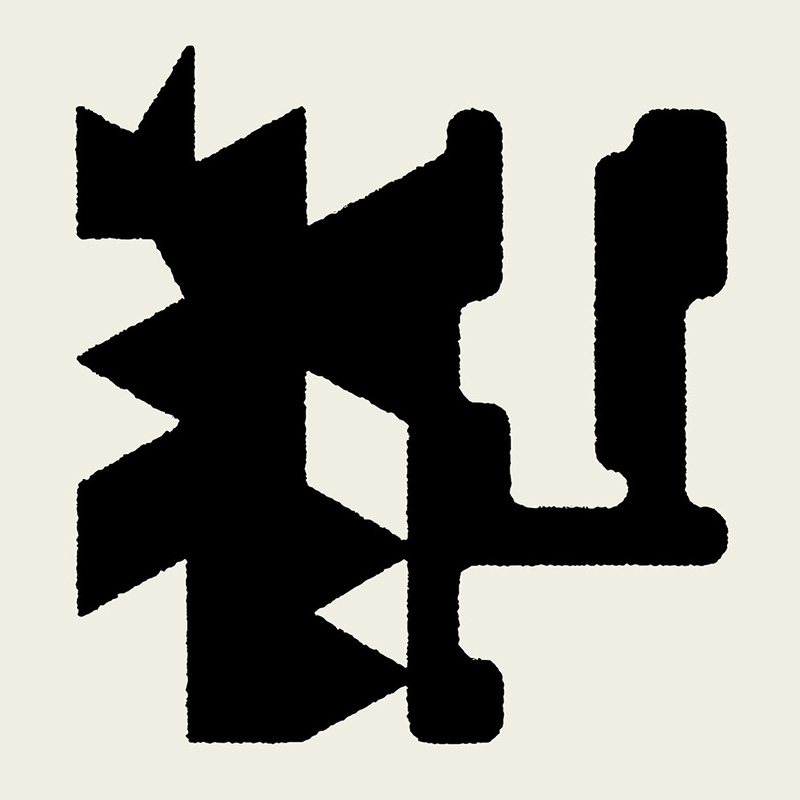MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Meemo Comma- Neon Genesis: Soul Into Matter²
オトナになれ。そういう話だそうだ。ググってネタバレは調査済みだが、映画自体はまだ観ていない。列島が『シン・エヴァ』一色に染まってしまったかのように見えなくもなかったこの3月、遠く海を隔てたUKから「いや、やっぱTV版でしょ」と言わんばかりの挑発的なタイトルを持つアルバムが届けられた。送り主はミーモ・カンマ、本名ラーラ・リックス=マーティン。マイク・パラディナスのパートナーである。これまでに3枚のアルバムをリリース、パラディナスと組んだヘテロティックとしても2枚のアルバムを残している。
じつは、彼女の影響力は大きい。紙エレ年末号をお持ちの方は、いま一度パラディナスのインタヴューを読み直してみてほしい。黒人たちのメンタル・ヘルスを支援するためのチャリティ・コンピ『Music In Support Of Black Mental Health』は彼女の発案によるものだ。「妻は僕の物事に対する考え方の多くを変えてくれた」「彼女が僕のポリティクスを変えた」と彼は述べている。ふたりの信頼関係は『ワイアー』の「目隠しジュークボックス」や『クワイータス』の相互インタヴュー記事からもうかがい知ることができよう。そんな彼女が日本のアニメ・ファンでもあったことは興味深い。
タイトル・シークエンスの “Neon Genesis” ではジャングルのリズムが用いられているが、なるほど、その神秘的なヴォーカルの響かせ方は “残酷な天使のテーゼ” (の間奏)を想起させなくもない。この手法は、やはりジャングルの断片がねじこまれた “Tif’eret” やビートレスの “Ein Sof”、“Tzimtzum” といった多くの曲で導入されており、アルバム全体のムードを決定づけている。
だが、じっさい『エヴァ』からインスパイアされたのはヴィジュアルのほうで、サウンドのレファランスは『攻殻』のサントラだそうだ。たしかに、これは鷺巣詩郎ではない。14歳のリックス=マーティンは初号機ではなく、殻を着たゴーストと出会ったのだ。レーベルの紹介文では「GHOST IN THE SHELL」と「S.A.C.」の両方が言及されている。つまり、親は川井憲次と菅野よう子のふたり、ということになる。ファースト・アルバムのタイトルも『Ghost On The Stairs』だった。そうとう好きなんだろう。
架空のアニメ・サントラと謳われているとおり、ビートのある曲は戦闘や疾走のシーンを想起させる。“Unit Chai” で戯れる電子音なんかは、タチコマ的なメカがなにかをサーチしているかのようだ。逆にビートのない曲はグライム以降のウェイトレス感を漂わせ、廃墟や心理描写の場面を想像させる。もっともよくできたトラックは “Merkabah” だろう。くぐもったドラムの鳴りとフットワークばりに切り刻まれたヴォーカルの応酬が、生命力あふれるリズムを紡ぎだしている。
本作のより大きなテーマはずばり、ユダヤ教だ。アダムとイヴ、使徒(天使)、生命の樹……『エヴァ』や『攻殻』、『ハガレン』などのアニメを享受する過程で彼女は、そこにみずからのルーツたるユダヤ教的・旧約聖書的なモティーフが登場することに惹きつけられる。アニメに限らず、多くのSFにはカバラ──ユダヤ教にもとづく神秘主義思想──が影を落としていると、リックス=マーティンは指摘する。たしかに終末論は定番ではあるが、「カバラにも美しくて、希望に満ちた考えがあってね」と彼女は補足する。たとえば、最初の人間には性別がなかった。本作はそのセックスレス/ジェンダレスな発想をSFと結びつけることで、「サイボーグ宣言」への回路を開いている──そんな深読みも可能かもしれない。
ともあれ彼女がユダヤの思想やモティーフを強く意識するようになったきっかけは、子どもができたことだったという。リックス=マーティン自身はずっとユダヤ人として生きてきたわけだが、パートナーとのあいだに生まれた子たちはそうではない。だから彼らに、自分たちが深い文化的背景を持っていることを知ってほしかった。そのような話を彼女は上述のインタヴューで語っている。親の、心だ。このポジティヴな動機が一見ダークな本作に、ある種の陽気さをもたらしているのだろう。
たしかにこのアルバムは暗い。けれども悲愴感をまき散らしてはいない。重苦しさとも無縁で、ユーモラスで、ときにコミカルでさえある。そもそも「Neon Genesis」と題したアルバムを『シン・エヴァ』公開のタイミングで発表すること自体、ちょっとしたいたずらのようなものだ(まあ、映画は何度も公開延期の憂き目を見ているので、意図したことではないんだろうけど)。対象との距離が、ここにはある。滅びゆく世界の主人公と同化し、おのれを憐れみながらカタルシスを調達する視聴者の姿は、ここにはない。ラーラ・リックス=マーティンは子を持つ親なのだ。オトナにならざるをえない。
ならばこれはTV版よりむしろ、『シン・エヴァ』に接近した作品ではないか。いやいや、「オトナになれ」というメッセージはTV版のころからずっと変わっていない、そんな意見も耳に入ってきてはいる。TV版や旧劇が描いていたのは「オトナになる」ことではなく、「他者と出会う」ことだとぼくは解釈しているので、さて新劇がほんとうはどのような結末を迎えたのか、この目でたしかめたくなってきた。
小林拓音
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE