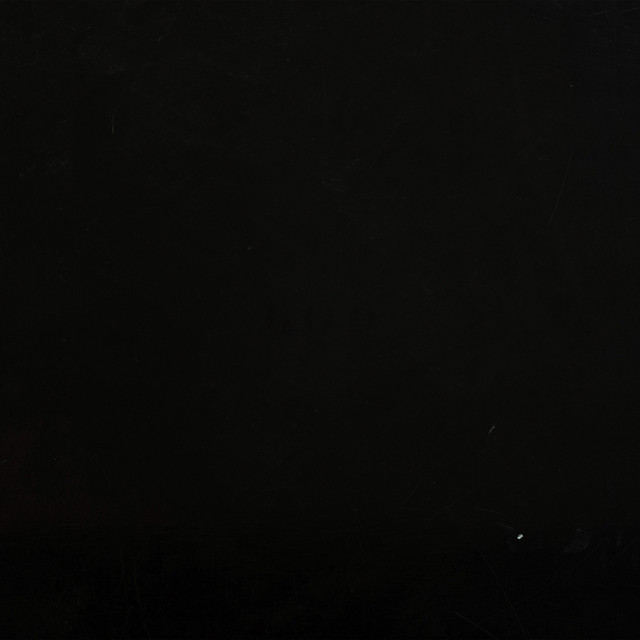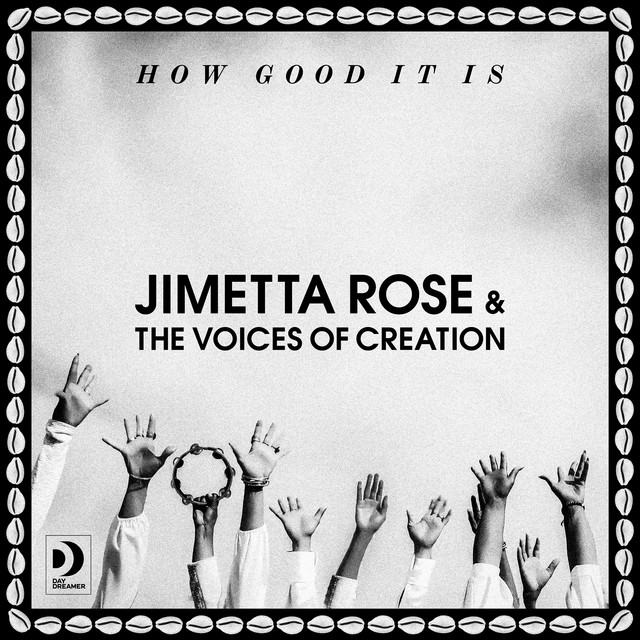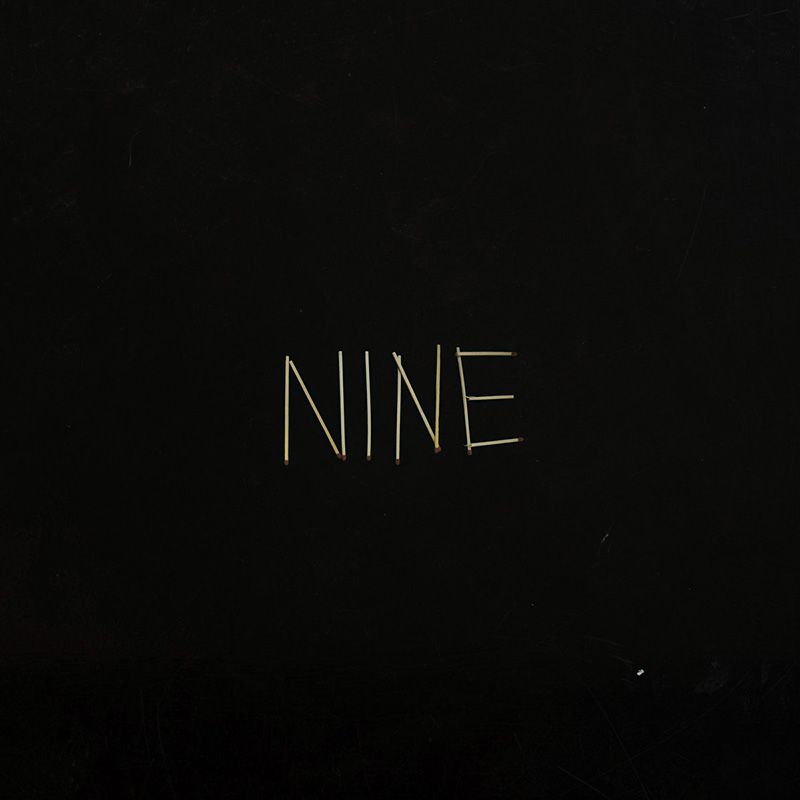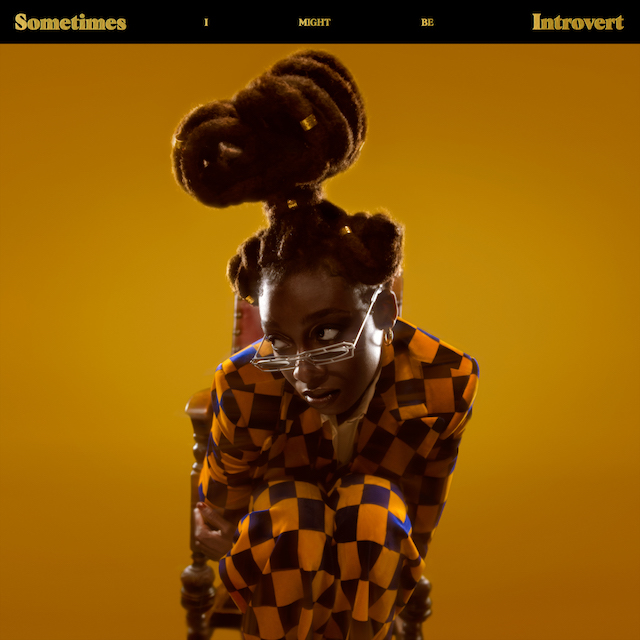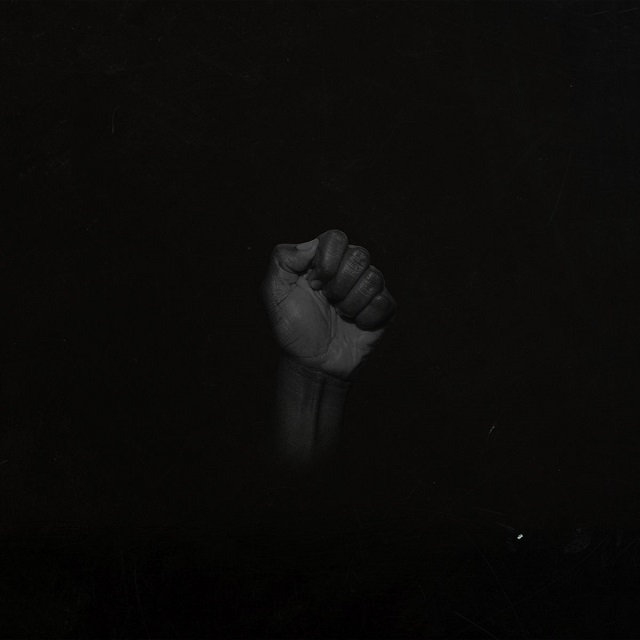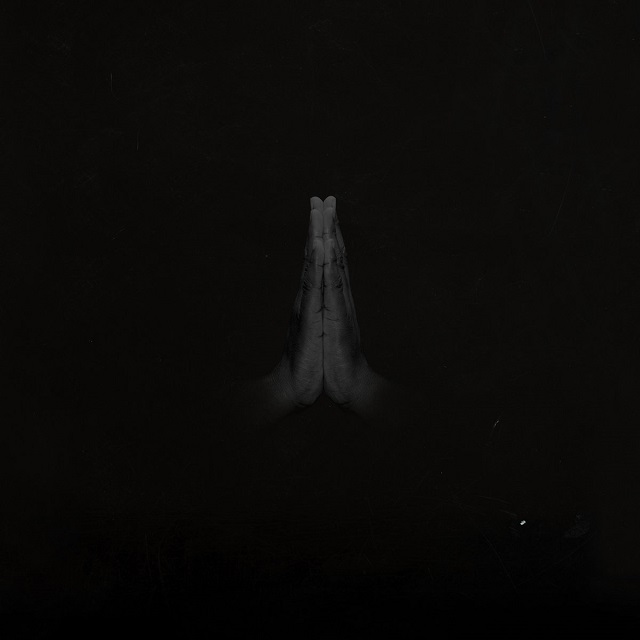MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > SAULT- Untitled (God)

凄まじい勢いで作品リリースを続けるスー。作品は自身のレーベルである〈フォーエヴァー・リヴィング・オリジナルズ〉から Bandcamp 経由で発信しているのだが、2022年は7つもの作品をリリースしている。それ以前は一年に1、2作程度のリリースだったが、2022年になってから一気にリリース量が増え、特に10月と11月にかけては6作品もリリースしている。2022年に入って最初にリリースした『エアー(Air)』と、その続編的な『Aiir』はそれまでの作風から一変したもので、オーケストラをバックにしたクラシック調の作品だった。男女混成コーラスによる歌詞のない歌は声楽というのが相応しく、賛美歌を思わせる高尚な雰囲気に満ちた作品だ。一方、『トゥデイ&トウモロー』という作品は1960年代のサイケデリック・ロック調で、ヴォーカルも粗削りでファンキーなものだった。こうした正反対の作品をリリースする意図がどこにあるのかよくわからないが、つくづくスーは人を混乱させるグループであると思うし、そんな神出鬼没で予測不能なところが彼らの魅力だと感じる。
10月以降の作品の中で、『アンタイトルド(ゴッド)』、『アース』、『11』には共通した要素がある。それはゴスペルである。『アンタイトルド(ゴッド)』はタイトルからしてそうで、曲目も “アイ・アム・フリー”、“ゴッド・イズ・ラヴ”、“スピリット・ハイ”、“ディア・ロード”、“ウィー・アー・ゴッズ”、“ゴッド・イズ・オン・ユア・サイド”、“フリー”、“マイ・ライト”、“ゴッド・イン・ディスガイズ” と、神や創造主、自由や精神、光などをテーマにしている。“ゴッド・イズ・ラヴ” はいわゆるゴスペル・ファンクというようなナンバーで、“スピリット・ハイ” はゴスペル色の濃いネオ・ソウル。“ラヴ・イズ・オール・アイ・ノウ” はガラージ・クラシックかムーディーマンの作品のようにも聴こえるナンバーで、やはりゴスペルの強い影響を感じる。面白いもので、これらで披露される歌声は正反対な『エアー』と『トゥデイ&トウモロー』の両方に通じるところもあり、一見して繋がりのないように聴こえるこれら作品が、実は繋がっていることを示している。
『アース』にもこうした傾向は続き、曲目も “スピリット・コール”、“ザ・ローズ・ウィズ・ミー”、“ゴッド・イズ・イン・コントロール”、“パワー” といったゴスペルならではのものが並ぶ。“ザ・ローズ・ウィズ・ミー” における呪術的でアフロセントリックなモチーフは、ゴスペルというよりもはやヴードゥー教の祈祷のようでもある。アフロ・キューバン調の “ソウル・インサイド・マイ・ビューティフル・イマジネイション” もそうだが、『アース』はより原初的なルーツ・ミュージックに立ち返ったような作品でもあり、そうしたところからこのアルバム・タイトルになっているのだろう。
『11』はサイケデリック・ファンクの “グローリー” を除き、直接的には神や宗教に繋がるようなタイトルのナンバーはない。それでも “トゥゲザー” や “ハイアー”、“ザ・サークル” などスピリチュアリズムを連想させるようなワードが並ぶ。ファンクやソウルを軸にアンビエントやフォークとヴァラエティーに富む作品が並ぶが、歌のテイストにはやはりゴスペルに繋がるムードが流れる。1960~70年代のグループで言えばロータリー・コネクション、24カラット・ブラック、ザ・ヴォイシズ・オブ・イースト・ハーレムといったところだろうか。
こうしたゴスペルへの傾倒について、そもそもスーは様々な音楽性を持つグループであるが、なかでもソウルやファンクなど黒人音楽を主軸としているところがあり、多くの黒人音楽に影響を与えているゴスペルへ行きつくのは自然な流れであると言える。『ブラック・イズ』のようにブラック・ライヴズ・マター運動に呼応した作品もリリースしてきているが、遡れば1960年代の公民権運動とゴスペルにも同じような関係性があった。また、グループの中心人物であるインフローことディーン・ジョサイア・カヴァーは、黒人シンガー・ソングライターのマイケル・キワヌカの作品をプロデュースしてきており、彼のブラック・フォークとゴスペル・ファンクとアフロが混じったような世界は、スーにおいても散見されてきた要素であるので、こうしてゴスペル色が前面に出てくるのも合点がいくところだ。
同様にインフローがプロデュースを手掛けるリトル・シムズも、新作『ノー・サンキュー』を2022年の年末にリリースした。これまでの〈エイジ・101・ミュージック〉でなく、〈フォーエヴァー・リヴィング・オリジナルズ〉からなので、インフローの影響がより強い作品となっている。ピアノをバックにアカペラ・コーラスが流れる “コントロール”、プリミティヴなアフロ・リズムに荘重なコーラスが絡む “X”、オーケストレーションと混成コーラスをフィーチャーした “ブロークン” など、これまたゴスペルに繋がるムードが随所に感じられる作品となっていて、これまでのリトル・シムズにあまりなかった面も見せる興味深いアルバムだ。
ゴスペル関連でいくと2022年はもうひとつ象徴的な作品が生まれている。これまでジョージア・アン・マルドロウ、ミゲル・アトウッド・ファーガソン、サー・ラー・クリエイティヴ・パートナーズなどと仕事をしてきた女性シンガーのジメッタ・ローズによる『ハウ・グッド・イット・イズ』で、地元ロサンゼルスのゴスペル・コーラス・グループであるザ・ヴォイシズ・オブ・クリエイションとの共演作となる。楽曲もローランド・カークのゴスペル・ジャズ・クラシックである “スピリッツ・アップ・アボーヴ”、西海岸の伝説的なスピリチュアル・ジャズ・バンドであるサンズ・アンド・ドーターズ・オブ・ライトの “レット・ザ・サンシャイン・イン” などをカヴァーしていて、ゴスペルとクラブ~ダンス・ミュージック・カルチャーの接点から生まれたアルバムとなっている。このようにゴスペルがキーワードとなった作品が見られた2022年だが、2023年もこうした傾向は続くのではないかと予想する。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE