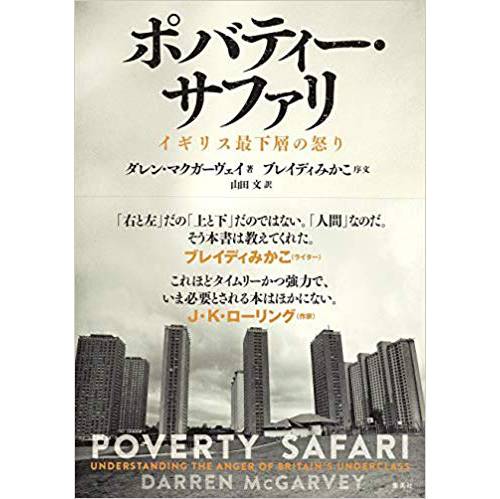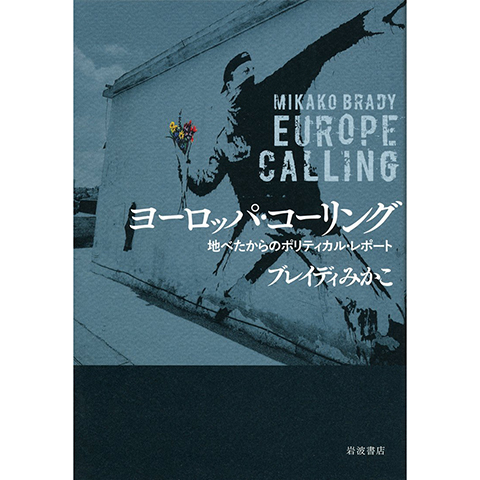MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > 子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から- ブレイディみかこ
三匹の子ぶたのその先
「三匹の子ぶた」は誰もが一度は話を聞いたり、本で読んだりしたことのある有名な昔話である。どうやらイギリスの話らしい。一人目の子ぶたはワラで、二人目の子ぶたは木材で家を作るが、彼らを狙うオオカミにどちらも吹き飛ばされてしまう。しかし、最後の子ぶたが作ったレンガの家にはオオカミもなすすべがない。オオカミは煙突からの侵入を試みるのだが、煙突の下で沸かしておいた熱湯で茹でられ、反撃を食らう。──そんな話のプロットはおそらく誰もが覚えているだろう。
私はこの昔話が特に好きだったわけでもないのだが、二年前にこのお話の発祥の地であるイギリスで、とある「三匹の子ぶた」絵本を見てから、妙にこの話が気になるようになった。この話のポイントはなぜ三匹の子ぶた、すなわち、三人の未成年者が自らで家を建てねばならなくなるのかというところにある。我々が普段目にするバージョンではそのポイントはぼかしてある。だが、どうやら古い民間伝承に忠実に描かれたらしいその絵本では、その理由が最初のページでハッキリと描かれていた。
三人は「もうお前たちを育てていくことはできない」と言う母親から、家を出て行くよう告げられるのである。彼らは捨て子ではない。彼らは自分たちの親を知っている。彼らは親が蒸発してしまったわけでもない。いかなる理由からかは明確ではないが、家を出て行って自分たちで何とか生きていくようにと、親に告げられるのである。
捨て子には捨て子のつらさがある。親が蒸発した子には親が蒸発した子のつらさがある。そして「もうあなたを育てることができない」と言われた子には、そのように言われた子のつらさがある。
蒸発せずにハッキリとそのように口にする親には、自分が置かれている状況に目を向けようという気持ちが感じられる。その場からいなくなってすべてを忘れようとするのではなくて、少なくとも自分で問題に対処しようとしているからである。しかし、親に面と向かってそのように告げられる子の気持ちはいかなるものであろうか。
おそらく三匹の子ぶたたちにとって、最もつらく、そして、実際に描かれることはないけれども最も劇的であっただろうと想像されるのは、家を出てから一人一人で新しく家を作ろうとするまでの間の時間である。簡単ですぐに手に入るワラに飛びつく一人目の兄弟。そのことの愚かさに気付くだけの知力はもっていたけれどもどこかで「この程度でいいだろう」と判断してしまった二人目の兄弟。そして、時間も費用もかかるが確実な家を建てられるレンガを求めるべきだと判断できるだけの知力を持ちつつも、最後には、自分たちを食い物にしようとした連中と全く同じことをしてしまう三人目の兄弟。
特に三人目の兄弟の運命は心を打つ。オオカミを鍋の熱湯で煮て食べる彼の所行は、不幸は復讐を望む心を生み出し、復讐を望む心はその不幸をくり返すばかりで何も新しいものをもたらさないという暗い真理を告げているようである。三人目の兄弟は利口だったのかもしれないが、利口であったが故に、彼らにこのような不幸を課してきた社会の論理に過剰に適応してしまったのだ。彼は復讐を試みることで、自らが復讐したかった社会そのものになってしまった。
*
書評原稿であるというのに昔話を熱心に論じてしまったのは、ブレイディみかこ著『子どもたちの階級闘争』を読みながら、この話をどうしても思い出さずにはいられなかったからである。
著者と同書について簡単に紹介しよう。氏はイギリスのブライトン在住保育士であると同時に、ブログやネット記事で大人気のライター・コラムニストでもある。2004年からネットで文章を発表し始め、2005年には最初の著書を出版しているのだから、相当な実力の持ち主であると言わねばならない。最初の著書『花の命はノー・フューチャー』は最近、Delux Editionと銘打って文庫化された(ちくま文庫、2017年)。
ブレイディ氏はその後も旺盛な執筆活動を続けてきた。「底辺託児所」での経験を通じてブロークン・ブリテンを紹介した『アナキズム・イン・ザ・UK──壊れた英国とパンク保育士奮闘記』(Pヴァイン、2013年)。イギリス「左翼セレブ」伝『ザ・レフト──UK左翼セレブ列伝』(Pヴァイン、2014年)。テロとグローバリズムと格差に揺れる2010年代中盤の欧州を描いた『ヨーロッパ・コーリング──地べたからのポリティカル・レポート』(岩波書店、2016年)。日本のデモクラシーと格差の現実を取材した『THIS IS JAPAN──英国保育士が見た日本』(太田出版、2016年)。熱烈な音楽ファンであり且つ政治通である氏の面目躍如の著作と言うべき『いまモリッシーを聴くということ』(Pヴァイン、2017年)。
いずれも話題作となったが、特に2016年に出版された二冊は氏の名前を広く世に知らしめることとなり、そのことを氏が望んでいるかどうかはともかくとして、その名前は「論客」のリストに掲載されることとなった(経済学界の高齢の重鎮が氏の著作の素晴らしさに驚愕し、出版社まで電話をかけてきたという逸話も私は耳にしている)。
氏の文章は、正確で広範囲におよぶ政治・社会についての知識(日本と違って新聞がおもしろいからかもしれないが、氏はとにかくイギリスの新聞をよく読んでいる)、保育士として常に「地べた」を見つめようとする気概(氏は『子どもたちの…』の序文で「わたしは保育士である」と何度もくり返す。氏は「論客」などというものになろうとしているのではない)、そしてヒューモアとシリアスが混じり合った文体(「あなたたちはダメなのよ、屑なのよ、どうしようもないのよ、と私は思うのよ。の、その先にあるもの。についてあのとき私はずっと考えていた」(『子どもたちの…』283頁)──他の誰にこんな文を書くことができるだろう!)、これらの要素の絶妙なミックスとしてある。
私自身も海外生活が長かったのでよく知っていることだが、インターネットとグローバリゼーションの時代になっても、実際には海外の政治・社会の情報はほとんど伝わってこない。政治・社会というのはその地に住む者がその地の雰囲気を通じて感じ取っていることと切り離せない。だからその雰囲気を伝えることができる書き手に恵まれなければ、ある土地に住む者が別の土地の政治・社会を十全に理解することはできない。そして学者という名の専門家が常に優れた書き手であるわけではないのだから(というか、そうでない場合がほとんどであるから)、ある国の政治・社会を研究する専門家がどれだけいたところで、その国の政治・社会が、別の国に住む者たちに十分に伝えられるわけではない。だからイギリスの政治に関心をもっていた私は、ブレイディ氏の登場を心から喜んだ。
本書『子どもたちの階級闘争──ブロークン・ブリテンの無料託児所から』は或る意味で『アナキズム・イン・ザ・UK』の続編である。『アナキズム…』は氏が無料の「底辺託児所」を去るところで終わる。氏はそこを去って民間の保育所に就職したのである。ところが、その保育所はある事件をきっかけに潰れてしまう。『子どもたちの…』は氏がかつて働いていた「底辺託児所」に戻ってくるところから始まる。託児所を離れていたのはほんの4年間のことであった。ところが託児所は様変わりしていた。その4年間は、保守党政権の進める緊縮財政が様々な公的セクターを直撃した4年間であったからである。もはやそれは「底辺託児所」ではなかった。氏はそれを「緊縮託児所」と呼ぶ。ところが、何ということであろうか、この託児所も閉鎖されてしまう。託児所は貧困世帯に食料を無料で提供するフードバンクにされてしまうのである。
『子どもたちの…』の前半は託児所の閉鎖で幕を閉じる。そして、まるで、今はなき託児所に思いを馳せ、「底辺託児所」が「緊縮託児所」に変わっていく間に失われたものは何であったのか、その答えを探し求めるかのように、同書の後半では「底辺託児所」時代のことが語られる。つまり、氏が民間の保育園に就職する前、「底辺託児所」時代に書いた文章が後半に掲載されているのである。『子どもたちの…』は時間を遡る形で編集されている。時間を遡りながら、読者は、何が失われたのかを氏とともに考えることになる。
『子どもたちの…』はその編集形態そのものが大きなメッセージになっていることに注意しなければならない。同書の本体をなすのは、前半部に収録されることとなった雑誌『みすず』での連載であるが、これは単に連載をまとめた本ではない。この本の形そのものが氏のメッセージになっている。
*
いくつもの話が心に突き刺さる。だが、私自身、子を持つ親として、本当に読んでいてつらかったのは、子を手放さねばならない親たちの話である。親として不適格であると判断されるとソーシャルワーカーによって親が自分の子どもを取り上げられるというのはイギリスではよくあることだという。この政策の是非はともかく、ここには子どもの福祉を最優先にするという思想が反映されているわけだが、底辺託児所に来る親たちはアルコール依存など様々な問題を抱えており、したがって、何とかして子を取り上げられないよう、ソーシャルワーカーと戦わねばならない──というのが底辺託児所時代の当たり前の光景であった。
ところが今は違う。
緊縮託児所の親たちは子どもを手放そうとしている。
「決して親たちが薄情になったとかいうことじゃない」。氏は友人の言葉を紹介する。「親が、もう踏ん張れなくなってる」(『子どもたちの…』38頁)。緊縮財政のもとで社会への投資が削減され、底辺家庭は徹底的に追い詰められている。
子どもたちの姿も心に突き刺さる。そうして追い詰められた家庭の子どもであるマヤは「声を出さずに泣く子ども」だ(『子どもたちの…』39頁)。氏は託児所で、声を出さずに泣く子どもたちに出会う。泣きたい気持ちをそのまま表現することも許されずに過ごしてきた子どもたちである。
もちろん、同書は暗い話だけに貫かれているわけではない。母親はヘロイン中毒で、父親はDVで刑務所を出入りし、祖母も盗品を売りさばいて金儲けしていたストリートギャングの元締めであったというロザリーは、幼い頃、この託児所に預けられていて、託児所の人びとを様々に困らせていた子どもの一人だった。しかし、今ではブライトン大学で小学校幼稚部教諭になるために学んでおり、しかも、成績があまりにも優秀であるため、彼女の実習先である底辺託児所に自治体から奨励金が下りたほどだったという。「こういうところで育ったらこうなる」というのは偏見に過ぎない。ロザリーの存在は人に「希望」という言葉を思いつかせる。
しかし私はあまり「希望」という言葉を使いたくないし、使う気になれない。「希望」というのは、本当はこれから起こることが分からなくて怖いから、現状に目をつぶってつぶやく言葉なのだというようなことを私が研究しているスピノザという哲学者が言っている。本当にそうだと思う。実際、ロザリーが戻ってこられた託児所は、無機質なスチール棚が立ち並び、ビニール袋に入った食料や缶詰が整然と並べられているフードバンクに変わってしまった(『子どもたちの…』283-284頁)。
子どもを手放さねばならない親の話を読んで、私は「三匹の子ぶた」を思い出した。三人の未成年者は、内二人が食い物にされ、最後に残った一人は彼らを食い物にした社会に復讐して終わった。残酷な話だ。そしてこの話は残酷であり、且つ、2017年の時点でリアルな話である。ならば我々は「希望」などという甘ったるい言葉でごまかしてそこから目を背けるのではなく、「三匹の子ぶた」のその先を考えなければならない。
氏はこの本の最後、「あなたたちはダメなのよ、屑なのよ、どうしようもないのよ、と私は思うのよ。の、その先にあるもの。についてあのとき私はずっと考えていた。思えばわたしはずっとそれを言葉にしようとしていたのかもしれない」と書き、その答えは「愛」ではなくて「尊厳」だったと言っている(『子どもたち…』284頁)。底辺託児所にあったアナキズム、あのアナキズムは尊厳そのものだった、と。
欧米ではしばしば尊厳は薔薇の花にたとえられる、とも氏は記している。いま失われたもの、そして、この現状のその先で再び咲かせなければならないもの、それは尊厳の薔薇だ。ブレイディみかこ氏の文章を通じて、我々は再び、尊厳という古くて新しい言葉に出会う。そして、どうすれば薔薇の花を再び咲かせることができるのか、考え始めるのである。
國分功一郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE