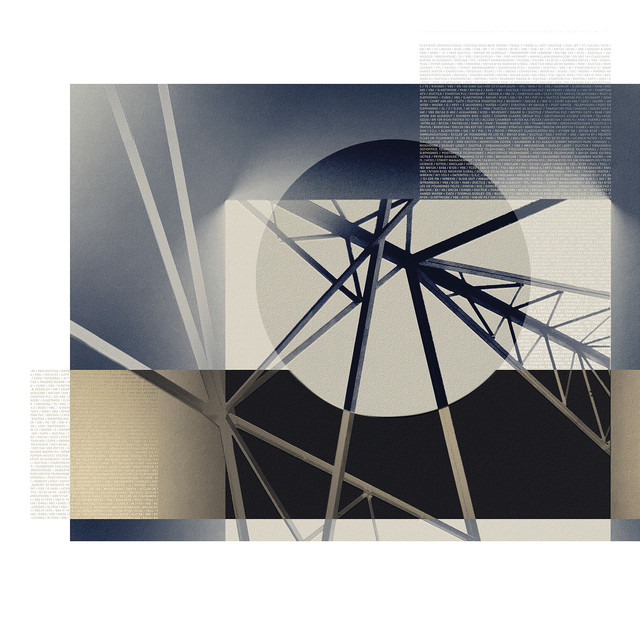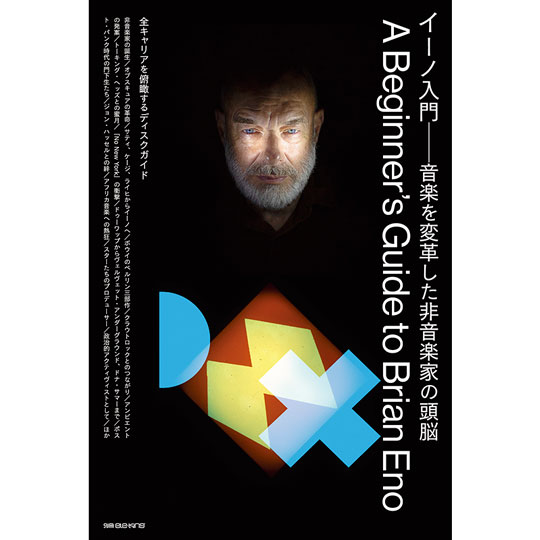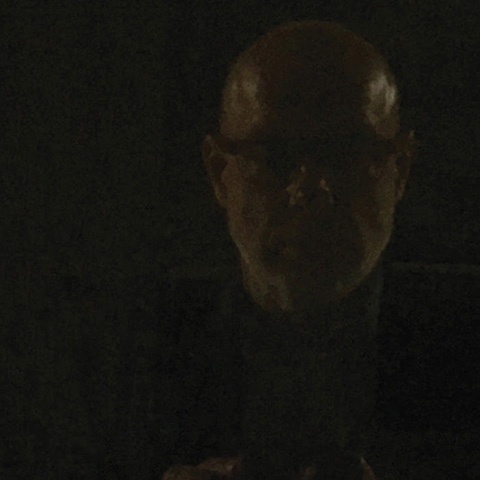MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Live Reviews > ブライアン・イーノ- “Ships“: Brian Eno & Baltic Sea …

グラム・ロック、アート・ポップ、エレクトロニック・ミュージック、前衛、アンビエント等、いくつもの領域にリーチし「万能ポリマス」ぶりを誇ってきたブライアン・イーノにも死角がある。ライヴ・パフォーマンスだ。
ライヴ活動を完全に回避してきたわけではないが、近年では2009&10年開催の芸術祭向けプログラム「This is Pure Scenius!」、21年にアクロポリスで弟ロジャーと初コンサートと、散発的なのは確かだ。ワークシャイ(仕事嫌い)ならぬツアーシャイ? その意味でも、ロキシー・ミュージックを脱退しソロに転じて50年後に、イーノが「Ships across Europe」と題してヴェニス、ベルリン、パリ、ユトレヒト、ロンドンを初めてツアーすることになったニュースは世界の音楽ファンを驚かせた。
ヴェネツィア・ビエンナーレで特別功労賞を受賞したイーノは、同ビエンナーレ音楽部門向けのプログラム制作を依頼された。結果生まれたクリスチャン・ヤルヴィ指揮バルト海フィルハーモニーとの共演作『Ships』を、フェニーチェ劇場でのプレミア後、欧州数カ所のコンサート・ホールで披露。2016年のアルバム『The Ship』篇、そして過去の作品からセレクトされた「歌もの/ヴォイスもの」篇から成る二部構成だ。ゲストとして、イーノ組常連リオ・エイブラムス(G)とピーター・チルヴァース(Keys)、そして声楽家/作曲家メラニー・パッペンハイムと俳優ピーター・セラフィノヴィッチ(朗読)も参加した。
開演前からスモークがうっすら漂う会場内。後方にキーボード、ドラム他の演奏台がひな壇式に組まれただけのシンプルなステージだ。着席しても、イーノの重い腰を上げさせたのは何か? なぜ「今」実現したのか?と素朴な疑問が頭をよぎる。その疑問は、ヤルヴィとバルト海フィルを実際に体験して氷解した。イーノ自身、『The Ship』のライヴ版を構想していく中で浮かんだ「スコアではなくハートから演奏する、若くフレッシュな演奏家を」という要望を彼らはすべて満たしていた、と述べているが(しかも「海」が名前に付くので「船」とも語呂がいいのが決め手だったらしい)、このオケがあってこそ実現可能なパフォーマンスだった。
客電が落ち、数秒の沈黙の後、フルートの響きがかすかに流れてくる。フルート奏者を先頭に両袖からオーケストラのメンバーがひとり、またひとり……と暗いステージに足を踏み入れ、徐々に増すアンビエンスの中に霧笛を思わせるホーンが寂しげにうなる。ドローンやかすれる弦が生むノイズは「綺麗ではないアンビエント」で、『The Ship』のモチーフのひとつであるタイタニック号の夜間航行の雰囲気。ヴァイオリン他の手持ち楽器を担当するミュージシャンは演奏しながらステージを淡々と歩き回り、その光景は雑踏のようでもあり、幽霊の群れのようでもあり、集団労働の場のようでもある。全員、黒地に様々な色の大きな丸を染め抜いたTシャツ&黒ズボン姿。ひな壇の上の、シンセ他のハードウェアが囲む中央ブースにイーノが立った。
バルト海沿岸10国(ヤルヴィの出身国エストニアも含む)の音楽家育成のため2008年に設立されたユース・オーケストラを母体とするバルト海フィル(32名)は見たところ20〜30代。ハープやチェロといった大型楽器奏者以外は椅子を使わず譜面台もなしで、リード/弦/金管勢は曲の展開に合わせて持ち場を変え、観客に背を向けたり床に座ったり、コーラスを添える。バスティルとの共演はオーソドックスなスタイルで演奏しているが、今晩の彼らは「バックの楽団」ではなく文字通り「パフォーマー」だ。
それ以上に目を奪うのがヤルヴィの指揮ぶり。「熱血指導」と形容される彼のスタイルは、クラシック音楽ファンの間ではつとに知られているらしい。一応ステージ前方中央がポジションとはいえ、団員の中に分け入って面前で細かく指示を出し、歩き回り、跳ね、グルーヴにノり、歌い、フレームドラムを叩き、満面の笑顔で観客を煽る――イーノはヤルヴィを「船長」と呼び、かつ「この人はトチ狂ってる!(笑)」と紹介していたが、ここまで「全身を使ってコンダクト」する指揮者にはお目にかかったことがない。ジャズやヒップホップを吸収した室内楽アンサンブルから始まり、スティーヴ・ライシュからマックス・リヒターまで多彩な共演を果たす等、20世紀の重鎮(旧世代)と彼らに影響されたコンポーザー(新世代)を橋渡しする意欲的なこの御仁(作曲家でもある)は、なるほど複数のモードとジャンルが混じった本パフォーマンスのキャプテンにふさわしい。
ゆえにこの型破りなコンサートをデイヴィッド・バーンの『American Utopia』と比較する声があったのも、ある程度は理解できた。しかし『Ships』は『〜Utopia』のようにガチに振付けされたミュージカルではなく、ストーリー性も「提示」というより「喚起」だ。それは、刻々とモーフしていく音像と抽象的なヴォーカリゼイション――『The Ship』で歌われる/朗読されるのは、第一次世界大戦時の歌やタイタニック号沈没報告書等をアルゴリズムを用いて変換・生成した言葉だ――というコンポジションの性質が大きい。

20分以上にわたるダーク・アンビエントなタイトル組曲“The Ship”は、冒頭のさざめきがいつしか群青の海に姿を変え、ピンスポットに浮かび上がったイーノが歌い始める。ハーモナイザーで加工しているものの、ロシア正教会聖歌風の歌唱が深々と響く。アルバム版はシンセが基調だが、オケの生音で聴くと立体的な隆起性や重力がそこに加わる。『The Ship』は元々オーディオ・インスタレーションとして創案され、多種多様なスピーカーやチャンネルが用いられた。イーノは「スピーカー群をオーケストラ楽器の一群のように捉える」と語っていたが、このパフォーマンスはその発想を逆転させたものと言える。演奏者が移動し、向きを変え、しゃがんでいた状態から立ち上がるにつれ、サウンドの遠近・高低・バランスも微妙に変化。「動き回るオケ」というのは一見ギミックぽいが、それは『The Ship』を生演奏で体験するための必然だった。
雅楽的なパーカッションに同期して照明が明滅し、女性と男性のミステリアスなささやき――テープではなく、リアルタイムで加工されてはいただろうが、ブレスやマイクとの距離等々で声の響き方を見事にコントロールしている――が入り混じる。すれ違う記憶、もどかしさ。クリス・マルケルの映画を思わせる瞑想的なムードの中、最後は「Wave, after wave / after wave…」のリフレインが引き潮のように残った。
続く“Fickle Sun”組曲は、コントラストを強調しドラマ性を高めた演奏だった。“Fickle Sun 1”で、チェロやヴィオラが敷く不気味なドローンの上をイーノの達観した「And on the day the work is done…」の声が流れる。縁の下の力持ち的存在だった管楽器が威力を発揮し出し、弦の刻む重音とねじられうめくヴォーカルも緊迫感を煽る。暗かった舞台をオレンジの照明が煌々と照らし、吹き荒れるスモーク――クレッシェンドの迫力はさながら『地獄の黙示録』の爆撃場面(いや、この楽曲のモチーフを思えば『西部戦線異状なし』か)で、うなり、振動する大音圧が皮膚にじかに感じられる。ドゥームメタルのライヴに近い聴体験だったが、決して耳に負担ではないのはライヴ音響担当者の功績だ。ほんと、とんでもなく良いサウンドだった。
業火が吹き荒れた後に、「All the boys are falling down…」と歌い始めるイーノ。このパートはマニピュレートしない地声で、無防備なぶん哀感が増す。古い宗教歌や民謡を彷彿させるハーモニーがせりあがり、「テ・テ・テ・テ・テ…」と一音をループする女声が精霊のように飛び交う異界に落ち、舞台は暗転した。しばし間を置き、頭上から黄金色の照明がハープに注がれ、その雅びなメロディとコントラバスのかすかなタッチを伴い、セラフィノヴィッチが美声で朗読を披露。短歌にしろソネットにしろ、詩とは本来こうして「耳で聴く」ものだったのを思い起こす。声は楽器だ。
ムードが落ち着いたところで舞台全体に少しずつ照明が復活し、フルートの調べに導かれる形でヴァイオリン奏者9名もステージに戻ってくる。デリケートな潮のごとく満ちていく音の海の中から、紛うことなきルー・リードのあのコード感覚が浮上してくる。それだけで筆者は不覚にも涙してしまったが、甘くも芯は太い声でイーノの歌いあげる「And now I'm set free / To find a new illusion」にどうしようもなく情感が高まり、涙腺の堰は決壊。ステージ上の全員が初めて一斉に観客に顔を向け、照らされた観客席と一体となった。「私は自由になった/また新たな幻影(物語)を見つけるために」のフレーズのイーノ解釈は、歴史という名の「物語の累積」から解放され、自分自身で新たな物語を見つける自由を得た歓びだ。未来に希望を捧げるフィナーレ。
この貴重な機会を無駄にするわけにはいかないとばかりに、「じゃあ、あと何曲かやるよ」と第二部がスタート。「50年近く前に書いた曲だ」のMCに場内にさざめきが走り、照明が緑/青/紫にスイッチしのどかな鳥の歌声と川のせせらぎが響き出す――名曲“By This River”だ。至福。ピアノのパートをハープが紡いだことで、アルカイックとモダンが混ざり合った不思議に根元的で透徹した原曲の味わいに素朴でメルヘンな響きが増している。ピアニッシモな美とメランコリーで内側から輝く素晴らしい演奏だった。
続いて、最新作『Foreverandevernomore』から“Who Gives a Thought”。「誰が蛍のことを気にかけるだろう」という問いかけから始まる歌詞は、川のテーマ続きで納得だ。ディテールに富んだサウンドでアンビエントなサウンドスケープが構築されており、オケの繊細な演奏を堪能。ヤルヴィが振り始めたシェイカーにのってドラムがリズムを刻み、リオ・エイブラムスが軽やかなフレーズを吹き流す。「まさか、“Spinning Away”!?(だったら嬉し過ぎる!)」――と一瞬思ったが、ソロ・コンサートなのでやはりそんなことはなく、(これまたレアなイーノのヴォーカル・アルバム)『Another Day on Earth』収録の“And Then So Clear”。
この晩初めて一般的な意味での「グルーヴ」が広がり、前列にじーっと座っていた高校生くらいの少年が嬉しそうに身体を揺らし始める。プロセスされたヴォーカルは『Age of』期のOPNを思わせる響きだったが、イーノらしいリリカルでポジなメロディと歌詞の朝焼けのイメージ、バラ色の照明に包まれ、ステージ上の38名が作り出す「歌」――文字通り全員が合唱し、「演奏」していないプレイヤーも楽器のボディを軽く叩きパーカッション部に貢献していた――はあまりに温かく、「アァァァ〜ッ」の最後のコーラスはゴスペル合唱団を思わせるグロリアスさ。これが普通のコンサートだったら、観客も立ち上がり歌に参加していたことだろう。

スタンディング・オベイションと鳴り止まないアンコールの喝采を受け、パフォーマーがステージに戻ってくる。ヴィオラとチェロのリズミカルなリフがズン・ズン……と拍動し始めムードは一転、不穏に。マリンバも加わりスティーヴ・ライシュ的なミニマリズムが形成され、パッペンハイムの朗誦がダークなサウンド・ポエトリーを編んでいく。演奏後、この“Bone Bomb”(『Another Day on Earth』収録)の背景についてイーノは以下のように語った:
「新聞を読んでいて、自爆テロ犯になることを決意したパレスチナ人少女と、その逆の立場にいるイスラエル人医師の談話、その両方に出くわした。医師いわく自爆テロ犯の骨片は一種の散弾になり、被害・負傷は悲惨さを増す。一方、少女は自分が役に立つにはそれ以外にない、と考えている。実に悲しいことだ。曲を書いた当時(※第二次インティファーダ期)、私は『この紛争はなんとか解決するだろう』と思っていたが、もちろんそれは甘い考えだった」
「過去12日ほどの間に戦火は激化し、パレスチナ人の子供は4千人近く、おそらくイスラエル人もそれくらい命を落としている。にも関わらず英政府は、イスラエル支援のために軍艦を送り込んでいる。とにかく――停戦しようじゃないか! 今夜のマーチャンダイズ販売の収益はチャリティ団体『Medical Aid for Palestinians』に寄付されます。皆さんもぜひ、停戦を求める次回のデモ(※イギリスでは10月14日以来毎土曜に行進がおこなわれている)に参加ください。それが無理でも、寄付をしてください」
このツアーの始まる少し前に、パレスチナ・イスラエルの即時停戦を訴えるアート・コミュニティからの公開書状にイーノは署名している。しかしこの真摯な人道的呼びかけに対し、満場一致の大喝采……とはいかず、客席の反応がやや及び腰だったのは軽いショックだった。イーノのファンであるような左派〜リベラル勢の間ですら、パレスチナ・イスラエル戦争に対するスタンスを表明することは一種のタブー、触れられたくない腫れ物なのか、と(もちろん、「純粋に音楽を聴くために来たのであって、政治に関する説教は要らん」と感じる観客がいても当然だが)。ちなみに前労働党党首のジェレミー・コービンも観に来ていたが、彼は「一般市民の犠牲に対する批判」としてパレスチナ支援を表明したことで反ユダヤ主義の疑惑をかけられ、党員資格を一時停止されたことがある。それくらい歴史的・政治的・感情的に複雑に入り組んだ問題であり、分断でささくれたこの時代、おいそれとクチバシを突っ込まない方が無難な「火中の栗」なわけだが、公なプラットフォームを持つ者としての責任を放棄せず、自らの信念をはっきり打ち出したイーノに筆者は感動した。
「この曲を、パレスチナ・イスラエル紛争の犠牲者への一種の鎮魂歌に作り替えました」の言葉に続き、“Making Gardens Out Of Silence”。原曲は寂寥たるアンビエント・ピースだが、コオロギの鳴き声をイントロにサウンドがゆったり膨らんでいき、ヴォコーダー等で処理されたヴォイスの切れ端が織り込まれながら、やがてコズミックな聖歌に発展。宇宙へ――この感覚は、最後に披露された“There Were Bells”の悠久な響きにも流れていた。鳥の声のフィールドレコーディング(空)から始まり、現在のイーノが誇るディープな歌声がおごそかに(地に)降り積もっていく。「Never mind, my love / Let’s wait for the dove」――実に悲痛なメロディは、おそらくこの晩もっともエモーティヴな歌唱で客席に落ちてきた。ミラーボール調の照明はさながら光の祭典で、激しく隆起するサウンドもアナザー・ワールドに向かっていくが、イーノの歌は地に足を着けていた。
まさに「乗り切った」と言いたい熱演。喝采の中、改めての挨拶でヤルヴィが「皆さん、ブライアン・イーノです!」と紹介し、ライヴ音響エンジニア(3名)&照明スタッフの秀逸な仕事にも謝辞が送られ、熱いねぎらいの喝采が起こる。楽団員、ゲスト・パフォーマーら、全員がステージ前列に並び、そろってお辞儀――これはロック・コンサートでは「お約束」の図式だが、中央のイーノがぼーっと突っ立ったままだったのが印象的だった(ヤルヴィに促され、「あ、そうだっけ!」とばかりに、慌ててお辞儀に参加していた)。ベテランでありながら、この人はどこまでも「素人」だ。
その微笑ましい姿と、三世代――イーノを最年長に、中年(ヤルヴィ他)、青年(オケ)――が達成感いっぱいの笑顔を浮かべる光景を見ていて、イーノの語った音楽システムの「ヒエラルキー」を思い出した。彼は伝統的な西洋クラシック音楽のオーケストラ構造を、神を頂点に、その声を耳にし記譜した作曲家とそれを指揮するコンダクターが上部に、その下に演奏家が位置し、またそれら演奏家の中でも第一奏者から副奏者までいる……というトップダウン型のピラミッドになぞらえた。対してアフリカ音楽では、実はもっとも大事な基盤を成しているのは単純なビートを淡々と鳴らし続けるいわばヒラの演奏家だ。
この形容は「音楽はそもそもその成り立ちからして政治的」という話の中で出て来たものだったが、後者の例が民主主義モデルのそれであるのは言うまでもない。この晩の演奏にしても、ポップ〜ロック系コンサートであればヴォーカルが担うフォーカル・ポイントは固定せず、歌う場面でたまにスポットライトが当たる以外はイーノも終始後方に潜んでいた。先述したように、「歌い手」ではない指揮者やオケのメンバーも合唱していた。有機生命体のように全パートが関わり合い、シナプスで連携し、その場の状況に自らの意志・判断でリアクションする集団。それはまさに一隻の大きな船だった。
アンビエント曲をオケに翻案していく過程で、クラシック音楽界では耳慣れないような、抽象的なリクエストも飛んだことだろう。だが、ヤルヴィとバルト海フィルは「楽譜に書かれた通りの指定を忠実に遂行する」クラシックの伝統に縛られない若さ、そして生き生き自己主張しながらも全体像に貢献するポジなエネルギーで、イーノのアイディアを具現化したと思う。キャリア初期に、イーノはポーツマス・シンフォニアやスクラッチ・オーケストラといった、素人も参加OKの実験的な楽団に加わったことがあった。以降、アートの大海をひとりでボートを漕いで進むことが多かったとはいえ(エゴ云々ではなく、次々生まれるアイディアを形にするのにはその方が速いからだろう)、コラボレーションから生まれるシナジーは常に大事にしてきた。遂に理想的なオケと出会った彼は、75歳にしてこの初体験に果敢に挑んだ。その衰えないチャレンジ精神、サウンドとビジュアルに対する尽きせぬ好奇心、そして過去数年より顕著になっている活動家としての面をひとつにまとめて提示してみせた、まさに「イーノのナウ」が凝縮された素晴らしいコンサートだった。

SET LIST
The Ship
Fickle Sun 1
Fickle Sun 2 - The Hour Is Thin
Fickle Sun 3 - I’m Set Free
By This River
Who Gives a Thought
And Then So Clear
_________________
Bone Bomb
Making Gardens Out Of Silence
There Were Bells
文:坂本麻里子
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE