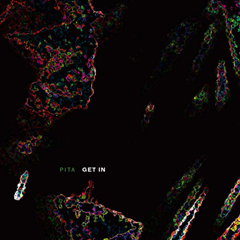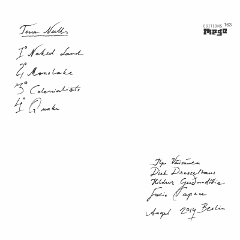MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Fenno'berg- In Stereo
00年代を予見した音楽としてレイディオヘッドやゴッドスピード・ユーが取り沙汰される時、それは気分的なものを差すことが多い。アラブ・ストラップであれ、フィッシュマンズであれ、90年代末にメランコリックなムードが充満していたことはレイヴ・カルチャーへの反動としても理解できるし、同時多発テロ以降の閉塞感を見通したというのなら、そういう言い方も決して無理ではないだろう。ゴッドスピード・ユーには、しかも、ドローン的な表現との橋渡しになるという音楽的なポテンシャルも少なからずあった。サン O)))やナジャといったドゥームからアルヴァーやヴェルヴェット・カクーンといったブラック・メタルにもその陰は落ち、アンチコン=ヒップ・ホップやブレイクコア=ワールズ・エンド・ガールフレンドがその磁場に引きずり込まれていったことも印象的なモーメントだったといえる。
予見的な可能性という意味では、しかし、99年も終わろうかという頃にリリースされた『マジック・サウンド・オブ・フェノバーグ』よりも音楽的なポテンシャルの高さを示したアルバムは当時はほかになかった。クリスチャン・フェネス、ジム・オルーク、ピーター・レーバーグという、その後の10年間にわたって存在感をアッピールし続けた3人が抽象的なイメージと具体的なサンプリングをぶつけ合い、勃興期のレイヴ・カルチャーとはまったく異なる混沌がそこには叩きつけられていた(チックス・オン・スピードによる奇怪なアートワークも強烈だった)。それは早くもエレクトロニカの鬼っ子的な表現であり、結果的には実験音楽の復興にも寄与する導線ともなった。あるいはブラック・ダイスというフィルターを経てオーヴァーグラウンドとの接点を探るものとなり、ピーター・レーバーグがサン O)))のスティ-ヴン・オモリーと組む(=KTL)ことでドゥームとのクロスオーヴァーも達成している。ソースはあらゆる方向にぶちまけられたのである。
KTLが来日した際、レーバーグに話を聞いていると、ふと、彼が「フェノバーグの3枚目が出るよ」と教えてくれた。3年前のことである。なんだよ、ウソだったのかなと思っている頃にようやく『イン・ステレオ』が店頭に並び、輸入盤はすぐに売り切れた。02年にリリースされたセカンド『リターン・オブ・フェノバーグ』(これもチックス・オン・スピードによるアートワークが秀逸)がシャープさを増していたのに対し、3作目は自らがつくりだした混沌を増幅させるようなものではなく、ヨーロッパ的な洗練に磨きがかかっているような印象が強い。唯一のアメリカ人であるジム・オルークが『ザ・ヴィジター』でポスト・クラシカルの決定打といえる方向性にシフトしたことも関係があるのだろう(アメリカのシーンが衰退しているわけではない)。かつては弾け飛ぶように、あるいは、突き刺さるようにアウトプットされていた電子音はここでは何かを撫で回すようにねっとりとした感触に取って代わられ、安直なアンビエント・ドローンへの迎合どころか、部分的にはジョン・ハッセルやラズロ・ホルトバギを思わせるドローン・ジャズとも接合しかねない。なるほどこれはミュージック・コンクレートとクラブ・ミュージックの快楽性を止揚させた成果といえるだろう。そう、クラブ・ミュージックのチープさを批判し、高度な音楽性を訴える者はここまでやるべきではなかったか。
三田 格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE