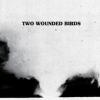MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Everything Everything- Schoolin'
UKからなにか目新しい音は聴こえてこないだろうか。ここ数年来、インディ・ロックと言えばUS。新鮮な驚きはつねに北米シーンに寄り添うようにしてあった。なるほどUKもグライムやダブステップにおいては活発な細胞分裂が進んでいるのかもしれないが、いわゆるロック・シーンの状況は低迷の感を否めない。クラクソンズのデビュー作が2007年だ。目立った更新がないまま、3、4年が過ぎようとしている。
エヴリシング・エヴリシングが新しい時代を作り得るかどうかはともかく、彼らのような音に名前がついていないことを不思議に思ってきた。もちろん、ネーミングなどプレス・サイドの一方的な押しつけだとも言えるし、あくまで便宜的なものだ。だが、名の知れたところではホット・クラブ・ド・パリス、最近ではチャップやチューブ・ロード、ハイ・レッド・センター(US)等々のバンドは、なにか気の利いた呼称で括ってもよさそうなものである。マス・ロック的なアプローチとプログレッシヴ・ロックの影響濃いアーキテクチュアルな曲展開、奇妙なコーラス。躁鬱的なビートにはポスト・パンク・リヴァイヴァル勢の残り香もある。いまのところ、この種の音はUKバンドに多い。そしておそらく、水面下にはもっと多く存在していると思われる。彼らには"アート・ロック"あるいは"マス・ロック"という言葉では広すぎるほど特定的な色合いがあるし、UKロック・シーンの一潮流としてもっと認識されていいのではないだろうか。エヴリシング・エヴリシングはファースト・フルを今月末に控え、〈サマー・ソニック〉への出演が決まっている。彼らへの注目が、こうした一連のバンドを浮上させる契機となればよいと思う。
さて本作は、そのデビュー・アルバムに先駆けたミニ・アルバムで、来日記念盤となる。UKバンドならではの売り出し方だ。「BBCサウンド・オブ・2010」として、ザ・ドラムスやデルフィック、ゴールド・パンダらとともに選出されている他、〈NMEレーダー・ツアー・2010〉でもヘッドライナーとして抜擢されるなど、メディアの期待とプッシュが大きい。また、前掲のハイ・レッド・センターやチャップ等と比較して格段にポップでもある。曲単位でもバンド自体の佇まいでも、メジャーな存在感という点では頭ひとつ抜きん出た印象だ。
"スクーリン"はいかにもシングル曲といったキャッチーなナンバーだが、神経質なシンコペーションと不自然に固さの残った――ぎこちない、というのではない――ファンクネスに、このバンドのキャラクターがよく映し出されている。彼らのリズムには肉体に一種の緊張を強いるようなところがある。ファルセット・ヴォーカルやリズムのパターン自体がソウルフルな印象を与えるとはいえ、それは例えばTV・オン・ザ・レディオやブラック・ジャックスのように、どこか身体性からはみ出てしまう覚醒感を伴っていて、乱暴に言えば非常に西欧的なものだ。ややウェル・プロデュース気味なストリングスのイントロに続いて、しつこく耳に残るフレーズがせわしないビートとともに次々とつなげられる。展開自体はかなり急転直下型というか、フレーズとフレーズの連続性を寸断するような進行には方法論としてはポスト・パンク的なものを感じる。ソリッドなギター、よく動くベース、ぴたりと決まる和音。ポップだがかなりねじくれた音だ。そして忘れ難い。
"メイキング・サム・ニュー・センス"はクイーンとレディオヘッドを繋ぐミッシング・リンクとも言えそうな、じつにブリティッシュな旋律を持ったナンバー。ヴォーカルのやや過剰なエネルギーも両者によく似ている。壮大にして繊細なアレンジ。打ち込み主体の曲で、生音へのこだわりはとくにないバンドなんだなと確信する。ラストはやはりグリー・クラブばりの同声四部を聴かせてくれる。
"DNA・ダンプ"も変拍子風のリズムが暴れるグルーヴィーなポスト・パンク・チューンだ。クリーン・トーンのアルペジオがポスト・ロック的というか、彼らの出自のひとつを証すように鳴っている。この曲がもっとも同系統のバンドとの共通項が多い。"ラッダイト・アンド・ラムズ"は粘りつくような3連符が昂揚を生むハイエナジーなギター・ロック。タイトルからして、社会風刺的な意味が強そうだ。ポップ・ミュージックにおいてこうした要素が果たす役割は小さくない。美術の世界における「マイクロ・ポップ」なる概念と相似形を成すように、現USの一大潮流であるシット・ゲイズ~新世代のローファイ・シーンは、社会や国家といった抽象性を切り捨て、ささやかな日常の世界に退却することで2000年代末のオルタナティヴなマナーのひとつを提示してきた。そんなムードのなかで大上段に振りかぶったテクノロジー批判には、しばらく忘れていたポップ・ミュージックの王道を感じさせる。
そして興味深いのが"ライオット・オン・ザ・ワード"。完全なア・カペラ作品となる。ベンジャミン・ブリテンやジョン・ラターなど20世紀のイギリス人作曲家による合唱作品を思わせるのだが、非常に新鮮に聴いた。世俗化した宗教曲といった雰囲気で、夜露とふくろう、聖堂の回廊などのイメージが立ち上がってくる。ラターの曲のように、シンプルな和音と旋律。カウンター・テナーが誘い込む、霧深い英国の森......それは時計ウサギがおかしな時間を指し示し、チェシャ猫が歯を見せて笑う、ルイス・キャロルやマザー・グースの英国である。こんな曲が1曲忍んでいるのもおもしろい。
天気雨のように不可思議なバランスでポップと過剰が入れ替わる、ブリティッシュの伝統と新しさを備えた好バンドである。USのローファイ・コロニー〈キャプチャード・トラックス〉からもUKバンドが出てくる昨今だが、あくまでUKはUKらしさのなかから次の音を生んでほしいと思う。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE