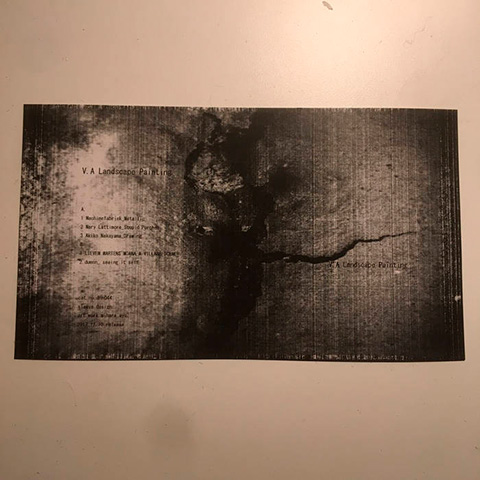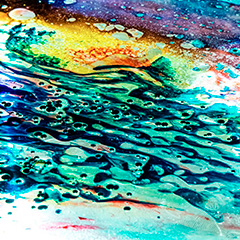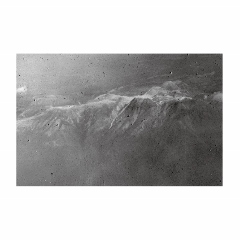MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Various Artists- duenn presents "after tape&…
このカセットテープの作品は、リリースしてから数か月が経っている。それを何故いま取り上げるのかというと、先月、ようやく家のカセットデッキを買い換えたということが大きい。それまで使っていたカセットデッキはずっと調子が悪く、たまにトレイが止まったりするので(小さな子供がいる方にはおわかりになるだろうが、わりと低い位置に置かれるCDプレイヤーやカセットデッキは頻繁に玩具とされる)、仕方がないから昔のラジカセで聴いていたりしていたのだが、晴れてアンプに繋げて家のスピーカーで聴けるようになった。カセットテープ・シーンについて書いておきながらなんたることだと思われるかもしれないが、値段にかかわらず、ひとつの機材を買うにはそれなりの決心がいるし、聴けないわけでもなかったので、消費するかどうか迷っていたのである。
そんなわけで、カセットデッキを子供には届かない高い位置に置いて、カセットテープというメディアを操作する面白さを噛みしめながら、最近購入した数本を聴いた。カセットテープの良いところのひとつは、その構造を素人でもある程度理解できることだ。実を言えば、数か月前僕はラジカセを1台修理した。修理といっても、劣化したベルトのゴムを数百円で買ってそれを取り替えただけだが、アナログ再生装置は仕組みがわかりやすい。デジタルにはない安心感がある。そうした安心感は、福岡のアンビエント・レーベル〈ダエン〉から1260円で発売されたこの素晴らしい作品を聴くにはひとつ重要な要素だと思われる。
本作『after tape』には、以下の23組の作者がすべて1分の曲を提供している。まずは作者の名前を列挙すると......duenn / PsysEx / LiSM aka GoHIYAMA / 白石隆之 / on_14 / aenpawn.aka.hidekiumezawa / HAKOBUNE / Kmmr / ヒトリアソビタラズ / source / TAGOMAGO / Escalade / Go koyashiki / akira_mori / yui onodera / arcars / tamaru / polarM / koyas / 毛利桂 / Computer Soup / NERAE......といったところで、知っている名前も何人かいるが、僕には初めての人も多い。が、これは匿名性の高いアルバムだ。なにせひとり1分であるがゆえに、気がつくと他の曲になっていて、どれが誰の曲かよくわからなくなる。
1分の曲という尺も面白い。ポップスのような商品性の高い音楽でも、消費者に記憶させるために3分は要する。が、1分ではなかなか覚えられない......というか、わかりやすい反復がいっさいないこのカセットテープでは、曲という単位がぼやけてしまい、このテープ1本が23組による共作のように聴こえる。でもたぶん、そういうつもりなのだろう。
面白いのは、すべての作者の曲は音数が少なく、そして「間」という概念があることだ。これは日本的な叙情性が関係しているのだろう。1ヶ月ほど前に三田格さんからティム・ヘッカーを数枚貸してもらい、それらはずいぶんと楽しめたが、あれはどうにもヨーロッパの感性がある。カテドラル・アンビエントと呼ばれほどであるからまったくそうなのだが、それに対して『after tape』はワビサビで、その美意識はアンビエント/ドローン(もしくはクラウトロック的なアイデア)と親和性が高い。僕はたいした数のアンビエント・ミュージックを聴いているわけではないので他と比較しようがないのだけれど、ひとり1分というコンセプトもさることながら、『after tape』のアンビエントは群を抜いてユニークなのではないだろうか。
音の質感に関して言えば、たとえばエイフェックス・ツインの『アンビエント・ワークス』のほとんどのマスターがMTRで録音されたカセットテープであるように、ここには独特の中域、こもり方(人によっては温かみとも言う)がある。まあ、いまどき作者たちの多くは(というか、ほとんどは)デジタルで録音しているのだろうから、『アンビエント・ワークス』を持ち出すのもおかど違いといえばそうだが、カセットテープでしか出せない質感は確実にこの音楽に良い影響を与えている。
そしてこういう作品は、やはり店で買って、家に買ったときにバッグから取り出してウキウキしながら聴きたい。下北沢のワルシャワにはたくさんのカセットテープが並んでいるが、値段的にも安いので、そのなかのどれかを買おうかなと思ったりするとちょっとワクワクする。一時期は、もうこんな不便なものは要らねーやと思っていたというのに、我ながら身勝手なものだなあと痛感する。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE