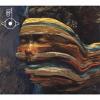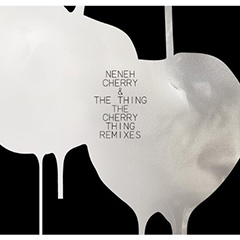MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Bjork- Biophilia
「アメリカのロックンロール産業はアイスランドの電気工組合にくらべてずっと保守的」と言ってのけたのが、もう10年以上昔のビョーク・グズムンスドッティルだ。「電気職人はとにかくで適応が大事。毎年新しい器具が出てきて、いちど電工になったら最後、新しい動きについていくためにいつもいつも研修を受けに行かなきゃならない」※
今日のUSインディ・シーンにおいて、ラップトップを使った女性アーティスト(ジュリアンナ・バーウィック、グルーパー、U.S.ガールズ、グライムス......そしてアマンダ・ブラウンやマリア・ミネルヴァなどなど)が大勢出てきたことの契機のひとつとなったのは、まあ、間違いなくビョークだろう。『ホモジェニック』以降の彼女の音楽、そしてひょっとしたら彼女のa way of lifeもそれを促しているかもしれない。16歳でシングルマザーとなって、アナーキスト・バンドのクラスに会いに行くために角砂糖をなめながら旅費を貯め、2ヶ月も風呂に入らずアイスランドからベルリンまで車中で過ごしたような経験を持っている女性が、やがてアイドル的に華々しくソロ・デビューを果たし、そして最初に売り上げが下がったアルバム『ホモジェニック』において用いた方法論――つまりラップトップによるIDMサウンドをその後の自らの基盤としたビョークの活動の軌跡は、性別に関係なく触発されるものだ。彼女が"ハンター"で歌ったように、「旅の途中で家を見つけたとしても、私はそこにとどまらない」とは真実なのだ。
僕はいま『EYESCREAM』誌の連載コラムで『バイオフィリア』について書き終えて、そのノリのなかでこのレヴューを書いている(これはそのコラムの補足のようなものです)。『バイオフィリア』は"自然科学"をモチーフとしたアルバムだが、コラム原稿のなかで、彼女がエレクトロニクスを用いて"自然"を描いた最初の名曲が"ヨーガ"であると僕は書いている。"ヨーガ"は、3.11を経験している我々がいま聴いたら重たい曲かもしれない。何故なら彼女が表現する自然とはオーガニック系が好むところの豊かな緑と暖かい海に囲まれたそれではなく、地底でマグマがうごめき、灰色の岩々が空に突き出た、荒涼とした大地が広がる自然なのだ。それは心象風景でもあるが、間違いなく自然そのものでもある(そしてその曲には、アレック・エンパイアによるさらに荒涼としたヴァージョンが3つもある)。あるいはまた、彼女は『ホモジェニック』に収録された"アラーム・コール"では、長持ちする電池とカセットを持って山頂に登って、愉快な音楽を流して人類を苦しみから解放することの夢想を歌っている。彼女は自然も愛しているが、同時にテクノロジー(科学)への評価も忘れない。
......と、偉そうなことを書いているが、正直なところ僕はビョークに関してはなかばミーハーなので、先行リリースされた12インチも4枚買ったし、今作の話題のひとつ、曲ごとのiPhone用のアプリもすべて購入した。もっとも僕はタッチスクリーン操作が彼女ほど好きではないので、電車のなかでちょっと触ってみるぐらいだが、まあ簡単に言えば、学研の『科学』の付録のようなものである。「科学とアートはかつて同じところにいたのよ。21世紀になって、その両者はふたたび結ばれるんじゃないかしら」と、彼女は『ガーディアン』が企画した読者からの質問に答えている。
とはいえ、ビョークは科学者ではなく音楽家だ。かつて自分の音楽を「本能的」と形容した彼女の本質が変わっているとも思えない。理性を失っているわけではないが、ディオニソス的である。アルバムのなかのベスト・ソング"クリスタライン"は、結晶=鉱物を曲のテーマにしている。稲垣足穂めいた美意識を持ったこの曲には、いまでも「ナーディなダブステップや2ステップ、ミニマル・テクノのCDを買っている」という彼女らしい躍動的なブレイクビートの素晴らしい展開がある。いまでも僕は『ホモジェニック』を愛しているが、ストリングスを多用したあのアルバムのメランコリーに比べて『バイオフィリア』には"クリスタライン"に代表されるシンプルさと前向きさがある。"コモスゴニー(宇宙発生論)"も白眉のひとつで、この曲には『ホモジェニック』ならびに『ヴェスパタイン』とより近い叙情的なエレクトロニックな響きがある。サブベースを擁した"ウィルス"、ハーブのシンプルな音と歌のみで構成される"ソルスティス"もまた、IDM時代のオルゴールのようである。
それぞれの曲には自然科学から引用したコンセプト(DNA構造をリズムに置き換えたり、重力や月の周期をリズムの反復に置き換えたり......)があるが、こうしたヨーロッパ音楽における数学的な論理ないしは天体の動きを譜面化するような試みは、それこそ彼女も言うようにギリシャ時代からあるもので(たとえばジョスリン・ゴドウィン著『星界の音楽』参照)、彼女が非宗教的な"科学"をモチーフにしたことは注目に値すると思うが、僕は『バイオフィリア』においてそのコンセプトの内容までは深追いはしない。 それよりも"自然"というテーマと直面としたときに生楽器の使用しかアイデアの浮かばないような音楽家とは100万光年離れたビョークの多様な音色と音階が織りなすエレクトロニック・ミュージックの面白さをまずは楽しみたい。『ピッチフォーク』は「革新者としての彼女はいまだ力強いが、ソングライターとしての彼女は疲弊している」などと書いているが、ソングライターとしての彼女は『ヴォルタ』のときよりも魅力を増し、音数は少なく表現として豊かで(サブベースは、現代的な威力を発揮している)、ところどころ陽気に僕には思える。まあ何にせよ、科学が金銭欲と結びつくよりも芸術と結ばれることを強く願っているのは、日本で暮らしている我々であろう。
※エヴェリン マクドネル (著)、栩木 玲子 (翻訳) 『ビョークが行く』 (新潮社)
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE