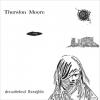MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kurt Vile- Smoke Ring For My Halo
別に「クソゲー」なんてクリアしなくてもいい。
クリアをあきらめて、友だちとそれなりの楽しみを見つければ、
この社会はそれほど悪くはない。
古市憲寿『希望難民ご一行様』(2010)
まずは、なんと言ってもその声だ。ルー・リード、ボブ・ディラン、あるいは、彼らに憧れたサーストン・ムーア以降のインディ・ロッカーたち......。ロックンロールの史学からすれば、まず間違いなくヴェルヴェッツ・スタイルを踏襲したトランス・ロッカーのそれだと推定されるであろう、けだるく、ナルシスティックな声を、カート・ヴァイル(31歳、ペンシルベニア州)は持っている。生まれた時代が違えば、アート・パンクの最前線で同時代の暗黒を歌っていたかもしれない。例えば、ノイジーなギター・ウォールに、時折、甘いメロディを載せて......。しかし、というか、実際のところ『Smoke Ring For My Halo』は、アコースティック・ギターの流暢なピッキングによって鮮やかに彩られた、丁寧なフォーキィ・ロック(欧米の批評では、"ストーナー・フォーク"ないしは単に"ヒッピー・フォーク")である。
とはいえ、ヴァイル自身がかつて創設メンバーでもあった、The War On Drugsの『スレイヴ・アンビエント』と同期するように、ここにもスペイシーな、エレクトロニック・ミュージックを通過した感性がある。古典的なフォークやブルースを背景に持ちつつも、プロダクションには浮遊感、さらには清涼感までもが漂う。しかし、同時代のフォーク同業者に比していえば、例えばボン・イヴェールのスピリチュアリズム、あるいは、フリート・フォクシーズのナチュラリズムからすれば、ヴァイルにはどこか堕落したような人間臭い雰囲気があり、実際、「変わりたくはないけれど ずっと同じままではいたくない/どこにも行きたくないけれど 僕は走っている/働きたくはないけれど 渋い顔で1日中座っているのも嫌だな」と、素朴な二律背反を、"Peeping Tomboy"で歌っている。
また、『SPIN』誌は、"偉大なる「No」の1年"と銘打った「The Best Of 2011」号にこう書いている。「カート・ヴァイル(とインディ・シンガー・ソングライターのひなたち)にとって、2011年は急浮上の1年となった。それも、混乱の季節にスポットを当てるのではなく、そこから距離を置くことによって、だ」。いわば、抑圧からも抵抗からも離れ、単なるフェードアウターとして生きること。低高度に降りて、俯瞰や巨視を徹底的にシャットアウトすること。夢から醒めることが、ある意味ではもっとも簡単な時代に、それでも音楽という時代遅れの夢をだらしなく見続けること。そう、現代ほど、反抗する理由に溢れ、かつ、反抗する虚しさに満ちた時代もない。例えば、『The Year Of Hibernation』(Youth Lagoon)が克服できずにいるような幼い虚無を、ヴァイルは自覚的に消化したうえで、自身の凡庸さや、世の不条理や、日々の平穏を憎まない。
さらにまた、前掲同誌に、ヴァイルはこんなことも語っている。「この世界に、どうにもならないくそったれなことや、あらゆる種類の、ギリギリの不安があるのは、知っているよ。人々は闘っているけど、クレイジーで恐ろしいことだよね。僕は家族とか、友だちとか、身の回りの小さな世界のことを考えているだけさ」――それは、ヴァイルが選んだある種の生存戦略なのだろう(『Rolling Stone』誌曰く、「彼流の楽観主義」)。したがって、ヴァイルがノイジーなアート・パンクを必要としないのは、当然だともいえる。選ばれた天性のサイケ声を持つ、長髪の青年が小さな世界で紡ぐ歌は、ベッドルーム・ライオットでさえ、ない。賛否あるだろうが、それはなんとなく不安の尽きない時代に、それほど悪くはなさそうに鳴っている。これもひとつの達観なのだろうか。
「僕たちがいつ老いるかを 僕は知っている/僕は死に向かっている/だけど必要なものはすべて手に入れた/今はそれで満足なんだ」 "In My Time"
竹内正太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE