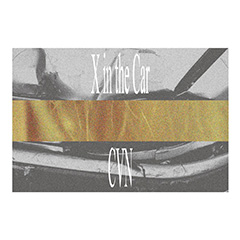MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Jesse Ruins- Dream Analysis
〈キャプチャード・トラックス〉のロゴをバシッとプリントされながら、いやそれであるからこそ、パッケージされている音が実際には圧倒的に日本的な情緒をたたえていたことに心を動かされた。いったいこの音を海外の人間がどんなふうに聴くのだろうか。無名の才能がブログ文化を通じて次々とフック・アップされる昨今、国も年齢も編成も知らずに音を聴く機会は増えたし、実際に海外のサイトがジェシー・ルインズに対しておこなったインタビューには「あなたがたは日本人か?」というような質問から始めるものもあったが、これとていまやめずらしいことではない。そうした流れにまきこまれるようにして輸出され、また逆輸入される運動において、ジェシー・ルインズはさながら木箱にオレンジとともに詰められてきたチェブラーシカのごと、日本訛りの正体不明な魅力としてさまざまな人の耳を惑わすのではないかと筆者はロマンチックに想像し期待している。
チルウェイヴや現在のUSインディ・シーンに同機する音楽性を東京周辺から抽出し、独自のカラーで存在感を示す〈コズ・ミー・ペイン〉の主宰として、また別名義のナイツ(http://cuzmepain.com/RELEASE.html)としても知られるサクマ・ノブユキことジェシー・ルインズのファーストEPが、先日シングルとともにUSの重要レーベル〈キャプチャード・トラックス〉からリリースされた。同レーベルのやってきたことは、レーベル・カラーとしてはっきりと打ち出されているように、ニューウェイヴやポスト・パンクとシューゲイズとのハイブリッドであり、参照点を80年代に置くバンドを多く輩出している。ジェシー・ルインズもダーク・ウェイヴの影響濃い音をしているが、それらを下敷きにしながらも非常に明るいアウトプットを持っており、そのことにも筆者はいたく共感した。
ナイツ名義で〈コズ・ミー・ペイン〉のコンピレーションに収録されていた"ケイティ"という美しい小品を耳にしたときに、すでにその感触があった。マイ・ブラッディ・ヴァレンタインをチルウェイヴの感性で翻案するようなドリーム・ポップだが、重要なのは曲なかばから入ってくるまるで不器用なシンセサイザーのフレーズだ。そこに筆者が述べようとする「明るさ」の感覚のほぼすべてがある。単純で、あからさまで、音量のレベルも大きすぎる。16小節もつづく。だがそれをまったくけれんみのない手つき、態度でやってしまう無垢(それは完全に無自覚になされているわけでもない、だがあざとさではあり得ない、確信に内側からみたされた、パンダ・ベアやトロ・イ・モワやその他フォトディスコなど2000年代から2010年代へのスイッチ世代に顕著な感覚だ。)に、いまという時代のエートスを感じる。そのいっぽうで、あの旋律、鍵盤ハーモニカのように無遠慮で無邪気な、しかし強度にみちた旋律には他の国の人がやらないようなある濃密な日本くささがある。さきに日本的情緒などと雑な言い方をしてしまったが、そこにはわれわれはたしかにそれを知っているというような、ある時代の、ある肉感的な記憶を喚び起こすなにかが埋め込まれている。
本EPでは"ソフィア"や"ラスト・アンド・フェイム"のシンセ・リフにそうしたノスタルジーが刻まれている。基本線としては、シカゴのアリエルやシークレット・シャインの近作のように〈サラ〉の雰囲気を持ったドリーミーなノイズ・ポップ......しばらく前にネオ・シューゲイザーと呼ばれたようなバンド群や、マンハッタン・ラブ・スーサイズなどジーザス・アンド・メリーチェインの遺伝子たちのまわりを低空飛行しつつ、"アイ・ニュー・イット"や"シャッター・ザ・ジュエル"などでジョイ・ディヴィジョンなどダーク・ウェイヴをかすめ、場合によってはセーラムなどを通過しながらダーク・アンビエントやブラック・メタルにものびていきかねない芽を予感させるものになっていて、だからもちろん純邦楽的な要素ともフォークロア的な文脈とも無関係なのだが、あの旋律にふれればきっとなにか日本に生きて目にした具体的な風景や感傷を引き出されるのではないかと思う。筆者の場合、それは90年代の後半の情景である。田舎の高校生活、ルーズソックスとポケベル、夏服とニルヴァーナ、運動部ならば顧問の先生が運転するワゴンでは誰かが『スラムダンク』を読み、誰かがポータブルのMDプレーヤーでミッシェル・ガン・エレファントを聴いている。そうした自分の記憶が山本直樹や宮台真司を通過して再構成されたような、幻想の90年代ともいうべきあの空気の薄い時代の記憶がなぜかしらたちあがってくる。そのころ日本の社会がどん詰まってから、とくに明るい兆しなどないまま今日まで一直線だが、のんきなのかシニカルなのか、わりに屈託ない明るさを持った眠りの音楽(=チルウェイヴ)をわれわれはいま好んで聴いている。サクマ・ノブユキ氏は筆者とは同年輩だろうか? ジェシー・ルインズの音楽は、筆者にはそうした奇妙な明るさでもってこの10数年をしずかにながめ、弔う音であるようにも思われてくる。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE