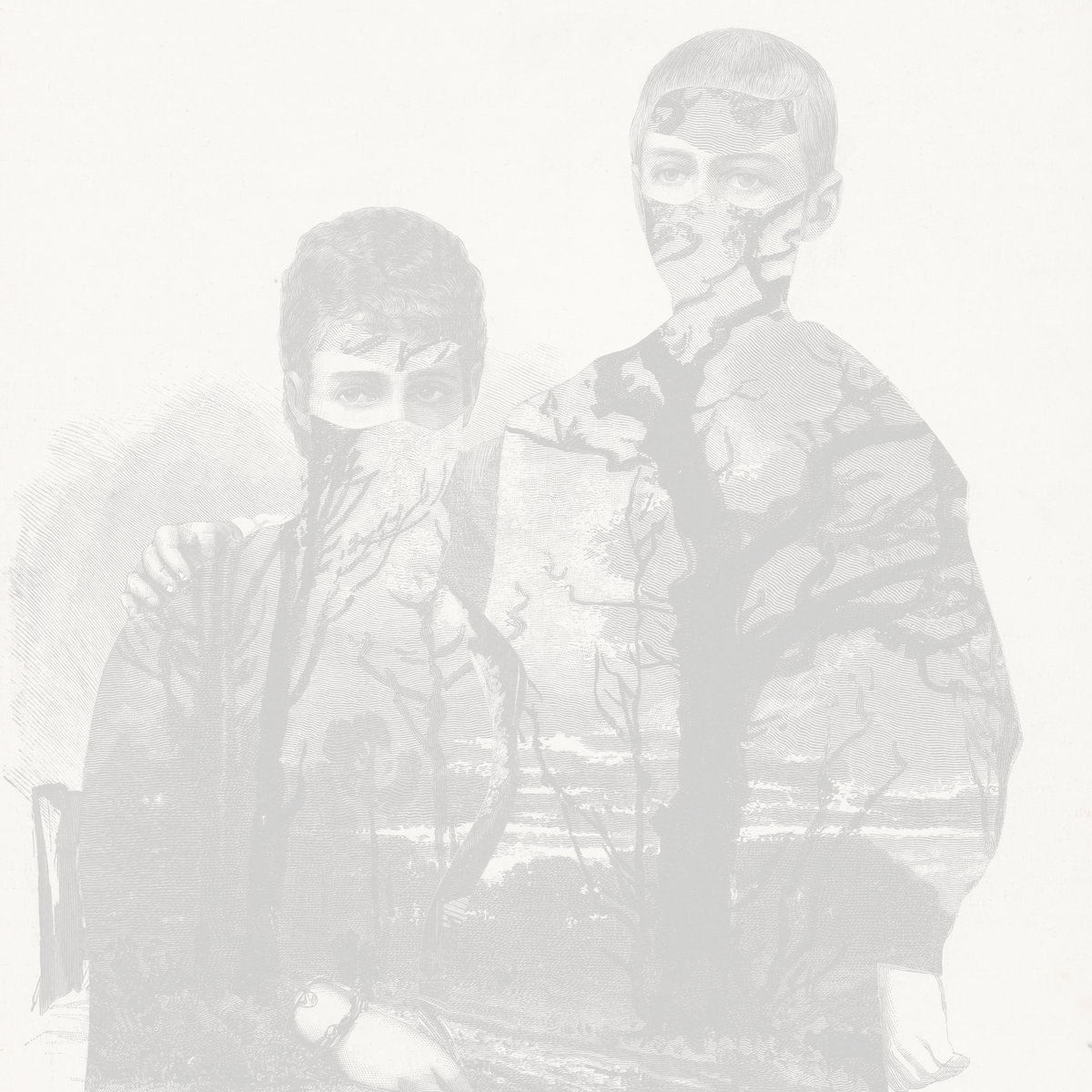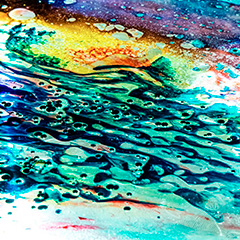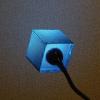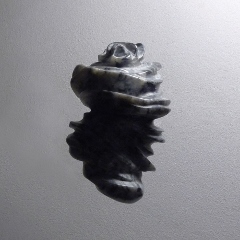MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Francisco López- Presque Tout (Quiet Pieces: 1993…

フランシスコ・ロペスの作品集が〈ライン〉からリリースされた。1993年から2013年までの20年間に制作された計7時間(!)におよぶ音源データを収録したDVDデータ作品である(データはWAV/44kHz/16-bitで収録)。ディスク1枚組であるが、通常のCDにすれば約7枚分ということになる。まさにボックス・セット並みの容量といえよう。
このフランシスコ・ロペスのクロニクル的な作品集を〈ライン〉がリリースしたという事実は、ロペスにとっても、〈ライン〉というレーベルにとっても、そしてわたしたちリスナーにとっても非常に大きな意味を持つ。〈ライン〉とは、サウンド・アーティストのリチャード・シャルティエが主宰するレーベルである。かつてロウワーケース・サウンドと呼ばれもした一連のミニマム・サウンドを牽引するなど(ポスト)デジタル・ミュージック・シーンにおいて重要な存在(現在はその種のサウンドにとどまらない幅広い作品のリリースを続けている)。「ほとんど聴こえない音から聴覚環境の再定義」を推進してきたこのレーベルにとって、オリジネーターの一人ともいえるロペスとの邂逅は必然であったはずで、それゆえ〈ライン〉は、「われわれのリスニング概念に多大な影響を与えたアーティストの作品をリリースしたことに非常に満足している」と公式サイトに書きつけたのだろう。そして、わたしたちにとっても、このディスクに収録されたサウンドに耳を澄ますことは、自身の「聴くこと」のパースペクティヴに対して、「聴こえないこと」を思考する貴重な(=批評的な)体験である。「聴こえない」ことは「聴くこと」なのかという問いは、ロウワーケース以降も重要な問いとしていまだ存在しているのだから。
ロペスの作品には、フィールド・レコーディングされたサウンドをそのまま用いたドローン的な楽曲と、ほとんど聴こえない静謐な音響というタイプがある。そして、より重要と思われるのは後者である。前者にはミュージック・コンクレートの現代的解釈という側面があり、はっきりとしたドローンとしての聴きやすさがあるが、前者のサウンドは聴覚として認知できるギリギリのラインで生成している。そこに極限の批評性があるように思えるのだ。
かつてロペスは、ライヴにおいて観客の周りをスピーカーで囲み、黒い布で目隠しをすることで視覚を剥奪し、音への距離や想像力を観客の側に近くへと引き寄せようとしていた。それはほとんど聴こえない音に対して聴覚を開くという意味もあったはずで、「見えない/聴こえない」の間から、「聴くこと」を浮上させる過激な試みであった。いってみれば、「見えない/聴こえない」というふたつの否定的な状況を設定することで、そこから本当の「聴く」という環境を生み出そうとしていたのだろう。そのために視覚を一時的に剥奪する。それがすなわち「聴くこと」への、より緻密で繊細な聴取体験に繋がるのだ。
その意味では、たとえば、視覚に対して過剰に高解像度データを注入し、同時に音も高解像度にマキシムであろうとする(近年の)池田亮司の作品と対になっているとはいえないか。それゆえ両者はほとんど同じ地点からモノゴトをはじめているようにすら思えるのだ。それは「聴こえない/見えない」という地点からのスタートとでもいうべきか。
池田亮司の作品は、すべてが高解像度に見えすぎる/聴こえすぎるがゆえに、ほとんど見えていない/聴こえていない状況を生み出してしまう。それは聴き手・観客に対して、限界ともいえる視聴覚情報を浴びさせることで、観客の判断を停止させるほどの体験の生成を意味する。マキシマムな高解像度の情報摂取ゆえの判断停止。過剰なゼロの状況の創出。彼のインスタレーションや音楽作品がときに「戦争」的な比喩を想起させるのもたぶん、そのせいであろう。また、その「崇高」な作品群はときにファシズム的美学へと接近する危険な魅惑に隣接している。まさに作品自体が情報と戦争の20世紀と化していくのだ。
対してロペスは、ほとんどゼロに近い状況からスタートし、観客の知覚をゼロの中にある微かな響きの地点を知覚させるようにする。そこにおいて美学は徹底的に剥ぎ取られ、見えない/聴こえない状況の中で、音環境の残存のような微かなものだけが存在することになる。視覚を奪われたわたしたちの耳はその残存の震えをより敏感に察知するだろう。音の微かな震えを感じること。池田とは正反対の方法論を駆使しつつ、限りなくゼロに近い音響空間を創出する。それは美学を放棄した音響芸術である。しかし、その放棄のむこうに、ギリギリの状況で生成する「瀕死の音楽」のようなものが立ち現れていくのだ。いわば零度のエクリチュールのような音楽/音響。
事実、このDVDに収録された音源データを聴きつづけると、わたしたちの耳は限りなく研ぎ澄まされていく。とくに注目したいトラックが本ディスクの末尾に収録されている2013年作の2作品だ。ひとつは18分の“アンタイトルド#309”。もうひとつは3時間におよぶロング・トラック“アンタイトルド#313 ”である。3時間の“313”は徹底的な微音量トラック。ほとんど聴こえない瞬間すらある。それは「聴く」という行為を必然的に対象化してしまうだろう。「聴こえないこと」に遭遇する体験とでもいおうか。そもそも3時間もの間、この音の連なりを集中して聴くことなど不可能に近いはず。わたしの場合は家にいる時間、その空間に、ただ流していた。その間、さまざまな生活音に混じって不意に音が聴こえるときもある、といった程度の聴取状況であった。
だが、それゆえ時折、聴取の遠近感が変わってしまう瞬間があった。超絶的にミニマムな響きが、さまざまな生活音の中で、不意に浮上してしまうとでもいうべきか。それは「聴こえていない」時間の中に、「聴こえる」という体験が不意に侵入してしまうような感覚でもあった。世界と音とわたくしの関係性の遠近法が崩れ、再構成される聴取体験。かつてロペスが目隠しで生み出したライヴ環境とはまったく正反対の環境・状況でもあるのだが、同時に、聴こえない音が不意に傍に来るという意味では共通する体験、ともいえるだろう。
18分のトラック“309”はヘッドフォンで集中して聴いた。このトラックもまたほとんど聴こえない瞬間がある。だが、ヘッドフォンで聴くと、耳と耳の内側そのものが快楽的に震えるのだ。そんな震動をたしかに感じることができるのだ。わたしは、その震動を「音楽」とすらはっきりと認識するだろう。震動による音楽的快楽の生成。ロペスの作品は、そのような弱い音であり、同時に、接触的な震動という強烈な音楽(そう、音楽!)を獲得している。零度の音楽/音響。
この一枚のDVDディスクには、そんなロペスの20年に及ぶ思考と実践が圧縮されている。この計7時間におよぶ音を摂取=聴取すること。聴き手は、そこから音/響の実験・実践の新たなパースペクティヴを思考/獲得することになる。その意味で、このディスクは、サウンド・アートの物質化である。そしてデータという意味ではサウンド・アートの流動化でもあるのだ。この音たちは、世界の音の群れとミックスされるだろう。そうしてロペスの実験と実践は、世界に向けて開かれていくのだ。弱い音によって生まれる音の極限。そんな環境・状況に向けて、思考と耳を大きく、自由に拓くこと。そう、まさに「聴くこと」をめぐる豊穣な思考の誘発がここにある。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE