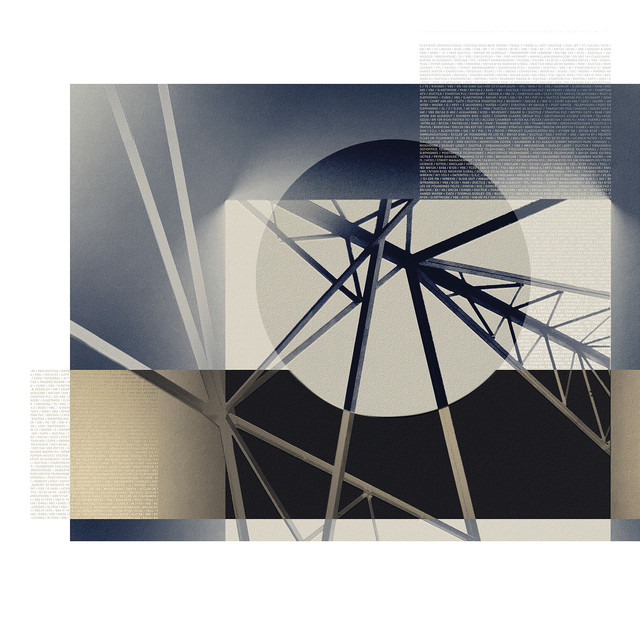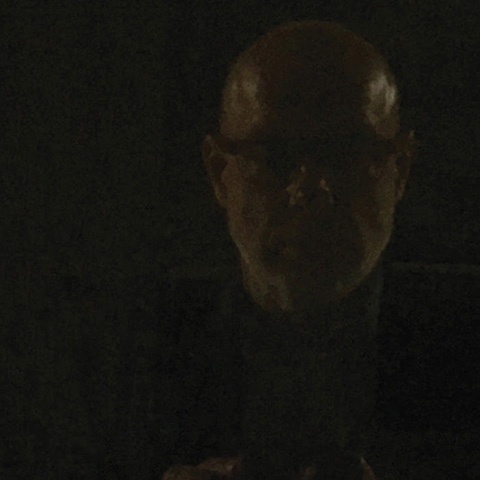MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > ENO & HYDE- Someday world

やはりブライアン・イーノから語りはじめるべきだろうか。
ブライアン・イーノは20世紀後半から現代に至るまで、ポップ・ミュージック/ロック・ミュージックの「知性」を体現する存在である。「知性」と は何か。好奇心である。彼の類稀な「知性」は、音楽を基点としつつ、アートやサイエンス、文学に至るまでさまざまな領域を、関心の広がりの赴くままに吸収 してきた。その過程でイーノは「アンビエント・ミュージック」という有名なコンセプトを生み出した。これは音楽のみならず芸術と環境を中継する概念/構造 でもある。彼の活動の中心概念は「音楽をいかにユーザーの生活=環境に溶け込ませるか」だったように思える。
イーノがアーティスティックなアンビエント作品、ストレンジなロック・ミュージック、インスタレーションの制作やソフトウェアの開発のみならず、U2、 コールドプレイなどのメジャー・バンドまでも平気で手がけ、そのどれもが成功を納めてしまうのは、彼が「ユーザーの環境=生活の中にある音楽」という概念 の実現化を実践してきたからではないか。ヒット曲もミュージック・アプリも、生活の中になるアンビエント・ミュージックである。そう、つまりは文房具のよ うな音楽。
ゆえにイーノは20世紀後半を代表する音楽家であると同時に、20世紀後半を代表する音のプロダクト・デザイナーである。
この春、かねてから話題になっていたブライアン・イーノとカール・ハイドのコラボレーション・アルバムが〈ワープ〉からリリースされた(いまさら二人の経歴を語る必要もないだろう。検索すればすぐにわかるのだから)。
ネット上でも発売前から2曲が先行トラックとして発表されており、アルバムの雰囲気は多くのリスナーが掴んでいた。事実、このアルバムを通して聴いた者 は、先行トラックの2曲がもたらしたイメージと、大きな差異がないことに安心と納得を受け取ったはずである。イーノのファンならば「さすがはブライアン・ イーノ」と安心するだろう。それほどのファンでなければ「近年のイーノ御大の音だな」などと呟くだろう。またアンダーワールド=カール・ハイドを聴いてき たリスナーならば、彼特有のヴォーカル・ラインが本作でも健在であることに喜びを感じもするだろう。
いずれにせよ、このアルバムを聴いたものは、決定的な「驚き」を感じることはない。ここにあるのは「驚き」ではなく「必然」なのだ。レコーディングの技 術的な部分や楽曲・演奏の細やかな箇所でより専門的に「驚く」ということはあるかもしれないが、一般的なリスナーにとっては、エレクトロニクスと生演奏が バランス良く交じり合った(しかし少しだけ変な)聴きやすいポップ・ミュージックである。それゆえ何度も聴けるアルバム=プロダクトに仕上がっているとい える。
そう、このアルバムの最大の肝は「驚くべきことなど何もない」というブライアン・イーノの強靭なプロダクトの品質管理の意識が、しかし管理された窮屈さに収まることなく、ある種の風通しの良さを保持している点にある。
「驚きではない」。そこから本作を考察してみよう。たとえばイーノとハイドのコラボレーションに関しても驚くには値しない。なぜなら過去のライヴ競 演やハイドのソロ・アルバム参加などを考えれば必然であった。また、イーノはU2やコールドプレイなどのメジャーなロック・バンドのプロデュースを巧みに 実践してきたベテラン・プロデューサーである。アンダーワールドというテクノ・ユニットのポップ・スターのメンバーと仕事をすることに違和感があるわけで もない。
リリース前にアナウンスされていたアフロビートの導入も、2011年のシェウン・クティのアルバムのプロデュースという直近例を挙げるまでもな く、イーノはトーキングヘッズのプロデュース時代からロック・バンドにアフリカン・リズムを一種の「モード」として取り入れてきた先駆者(の一人)であ り、やはり必然性がある。またポリリズムを駆使した本格的なアフロビートではないという点も同様だ。あくまでロックのビートを基準として一種の香水のよう にアフロビートがふりかけられているのだ。その点においてもイーノ過去作品と共通する。
そして本作においてビートルズの“トゥモロー・ネバー・ノウズ”的なメロディの楽曲が多い点も「驚き」はない。もちろんイーノ単独曲では、まるで 70年代のロック期ソロ作品のようなメロディも聴かれるが(9曲め“トゥー・アス・オール”など)、カール・ハイド(とフレッド・ギブソン)との共作“ダ ディーズ・カー”““ア・マン・ウェイク・アップ”などリズムが強調される曲においては、念仏のような“トゥモロー・ネバー・ノウズ“的なメロディにな る。なぜならこれらのヴォーカル・メロディは、モーダルな構造のトラックの上で、そのコードの基音の狭間を這うように作られているからだ。結果としてブリ ティッシュ・ロックがミニマルビート化/テクノ化したときの一種の伝統として(ケミカル・ブラザーズ)、“トゥモロー・ネバー・ノウズ“化していく。
ともあれ、このように簡単に列挙できるほど、このアルバムに「驚き」はない。そもそもイーノも(そしてハイドも)、奇想天外な「驚き」をもたらす アルバムを作ろうとは思っていなかったはずである。イーノは「イーノ・ハイド」という名義のアルバムを、プロダクトとしてほぼ完璧に仕上げた。何度も繰り 返し聴ける高品質な音源。手にする喜びのあるジャケットのアートワーク。
イーノが自身の作品の、ある種の「アート・プロダクト」化を徹底しはじめたのは、じつは〈ワープ〉移籍以降の大きな特徴だ。『スモール・クラフト・オ ン・ア・ミルク・シー』(2011)以降、ジャケットのアートワークは装丁や紙質を含め完璧である。そしてデジタル化していく現在の音楽状況のなか、フィ ジカル盤のアートワークを追求していくのは大切な仕事だ。
音楽的にも〈ワープ〉以降のイーノ作品は、風通しの良さ(イーノ特有のユルさ?)を保持しつつも、デジタル時代特有の輪郭線のクッキリしたグリッド感を 実現する精密なポスト・プロダクションを行うことで、自由と厳密さが絶妙なバランスの上に成立している。本作も同様である。
しかし、それでもなお、本作には真に驚くべき点が3つある。1つは「サウンド・プロダクト・デザイナー、ブライアン・イーノ」だけではなく、独自 のメソッドを独学で学んだ「作曲家、ブライアン・イーノ」が不意に顔を出す点だ。とくに1曲め“ザ・サテライツ”のイントロのシンセ・ブラスのフレーズ。 そこに彼の指先が生み出す独特な響きを聴き取ることができるはずである。本作には、「音楽家イーノ」の素の顔がところどころに表出している。この音楽の魅 惑的な奇妙さ。その傾向は前3作よりも強い。
2つ目は、それゆえイーノが主導権をもってアルバムを作り上げているように思える点である。65歳を迎えたこの音楽家は未だ完全に現役であり、プ ロデュースのみならず自らトラックを手がけているのだ。もちろんカール・ハイドのギターやヴォーカルは重要である。そして若き共同プロデューサー・フレッ ド・ギブソン(20歳!)、シェウン・クティのアルバムで共同プロデュースしたジョン・レイノルズの功績も大きいだろう。だが彼らの奏でる音に対して、き わめて自由に、何の先入観もなく、オトノアソビのように介入し、サウンドの生成と戯れるさまこそブライアン・イーノの真骨頂だ(それゆえイーノ単独曲“ブ ラジル3”、“セレブレーション”が収められているデラックス2CD盤のディスク2は興味深い)。
そして3つめは、ブライアン・イーノというひとりの人間の中の、ミュージック・プロダクトを巧みに作り上げるプロデューサー/サウンド・プロダク ト・デザイナーという側面と、単なるプロフェショナルに凝り固まることなく、音と遊びつづける永遠の天才的なアマチュアが、ごく自然に同居している点であ る。これが何より驚くべきことだ。だが、それこそが音楽の創作者として正しい態度とするなら、やはり「驚くに値しない」のだ。なんという円環か!
あらためて結論を述べよう。ブライアン・イーノはつねに正しい。そう、「驚くには値しないこと」こそ、本当に「驚くべきこと」なのだから。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE