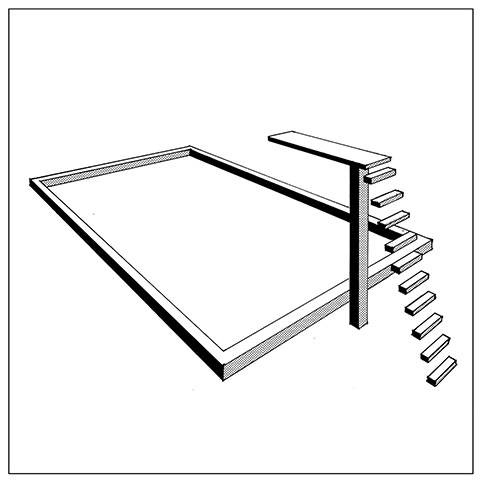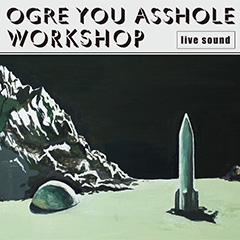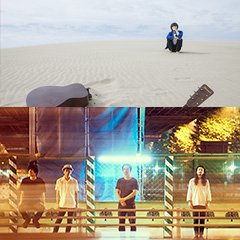MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > OGRE YOU ASSHOLE- ペーパークラフト

静かな、しかしけっして止むことのない怒りの音楽竹内正太郎
これは悪い夢なのだろうか、と思うことがある。数年前にはとても考えられなかったようなことが、いま、この国で実際に進行している。しかし、ある人にとってそれがどれほど悪夢のような世界に思えても、同時にそれは、他の誰かが夢にまで見た理想の世界でもあり得る、ということ。そして、その強烈なアイロニーを受け入れながら、同時に、徹底的な俯瞰でその全貌を描いてしまうこと。もし、そんなことをやってのけるロック・バンドがいまの日本にあるとすれば、それがオウガ・ユー・アスホールというバンドだろう。新作『ペーパークラフト』の一曲め“他人の夢”において、出戸学は「あー/ここは他人の夢の中」と歌っている。前作『100年後』で築いたあのムーディーなサイケデリアの照り返しの中で、ゆったりと、とても大らかに、まるでラヴ・ソングでも歌うような柔らかさで、彼は歌っている。
さらに、この“他人の夢”という曲は、ここ数年のライヴや、セルフ・リメイク・アルバム『confidential』の中で極まりつつあったノイズ・エクスペリメンタルな傾向からはひとまず切り離された、『ペーパークラフト』が新たに提示するある意味ではニュートラルな、それでいてポップスの常道からは逸脱したような(それこそ、詞の中で「ここにあるすべてが少しづつ変だ」と表現されているような)世界を象徴する曲でもある。とくに、1分を超える間奏パートに敷き詰められたコズミック・ギターのカーテンは、技術のひけらかしではなく、むしろ無言のままに、その雄弁な沈黙でもって聴き手の耳を圧倒するだろう。「希望や夢が一人一人を狂わせているよう」という言葉すらものみ込んで。
もし、オウガ・ユー・アスホールというバンドに不幸な点があったとすれば、転機となった意欲作『homely』のリリース・タイミングが、ゆらゆら帝国の退場とあまりにも綺麗に連動してしまったことだろう。正直に言えば、筆者もあのときに素直ではない反応を示してしまったリスナーの一人である。しかし、緩やかな韻律と、大さじの皮肉がなみなみと注がれる2曲めの“見えないルール”には、このバンドの覚悟を見い出さずにはいられない。もちろん、彼らの音楽を本当の意味で鍛え抜いたものが、仮に、3.11以降のこの国で起こったあれこれであったとすれば、僕はそれを喜んでいいのかわからない。ひとつ、確実に言えることがあるとすれば、『100年後』の一部楽曲を除いて、オウガ・ユー・アスホールの音楽でこのようなジレンマに陥ることはなかった、ということである。
その意味で言えば、この『ペーパークラフト』というアルバムの卓越した練度と問題意識は、ゆらゆら帝国の『空洞です』の完成をもって一度は放棄されてしまった日本語ロックのその後の可能性と(2010年の解散声明に「結局、『空洞です』の先にあるものを見つけられなかったということに尽きると思います。ゆらゆら帝国は完全に出来上がってしまったと感じました」と記されたショックを僕はいまでも忘れられない)、ceroの『My Lost City』という作品、とくに“わたしのすがた”に刻印された震災後の日本への真摯な問題意識を堂々と引き受けるものと言えるだろう。どう聴いても流行りの音楽ではない。優しい言葉のひとつもない。が、孤独は慰め合うものではないということを、この音楽は教えてくれる。
もちろん、『ペーパークラフト』は単なる生真面目さに縛られた作品というのでもない。“いつかの旅行”に見られるインディ・プログレ(?)とでも言うべき、まるでレトロなSF映画のSEをサンプリングしたようなプロダクションには豊かな遊び心が、また、いわゆるロックのイディオムからは遠く離れた、“ムダがないって素晴らしい”で乱舞するパーカッシヴなリズム・プロダクションには、忍耐強いリズムの探究がある。レコーディングのクレジット欄には、それを実現可能にしたアナログのヴィンテージ機材の数々が、記載しきれないほど列挙されている(“誰もいない”に吹き込まれるサックスの、あの叙情的な響きときたら!)。たとえば、とりあえず音圧上げて4つ打ち、というふうに、「敷居を下げることがポップである」と誤解されつづけているこの国で、彼らの試みがより多くの驚きを集めることを願う。
言葉の面で言えば、タイトル・トラックである“ペーパークラフト”が決定的だろう。もちろん、前提として断っておけば、彼らのメタフォリカルな言葉はいまでも一定の抽象性を守っているし、本稿に記されているのはあくまでひとつの解釈に過ぎない。だが、それでも、本作での言葉がこれまでにない強度を備えているのは気のせいではないと思う。あの震災を受けて、「これで日本もよい方向に変わっていくかもしれない」という一時的な希望を持ってしまった私たちの、皮肉めいたその後を描いたのが“他人の夢”だとすれば、他方では、ハリボテの街での生活もそう簡単にはやめられない、その意味では誰しもがある意味では共犯者なんだ、というパラドキシカルな意識がこの曲、ひいては『ペーパークラフト』全体に通底しているようにも思える。しかも、そのような複雑さを伴う作業を、彼らは極限までシェイプされた言葉でやってのけるのだから!
とはいえ、なにも僕は、「ロックとは何か/どうあるべきか」というウンザリするような定義戦争を仕掛けたいわけではない。が、この作品は、そんな徒労にもう一度だけ首を突っ込んでみたくなるような誘惑に満ちている。たしかに、僕たちは世界を変えることができないかもしれないし、世界も僕たちを変えることができないかもしれない。だが、あなたが好むと好まざるとに関わらず、世界を変えようとしてしまう人たちがどんなときにも存在する、ということは思い出すべきだろう。気づけば他人の夢の中で踊らされてる、なんてことになる前に。
少し大きな話になってしまうが、イマココの現実を相対化するために、「あり得たはずのもう一つの現実」を生み出すフィクションの力を、この国においてもサイケデリック・ロックが担ってきたのだとすれば、人々が暮らす街をひとつの霊廟として、しかも紙作りの霊廟として見てしまう『ペーパークラフト』の超然とした想像力は、トリップしながらも覚めている。それも凶暴なまでに。それは単なる厭世ではないだろう。そう、これは静かな、しかしけっして止むことのない怒りの音楽である。ある種の文学と、ロックという表現の可能性をいまでも信じる人に、どうか届いてほしいと思う。
竹内正太郎
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE