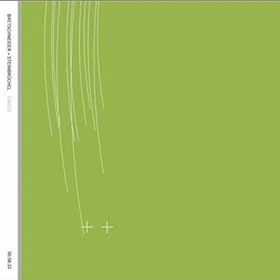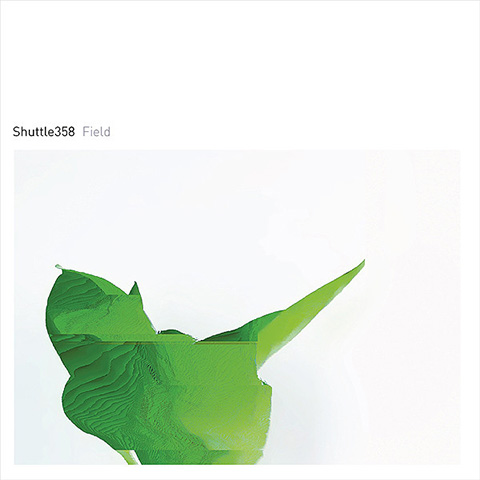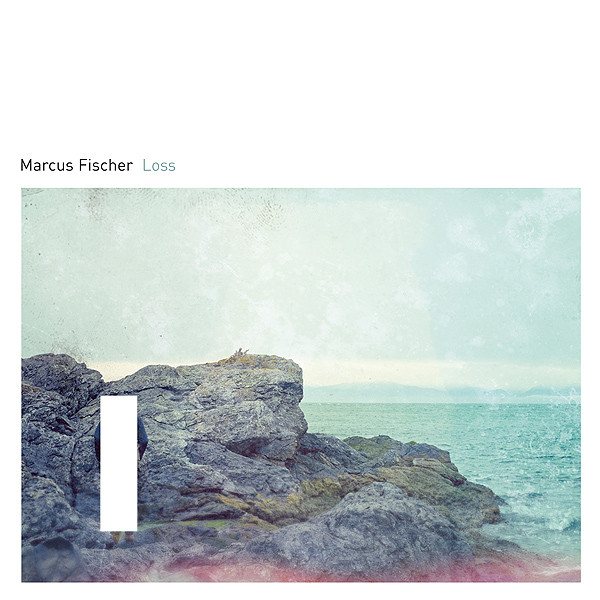MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Steinbrüchel- Parallel Landscapes

シュタインブリュッヘル待望の新作だ。しかも〈12k〉から初のアルバムである。その音の線、音の粒、音の空間、音の環境。粉雪のような電子音響。雪の情景のようなランド・スケープ/サウンド・スケープ。それはマシンによって生成するもう一つの自然環境のように……。まったくもって素晴らしい。
ラルフ・シュタインブリュッヘルは1969年生まれ、ドイツ出身・スイス在住のサウンド・アーティストである。その電子音響によるサウンド・パターンをレイヤーしていく作風は、2000年代初頭の電子音響/エレクトロニカの特徴をよく表している。私は彼をその時代を代表するサウンド・アーティストと思っていた。事実、シュタインブリュッヘルは、2000年代初頭に〈ライン〉〈カット〉〈アタック〉〈ルーム40〉〈アンド/OAR〉〈12k〉などの名だたる電子音響及びサウンド・アート・レーベルからアルバムやEPを多数、リリースをしていたのだから。
まず、1996年に自主レーベル〈ストックヴェルク〉から最初のアルバム『ストックヴェルク』を発表する。つづいて2000年から2004年あたりにかけて自主レーベル〈シンクロン〉でおもにライヴ録音作品などを送り出す。2003年にリチャード・シャルティエのレーベル〈ライン〉から『キルカ』をリリースし、2006年に『ステージ』を発表する。2004年には、〈アタック〉からキム・カスコーン、ジェイソン・カーンらとの作品『ATAK004』をリリース。2005年には〈ルーム40〉からベン・フロスト、テイラー・デュプリー、オーレン・アンバーチ、角田俊也らと『オペーク』、〈12k〉からフランク・ブレットシュナイダーとの『ステイタス』、2006年には〈リスト〉から、ギュンター・ミュラーとの『パースペクティプス』をリリースしている。
そして、2008年に〈12k〉からEP『ミット・オーネ』を発表する。折り重なる電子音の粒と線が、互いに無関係のまま運動の層をなしつつ、しかし、ひとつの音楽/音響として、結晶のように生成していく。「サウンド・パターンの多層レイヤー的配置による超ミニマルな音響作品」という2000年代エレクトロニカ/電子音響の特質を18分の中に凝縮しているのだ。これは傑作である(近年も2011年に〈ルーム40〉リリースの『ナロウ』をはじめ、〈クワイエット・デザイン〉や〈テープワーム〉などからCDやカセット作品を発表している)。
また彼は、グラフィック・デザイナーでもあり(むしろそちらが「本職」だろう)、端正なミニマリズムをクライアント・ワークのデザインに見事に落とし込む優秀なアート・ディレクター/デザイナーだ。〈ビネ・ミュージック〉諸作品のアートワークを手がけており、こちらの作品も素晴らしいものだ。デザインに共通するテイストは、清潔なミニマリズム。それは彼の音楽作品にも共通するし、同時に、2000年代初頭の電子音響/エレクトロニカの空気にも共通するものである。モダン・グリッド・レイヤー・ミニマリズム。
2000年代の電子音響は、そのような「新しいモダニズムを用いた環境音楽」であったと、いまならば思う。アートや建築などの概念を取り込みつつ、具体的な音響によってそれを示した。2000年代初期(以降)の電子音響/エレクトロニカが、サウンド・アートと密接な関係を取り結んでいた理由はそこにある。いわば、ブライアン・イーノの提唱したアンビエント・ミュージックという空間的/抽象的な概念を、テクノロジーとサウンドとデザインによって音響彫刻化し、録音、音盤を含めたサウンド・アートとして実現したのだ。
そこにおいてラップトップなど、コンピューター上で音響を生成可能なテクノロジーが大きく貢献したのは間違いない。この時期以降、音響生成は、作曲からデザイン的なものへと変化を遂げた。ゆえにシュタインブリュッヘルがグラフィック・デザイナーであるというのも非常に納得できるのである。
そして、これらが一定の成果を経た2000年代後半以降、すべてが溶け合うドローン/アンビエントへと変化したことは、(これもいまにして思えば)当然の変化でもあった。現在のインダストリアル・ムーヴメントもポスト・クラシカルの流行も、2000年代後半に起きたドローン/アンビエント・ムーヴメントの延長線上にある。モダンなレイヤー/グリッド性に対して、アンフォルメルな融解性への回帰でもあった。いわば「抑圧されたものの回帰」だ。ドローンやノイズへの感性はこの数年で多くのリスナーに深く浸透した。時代の無意識を象徴していたからだろう。
以降、最先端の音楽/音響は、グリッチ、ノイズ、ドローン、グリッド、レイヤー、コンポジション、ミュージック・コンクレート、現代音楽、インプロヴィゼーション、デザイン、モダン、ポスト・モダン、アンチ・モダン、アンフォルメルなどを包括しつつ、芸術の歴史を高速にスキャンする傾向が強まる気がする。すでにその傾向は、〈パン〉などのリリース作品に表れつつある。
そのような状況の中、私は、近過去であり、近年の電子音響作品の大きな転換点であった2000年代初頭の電子音響やエレクトロニカを総括してみるのも悪いことではないと思っていた。その矢先、シュタインブリュッヘルの新譜『パラレル・ランドスケープ』がリリースされたのである。『パラレル・ランドスケープ』は、EP『ミット・オーネ』のサウンド・パターン/レイヤーによるミニマリズムを引き継ぎつつも、微かで不確定なノイズ的な音響やドローンなども導入されており、2000年代後半の状況も経由して生まれたことは明白である。2000年代初頭な音響と、2010年代初頭的なサウンドの交錯。
その緻密にして繊細なサウンドは、まさに真冬の電子音響、とでも形容したくなる出来栄えである。粉雪のように冷たい音の粒が、線が、清潔な音響空間の中で降ってくる感覚。徹底的にマシニックな音なのに、どこか不思議な情感もある。まるで深夜に降り積もる雪の結晶のようなサウンドなのだ。
本作において、シュタインブリュッヘルの音は、近年の〈12k〉的なドローン/アンビエントを引き継ぎつつも、クールなマシンの叙情を交錯させている。ひとことでいえば、これまでより、かなり「音楽的」になっている。とはいえリズムやハーモニーなどの要素はほぼ皆無で、サウンドのレイヤーと運動性がより複雑かつ繊細になっているから、結果として音楽的に聴こえるのであろう。彼の手法はそう変わっていない。これが重要だ。つまり、マシニックなサウンド・パターンの方法論そのままに「音楽」が生成しているのだ(また、本作の元になった素材は、近年のライヴ・パフォーマンスで用いられてきたものらしいので、本作特有の「音楽的な柔らかさ」は、もしかすると目の前にいる聴衆の存在を意識したものだからかもしれない)。
シュタインブリュッヘルは最近のインタヴューで「私にとって音楽とは、空間内における3次元オーディオベースの彫刻のようなものです」と語っているが、これは電子音響やエレクトロニカが、2000年代後半以降ドローン/アンビエント化し「過度に音楽化」していったときに消えてしまった環境論的な思考である。この作品は、デザインされた音のレイヤーの複雑なコンポジションによって、過度に音楽的にならずに一種のムードを生み出すことに成功しているのである。つまりサウンドのレイヤーによって「音楽」をデザインしているのだ。私には、何よりその点に、とても驚いた。
本作はアートワークも素晴らしい。スリップケースの中に、CDとそれを収めるジャケットとともに、60ページに及ぶ冊子が封入されている。このブックレットは、テイラー・デュプリー撮影による冬の情景を捉えた美しい写真、ローレンス・イングリッシュのエッセイ、シュタインブリュッヘルによるミニマルなアートワークによって成り立っており、それらが糸によって製本されている。じつに丁寧に作られた本だ。このブックレットを手にしながら音を聴く経験は、もっとも原始的なサウンドインスタレーション体験ともいえよう。本作は「耳で聴く」ことのみならず、「手で触れる」ことを主題とした「サウンド・アート」だ。できる限りデータではなく、フィジカル盤を入手して聴くべきアルバムである。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE