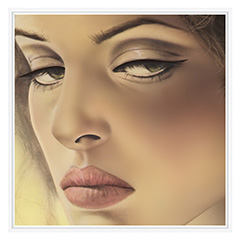MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 石野卓球- LUNATIQUE
そう、いよいよ90年代が始まる。1993年のYMO再生(実質上、テクノポップの終焉)から、そして『テクノボン』を経由して1995年までのおよそ2年間は、「90年代」というディケイドにおける重要なモード・チェンジの時期だったと思う。その象徴のひとつが、1995年の『Dove Loves Dub』だった。「電気グルーヴの石野卓球」ではなく「テクノ・プロデューサー、石野卓球」としての最初の作品である。
大友克洋のアートワークがもたらす相乗効果も大きかった。これは、同年リリースのケンイシイ『Jelly Tones』(当然、森本晃司監督による「EXTRA」MVのCD-ROM付きの初回盤)とともに、アンダーグラウンドなテクノがいままさにポップ・カルチャーの最先端にまで勢いをのばしているのだという、あの頃の高揚感へと繫がった。ジャンルが現在のように細分化される以前の、混沌としているがゆえのテクノの魅力とでもいうべきものがあった。電気のボックスセットからバラ売りするというカタチ(そうでもしなければ、テクノのソロ作品をメジャーで出すことは不可能だった)で同時リリースされた『Dove Loves Dub』と砂原良徳『Crossover』は、ある種の時代精神(!)のなか、聴き狂ったものだった。私は、電気と同じくらい熱心に卓球とまりんのソロを聴いた。
インダストリアルな魅力も兼ね備えたほど多彩な内容の『Dove Loves Dub』以降では、それとは対照的に渋いハード・ミニマル・テクノを打ち鳴らす1998年の『Berlin Trax』が好きだったけれど、それを言ったら2004年の「Title」シリーズ、2010年の『CRUISE』などゼロ年代の諸作品も忘れるわけにはいかなくなる。基本的にポップなイメージで見られる石野卓球だが、しかしソロで見せる音楽性はまったくのアンダーグラウンドで、ある意味ディープで、しかも素晴らしく洗練されているのだ。
そして、『CRUISE』から約6年ぶりに新作『LUNATIQUE』は、たしかな経験とスキルに裏打ちされた、まさに大人のテクノ/ダンス・ミュージックと呼ぶに相応しい仕上がりだ。何回も聴けば聴くほど新たな発見がある。心地良く、ビートも音色もメロディもシーケンスもベースも、すべてのパートがそれぞれ自然と体内に染み入ってくるようだ。あるトーンが持続し、反復し、展開し、グルーヴの低熱のようなものが入ってくる。まさに身体に「効く」音楽!
エロティシズムが主題だと言うが、全編にうごめく柔らかい音色は、たしかに官能的だ。ニュー・オーダーも影響を受けているイタロ・ディスコ的なセンスも伺える。たとえば“Fana-Tekk“や“Crescent Moon”など、かなり中毒性が高いトラックだが、しかし、それにしても、なぜこんなに気持ち良いのだろうか……。
冒頭の“Rapt In Fantasy”からしてそうだが、シーケンス・フレーズとビート、パーカッションとベースなど、ジャスト一歩手前の微妙なズレを伴っている。そのズレが独特のグルーヴを生み、さらにアルバム全編を通して伸縮するような大きなグルーヴを生んでいる。電子音なのにウネウネとして生っぽいのである。
“Fetish”も最高だ。水のような持続音、シルキーなシンセ、断続的に散らばるビートと、伸縮するベースなど、まさに官能と快楽だ。また、“Die Boten Vom Mond”や“Selene”などのアンビエントなシンセとミニマルなリズムとの重なりを聴いていると、ふと90年代のレーベル〈クリア〉の諸作品(モーガン・ガイストなど)を思い出してしまった。要するに、聴く場所を選ばない、ダンスとリスニングとのバランスがじつに良いのだ。
もっとも本作は、マニアだけを相手にするアルバムではない。『LUNATIQUE』はポップでもある。YMOのファーストやセカンドにあったポップ・センスをも彷彿させる。何と言ってもメロディが残る。宇川直宏による官能テクノ雑誌のようなアートワークも、本作のポップ感を見事に象徴している。ぜひ特殊仕様の初回盤を手にとってほしい(完売してしまったかもしれないが……)。『Throbbing Disco Cat』(1999)に匹敵する名ジャケだ。
そう、彼はいつどんなときだってユーモアを込める。つまり6年ぶりのこのアルバムは、粋なのだ。大人テクノの粋! 90年代の自分に教えてあげたいほどの力作である。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE