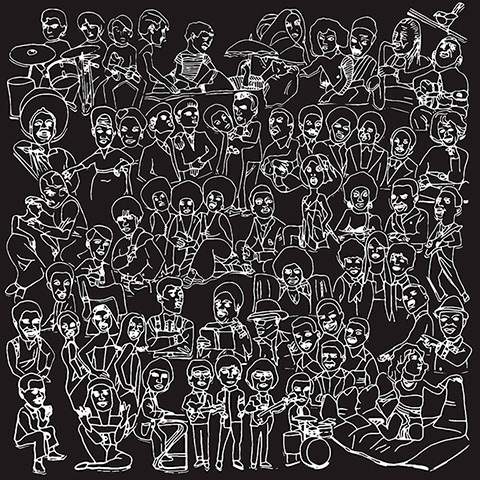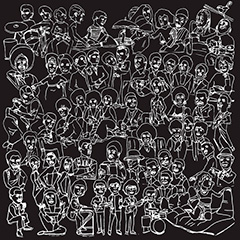MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Romare- Love Songs: Part Two
古今東西、さまざまなアーティストが「愛」をテーマにしたアルバムを作ってきた。マーヴィン・ゲイ、プリンス、セルジュ・ゲンズブール……。ロメアーことアーチー・フェアハーストの『ラヴ・ソングス:パート2』も、そんな「愛」のアルバムだ。曲名や歌詞(だいたいがサンプリングによる引用である)のそこかしこに「愛」という言葉やメッセージが溢れ、ブラックネスに富む前作とは異なる甘美なムードが流れている。ファースト・アルバムであった前作『プロジェクションズ』は、ニーナ・シモンの曲や黒人霊歌はじめ、ジャズやブルースなどをモチーフとし、それは否が応でもアフロ・アメリカンのアイデンティティを想起させていた。ただし、ロメアーはアメリカの黒人ではなくイギリスの白人プロデューサーで、そうしたアフロ・アメリカニズムをあくまで素材のひとつとして用いていた。だから、『ラヴ・ソングス:パート2』における変容も、そうした素材の変化があれば当然だろう(もちろん、『プロジェクションズ』でのアプローチを本作でも延長している部分はある)。
本作での素材として、ディスコなどからのサンプリングが挙げられる。ディスコの多くは「愛」をテーマにしているし、いろいろな人種や性が「愛」を求めて集まるところなので、そうしたアプローチとなるのも頷ける。ロメアー自身はネタを公表していないが、“フー・トゥ・ラヴ?”とかは明らかにドナ・サマーの“ラヴ・トゥ・ラヴ・ユー・ベイビー”が原型となっている(ロメアー本人はインタヴューで、ジミ・ヘンドリックスと彼のガールフレンドについての関係性を描いたと述べているが)。“オール・ナイト”とは、もちろんディスコの夜。ノーマン・ホイットフィールドが手掛けたテンプテーションズあたりを参考に、ファンクにブラック・サイケを加えたような味付けだ。“フー・ラヴズ・ユー?”もディスコに直結するムードを持ち、『ラヴ・ソングス:パート2』においてもっとも黒いフィーリングを感じさせ、『プロジェクションズ』の世界観を発展させた痕が窺える。“ジュ・テーム”からは、言うまでもなくセルジュ・ゲンズブールの影がチラつくが、作品自体はロメアーお得意のコラージュ調ナンバー。一方、“ハニー”は『プロジェクションズ』との違いを明らかにするようなエレクトロニカで、ロメアーの繊細なロマンティシズムが露わになっている。“カム・クロース・トゥ・ミー”も同様で、ディープ・ハウス調の曲ながら、『プロジェクションズ』でのムーディーマンに通じるゲットー・ハウス的なスタイルとは異なるものとなっている。“ニュー・ラヴ”はテクノやトランスのスタイルを取り込んだと語っている。リル・ルイスの“フレンチ・キッス”的なラヴ・ソングへのアプローチだろうか。“ドント・ストップ”での摩訶不思議なエキゾティシズムも面白いし、“L.U.V.”での楽園的なムードはバレアリックに通じる。なお、本作は『プロジェクションズ』ほどサンプリングに頼っておらず、そのぶん生楽器の演奏の比重を増やしたそうだ。単音のシンセにはじまり、祖母のリコーダーから父親のマンドリンまで演奏しているようで、“マイ・ラスト・アフェア”はそうした演奏に重きを置いた楽曲である。
インタヴューではアフロ・アメリカンの音楽や歴史から、ブリティッシュ・フォーク、アイリッシュ・フォークなどからヨーロッパの歴史へ興味が移行し、それが『ラヴ・ソングス:パート2』へ繋がっていると述べていたロメアー。一聴しただけではフォーク・ソングの具体的な痕跡はわからなかったが、強いブラック・アフリカニズムに彩られた『プロジェクションズ』から、『ラヴ・ソングス:パート2』という新たな世界へ移動してきたことは確かだ。そして、彼は思いつくままにいろいろと興味の対象を広げ、多くの影響を受ける人間のようである。コラージュという手法もそうした多くの影響からくるものであり、そこがロメアー・ベアーデンというコラージュ・アート作家の名前を冠するアーチー・フェアハーストらしさかもしれない。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE