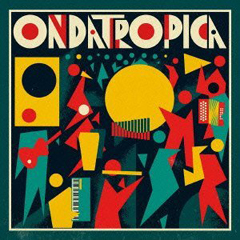MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > The Mauskovic Dance Band- The Mauskovic Dance Band
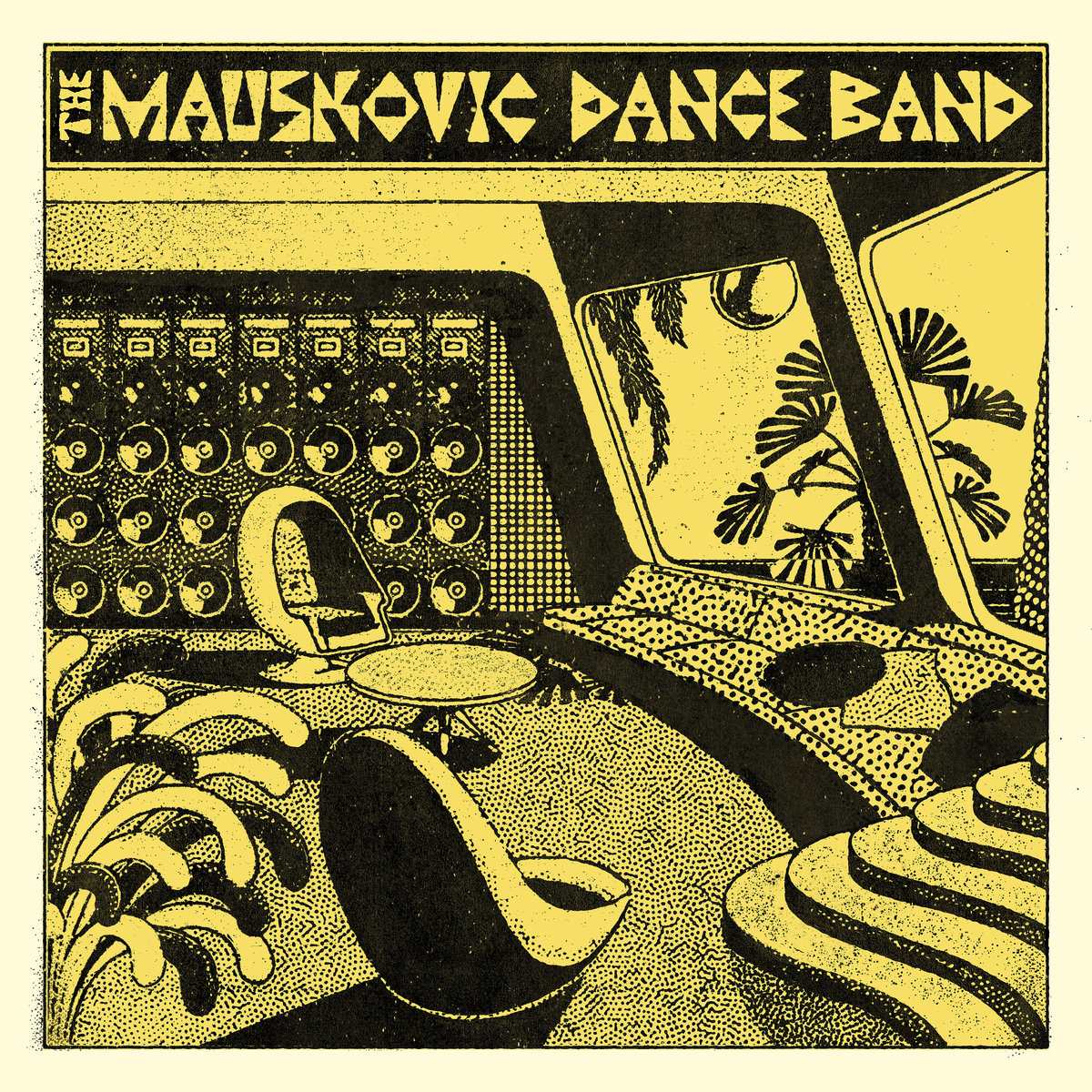
かつて1950年代から1960年代にかけて、ダンスホールやクラブには専属のバンドやオーケストラがいて、その頃のダンス音楽の主流であるラテンやアフロ・キューバンの生演奏を繰り広げる時代があった。その後1970年代に入り、ダンスホールはディスコティークに取って替わられて、バンドの役割も次第にDJへと変換していくわけだが、当時のディスコ時代でもMFSBやサルソウル・オーケストラなどはそうしたダンス・バンドの系譜を受け継ぐ存在で、バンドからDJカルチャーへの橋渡しをおこなった。ヨーロッパにおいても同様で、1950年代から1970年代にかけては多くのラテン・バンドが存在していた。ベルギーやオランダではニコ・ゴメス楽団、チャカチャス、エル・チックルズ、ショコラッツといったグループが活動していて、チャカチャスの“ジャングル・フィーヴァー”はムード・ラテンにディスコを取り入れた最初の例として世界中で大ヒットした。ベルギーとフランスの混成バンドのショコラッツは、セローンやドン・レイがいたコンガスと共にアフロ/ラテン~トロピカル・ディスコを確立した。オランダを拠点とするニック・マウスコヴィッチ率いるダンス・バンドは、それらかつてのラテン・ディスコ・バンドの現代版と言える存在だ。
ニック・マウスコヴィッチはアムステルダムで活動するマルチ・ミュージシャン/プロデューサーで、トルコ系のミュージシャンたちによるサイケ/フォーク・バンドのアルティン・ガンに参加する一方で、マルチ・ミュージシャンのジャコ・ガードナーとニューウェイヴ/バレアリック・ディスコ・ユニットのブラクサスを組んでいる。そんなニックによる5人組ダンス・バンドは、彼の兄弟のチョコレート・スペース・ドニー(キーボード、エフェクト)、マーニックス(ギター、シンセ、パーカッション)、マノ(ベース)が中心となり、そこにクンビア・ミュージシャンのフアン・ハンドレッド(ドラムス)が加わっている。2017年にデビューしてスイスのレーベル〈ボンゴ・ジョー〉からシングルを2枚リリースし、その後2018年にアフロやカリビアンなどワールド・ミュージック/辺境音楽系に強いUKの〈サウンドウェイ〉から「ダウン・イン・ザ・ベースメント」というEPをリリース。この中の“コンティニュー・ザ・ファン(スペース・ヴァージョン)”という曲がジャイルス・ピーターソンのコンピ『ブラウンズウッド・バブラーズ・13』に収録され、彼の催す「ワールドワイド・アワーズ・2018」の“トラック・オブ・ザ・イヤー”にノミネートされるなどして注目を集める。そして7インチの“シングス・トゥ・ドゥ”を経て、ファースト・アルバムとなる本作を〈サウンドウェイ〉からリリースという流れとなる。アムステルダムのスタジオで録音された本作は、現在ポルトガルのリズボン在住のジャコ・ガードナーによってミックスされた。
ザ・マウスコヴィッチ・ダンス・バンドのサウンドは、直接的には1980年代前半頃のアフロやラテン・ジャズと結びついたオルタナティヴ・ディスコやエレクトロ、ポストパンク~ニューウェイヴ・ディスコの中でも特にパーカッシヴでトライバルなサウンド、あるいはファンクとラテンが結びついたファンカラティーナなどの影響が強い。具体名を挙げればUSならアーサー・ラッセルによるダイナソー・Lやインディアン・オーシャン、オーガスト・ダーネルによるキッド・クレオール&ザ・ココナッツやサヴァンナ・バンド、リキッド・リキッド、コンク、ワズ・ノット・ワズ、UKならファンカポリタン、モダン・ロマンス、ブルー・ロンド・ア・ラ・ターク、ファンボーイ・スリー、ピッグバッグ、リップ・リグ&パニックなどだろうか。彼らのサウンドに共通するのは、どこか特定の国の本格的な民族音楽に倣うのではなく、世界の様々な民族音楽や辺境音楽をゴチャ混ぜにしたような無国籍感が漂うもので、ある意味で本場のサウンドではない偽物ならではの怪しさが漂うものだった(さらにそれらの源にあるのは、マーティン・デニーやレス・バクスターなど1950~60年代のエキゾティック・サウンドだろう)。
ザ・マウスコヴィッチ・ダンス・バンドもそうしたB級感覚を継承していて、それこそがダンス・バンドといういかがわしい存在を体現している。チープなドラムマシーンやアナログ・シンセにキーを外したヴォーカルがフィーチャーされる“ドリンクス・バイ・ザ・シー”や“セイム・ヘッズ”がまさにそうで、1980年代のレトロ感満載のサウンドだ。性急なビートの“スペース・ドラム・マシーン”やファンカラティーナ調の“ダンス・プレイス・ガレージ”は、パラダイス・ガレージでラリー・レヴァンがプレイしていたようなアンダーグラウンド感一杯のもの。“パーカッション・アンド・スパジオ・サウンズ”は文字通りマッドでコズミックなパーカッション・トラック。スティールパンのようなパーカッションの音色が印象的な“アルト・イン・ヴァカンザ”では、このバンドにとってダビーなテイストも重要な要素であることを示していいて、“レイト・ナイト・ピープル”や“イッツ・ザ・ロング・グッディ”にもそうしたディスコ・ダブの要素が表われている。レトロなラテン・バンド・スタイルを下敷きにしつつ、ニューウェイヴ・ディスコやディスコ・ダブの要素を交えて現代的にアップデートさせた彼らは、2010年代以降のヴェイパーウェイヴの流れの中にも位置づけられる存在と言えるだろう。
小川充
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE