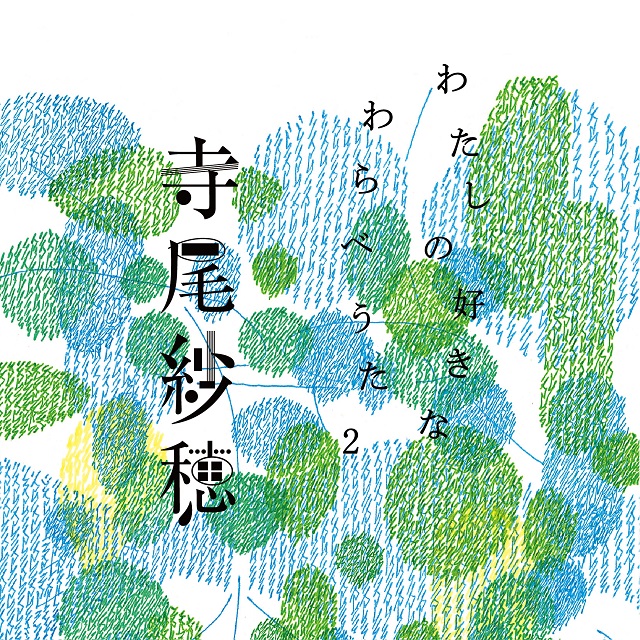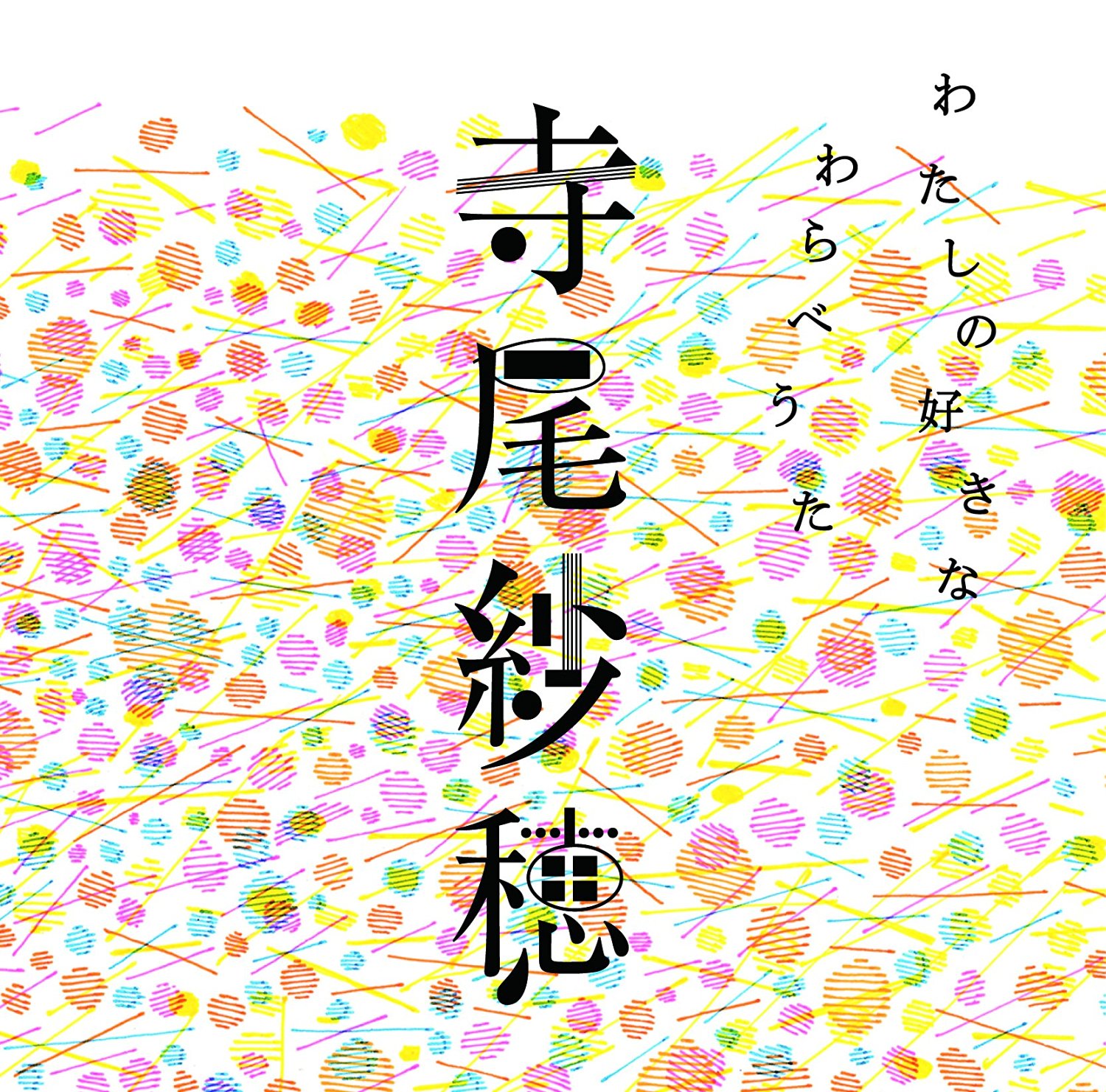MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > 寺尾紗穂- 余白のメロディ
震天動地の要人暗殺事件ですっかり話題に上らなくなってしまったが、先の参院選では音楽業界の4団体が特定の政党候補者への支援を表明するという、こちらもまた前代未聞の事態が起こり、当の音楽関係者による抗議声明をはじめ数多くの人びとから批判が集まった。それであらためて「音楽と政治」に関する議論も浮上した。ここでは深入りしないが、そしてくだんの問題とはやや論点が異なるが、政治を美学化するための道具として音楽を利用することの大きな問題点のひとつは、音楽が特定の役割、それも暴力装置としての役割を果たすためにあらかじめ決められた目的に沿って聴かれることへと向かってしまうことにある。象徴的な事例が軍歌だ。人びとは軍歌を歌うことで自らを鼓舞し戦争という目的へと向かって突き進む。注意するべきなのは何も軍歌だけにそのような力があるわけでなく、感情を動かし身体を揺さぶる音楽それ自体にそもそもそのような力が備わっているのであって、ひとたび目的を課せられれば軍歌であろうと流行歌であろうとポップスであろうと人びとを戦争へと駆り立てるための有用な手段となる。そして目的に沿って方向づけられた音楽を余白を欠いた音楽と言い換えるなら、その力の危うさを見定めるためにわたしたちはあらためて音楽の余白に耳を傾ける必要があるとも言える。
シンガーソングライターの寺尾紗穂による通算10作目にして2年ぶりとなるオリジナル・アルバム『余白のメロディ』がリリースされた。タイトルだけでなく作品それ自体の内容としても特定の目的や役割を持たない余白にスポットが当てられているように感じた。アルバムはカヴァー曲を除き全て寺尾による作曲だが、まずピアノの弾き語りをホーンとストリングスが彩る松井一平作詞の “灰のうた” で幕を開けると、続く MC.sirafu 作詞の “良い帰結(Good End)” ではヴォイスの多重録音やエレクトリック・ピアノも駆使しながら軽快なサウンドを聴かせる。3曲目 “確かなことはなにも” は寺尾が作詞作曲、ユニット「冬にわかれて」と同じく伊賀航(ベース)、あだち麗三郎(ドラム)とのトリオ編成で、4曲目 “ニセアカシアの木の下で” も寺尾の作詞作曲だがこちらは Mom のリズム・トラックと編曲が他の楽曲と比べて一風変わった雰囲気を醸している。そして野太いベースラインが印象的な5曲目 “期待などすてて” は再び松井一平作詞で、「冬にわかれて」のメンバーに加えてアルトフルートで池田若菜が客演。
ここまで聴き進めて、多数のミュージシャンが参加し、コラボレーション色の濃い楽曲の数々は、ヴァリエーションに富んでいるとも、一見するとまとまりに欠けるようにも聴こえるがしかし、後半5曲を通じて一気にアルバムは深化する。カヴァー曲の6曲目 “森の小径” はこのアルバムの重要曲のひとつだ。太平洋戦争前夜、すでに日中戦争の戦時下だった1940年に佐伯孝夫が作詞、灰田有紀彦が作曲し、有紀彦の弟・灰田勝彦が歌った “森の小径” は、勇ましい軍歌で溢れていた当時としては異色と言っていい、感傷的な歌詞をハワイアン調のスライド・ギターとシャッフル・ビートに乗せて歌う楽曲だった。だが特攻隊として戦地に赴く若者たちはそんな “森の小径” を愛唱したのだという。あまりに悲痛だ。その悲しさを受け継ぐように寺尾紗穂は奥行きのある音像で情感豊かにピアノを奏でつつ透き通るような声で歌う。間奏にはベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番「悲愴」を挿入するというアレンジだが、その意味は説明するまでもない。あたかも1曲目 “灰のうた” が、灰田兄弟の楽曲の伏線となっているかのようでもある。
“森の小径” のカヴァーでアルバムの雰囲気が少しばかり変化すると、残る4曲にそのまま耳が惹きつけられていってしまう。7曲目 “光のたましい” では一部にプリパレーションを施したピアノがいびつなノイズを微かに響かせながら、気づけば1曲目 “灰のうた” と同じ音型をピアノが踏襲しつつ、聴き手を優しく包み込むような歌声をじっくりと聴かせる。そして8曲目 “僕の片割れ” でもやはりピアノが同じ音型を繰り返し、中盤からは寺尾の歌とピアノが、客演した池田若菜の音が空間に滲み出すようなフルートと絡み合いともに歩む。9曲目 “歌の生まれる場所” では「冬にわかれて」のトリオにホーン・セクションが加わり、ポリリズミックなシャッフル・ビートからサビではゆったりと引き伸ばされ壮大に彩られた歌を歌う。しかし歌の生まれる場所とはどこか──その答えがおそらく次の、アルバムを締め括るカヴァー曲 “Glory Hallelujah” だ。西岡恭蔵のこの楽曲と出会い、そして初のワンマン・ライヴでカヴァーしたことが、寺尾の音楽活動のひとつの出発点となったのだった。ここから彼女の歌は生まれた。
いわばアルバム全体を通じて、わたしたちは寺尾紗穂の声とともに彼女の歌が生まれる場所へと遡行していく。前半の楽曲群がコラボレート色が濃くヴァリエーションに富んでいるのは、歌の発生から分化した先にある多様な現在地をまずは並べているのだと受け取ることもできる。それらは “Glory Hallelujah” とは似ていないが、ゲスト・ミュージシャンのひとり池田若菜がファースト・フル・アルバム『Repeat After Me (2018-2021)』で示したように、様々な記憶と混じり合い全く別の形に変化した歌の数々として、“Glory Hallelujah” を何かしら受け継いでいるのかもしれない。歌は言葉とメロディをそのまま辿り直すこと以上に、人間の個別的な経験を通じてつねに変化し得る生き物のような存在でもあるところに代え難いリアリティを宿す。そしてそこには様々な方向へと開かれた余白がある。寺尾紗穂は著書『天使日記』の中で、以前ライヴで “森の小径” を歌ったときのことを振り返りながら「世の中に軍歌があふれても、人の心の色まで染め上げることはできなかったと思う」とこの曲について記していた。それは激動の時代にいくばくかの希望を見せてくれる。人の心が染まらないのはすなわち感情に余白があるからだ。反対に余白を失い、ひとつの方向へと感情が方向づけられたとき、人の心は「軍歌」──それは「流行歌」あるいは「ポップス」で置き換えることもできる──で恐ろしくも単色に染め上げられてしまう。歌の生まれる場所、様々な方向へと開かれた場所に遡行していく『余白のメロディ』は、“森の小径” がそうであったように、こわばりゆく感情を解きほぐす希望の余白を響かせている。
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE