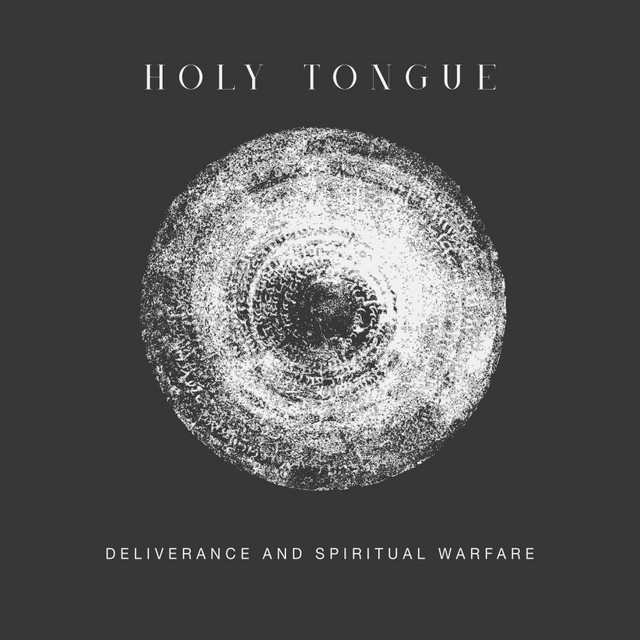MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Holy Tongue- Deliverance And Spiritual Warfar…
少し前の作品になってしまいましたが……こちらはUKのベース・ミュージック・シーンにおいてオリジナリティあふれる作品をリリースしてきたアル・ウートンが、パーカッショニスト、ヴァレンティーナ・マガレッティとともにスタートさせたホーリー・タン、その待望のファーストLP『Deliverance And Spiritual Warfare』です。本作のレコーディングでは、ヴァレンティーナも在籍するロンドンのサイケ・ロック・バンド、ヴァニシング・ツインのベーシストで、2000年代にはディスコ・パンク・バンド、ゾンガミンでも活躍していたムカイススムが現在はベーシストで参加し、3人体制へと発展しています(ムカイは、すでに2021年のライヴには参加していてその模様は彼らのカセット・アーカイヴ『Live at Servant Jazz Quarters』に収録)。ムカイのベースの他に、アルもシンセなど鍵盤の他にベース/ダブル・ベースを演奏、ヴァレンティーナはドラム、パーカッションの他に鉄/木琴とマレット系の楽器なども担当、そしてプロデュースはアルによるもの。これまでに2020年のシングル「Holy Tongue」を皮切りに、「II」「III」と3枚の12インチ・シングルを発表、ポスト・パンク的なヒリついた音像の、ミニマルかつインダストリアルなサイケデリック・ダブ/ファンク・サウンドで注目を集め、アルの、個人名義やレーベルでのベース・ミュージック・シーンでの活躍っぷりも重なりつつ、UKのある種伝統とも言えるダブ・サウンドの新たな発露として注目されているアルバムと言えるのではないでしょうか。
アル・ウートンは2010年前後、デッドボーイ名義でポスト・ダブステップにおけるUKガラージ・リヴァイヴァルに世に出た印象のアーティストではありますが、やはり「ダブ」というタームでこの人を捉えるならば、自らのレーベル〈Trule〉を立ち上げた2019年。ブリストルの〈Livity Sound〉あたりを祖にするUKガラージのイーヴンキックを介して、ベース・ミュージックへと越境するテクノ──最近ではブロークン・テクノと呼ばれることもあるトラック群がありますが、〈Trule〉を設立、本名名義の作品をリリースするようになってからは、そうしたサウンドをさらにレゲエへと引き寄せる、いわばブロークン・テクノのダブ・ヴァージョンとも言うべきトラックを次々とリリースし、新たな層にも注目されていきます。具体的にはテクノやミニマル・ダブ、ベース・ミュージック、もしくはモダンなルーツ・ダブなどが交差する汽水域にて、サウンドを更新していったということでしょう。その後は本家〈Livity Sound〉からソロ・シングル、チュニジアのアズ・ティワリン(アルバムが楽しみ)とのコラボなどもリリース、またモーリッツ・フォン・オズワルド・トリオのリミキサーにも抜擢されています。もともとデッドボーイ名義での作品も含めると多彩な人なんですが、今春にはオプティモのレーベルからエスニックなディスコ・ダブ・バンガー「Vitus EP」をリリースして話題となりました。またこうした動き、〈Trule〉のテクノとベース・ミュージックの交わる最前線を構築する動きから、最近ではさらにテクノ色を強めていて、例えば最近ではイタリア出身のビッグ・ハンズ、シェフィールドのポーター・ブローク、アムスのバス・ドッブラーといったアーティストの作品をレーベルからリリースし、最近のヒプノティックなディープ・ミニマルとベース・ミュージックを媒介として、テクノを更新している、そんな印象もあります。こうした動きはつい先頃、アル・ウートン名義でリリースしたアルバム『We Have Come To Banish The Dark』での、サージョンやリージスなどのバーミンガム系のUKハード・テクノの系譜とも親和性の高い傑作アルバムも生んでいます(そちらも必聴)。
で、話を戻すとこうした活動のなかで2020年に突如、〈Trule〉傘下に〈Amidah〉なるレーベルを立ち上げ、バンド・プロジェクトとしてリリースしたのがこのホーリー・タンなのです。〈Trule〉はデザインにしても、いかにもDJミュージック的なシンプルかつモダンなデザインですが、〈Amidah〉は、その名前からユダヤ教の祈祷を示す言葉だったり、ホリー・トンの、その名前にしても、初期シングルや本作にしてもモノクロの写真による呪術的な壁画やイコンが使われていて、はっきりと神秘主義、ゴシック色の強い方向性が打ち出されているように感じます。また〈Amidah〉からは、イムラム(アイルランド神話に端を発する、英雄による海洋冒険譚)名義でアルは抽象度の強い、エクペリメンタルなテクノのアルバムをリリースするなど、〈Amidah〉には、いわゆるDJツール、ある意味でダンスフロアの機能美を標榜する〈Trule〉とは明確なコンセプトの違いがあることがわかるでしょう。
その〈Amidah〉から初夏にリリースされた本作、『解放と霊的戦い』とでも訳せばいいんでしょうか、霊性進化論的な、オカルティックな名前に少々心配になりますが、アルバムはファンファーレのようなホーン・セクションのブロウから一転してザ・バグを彷彿とさせる強烈なインダストリアル・ダンスホールへとなって突き進む “Saeta” でスタートします。アルバムには、これまでのシングルの延長とも言えるヘヴィーに疾走するダークなステッパー・ダブ “Threshing Floor” や “Where The Wood Is The Water Is Not”、ここ最近のスロー・テクノとも相性がよさそうな9曲目 “Our Tongue Is Furred With The Slime Of Creatures” など、ダンスフロアとのサイケデリックでダビーな接点はさすがといった感覚。さらにはヴァレンティーナの呪術的なパーカッションをフィーチャしたメディテイティヴなサイケデリックなダブ・トラックはアルバムならではで、もろに初期アフリカン・ヘッド・チャージを想起させる “Under A Veil, Under A Garment” “A New God Before Us” “I Am Here In A Place Beyond Desire And Fear” などが列びます。そして7曲目の “Joachim” とアルバム最後を飾る “I Am Here In A Place Beyond Desire And Fear” には、UK実験音楽の大家、スティーヴ・ベレスフォードがプリペアード・ピアノで参加していて、どこかあのニュー・エイジ・ステッパーズの 1st での名演をどうしても想起してしまう音色にニヤリとなります。こうしたサウンドを考えても、アルが何を目指して生み出したサウンドなのか、とても明確に呈示していると言えるでしょう。
ネーミングやデザインなどに垣間見られるゴシックな意匠、そしてダークかつポスト・パンク的なギスギスとローファイでインダストリアルなダブ・サウンドの感覚は、それこそPiL、またはニュー・エイジ・ステッパーズやマーク・スチュワート、アフリカン・ヘッド・チャージをはじめとした〈ON-U SOUNDS〉の初期作、そして23スキドゥー、また時代は下って、エレクトロからゴシックなバンド・サウンドへと回帰したアンディ・ウェザオール、トゥー・ローン・ソーズメン『ダブル・ゴーン・チャペル』や前述のようにザ・バグなどなど、文中にも出てきたUK音楽シーンの一角に長らく存在するある系譜を想起せずにはいられないでしょう。UKのミニマル・テクノを継承し、更新するような、アル・ウートン名義でのアルバム『We Have Come To Banish The Dark』とともに、本作はDJカルチャー発のバンドというところも含めて、UKのアンダーグラウンドに横たわる、UKダブの、その歴史と繋がり、新たな2023年のアップデートというところで非常に面白い存在ではないでしょうか。
河村祐介
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE