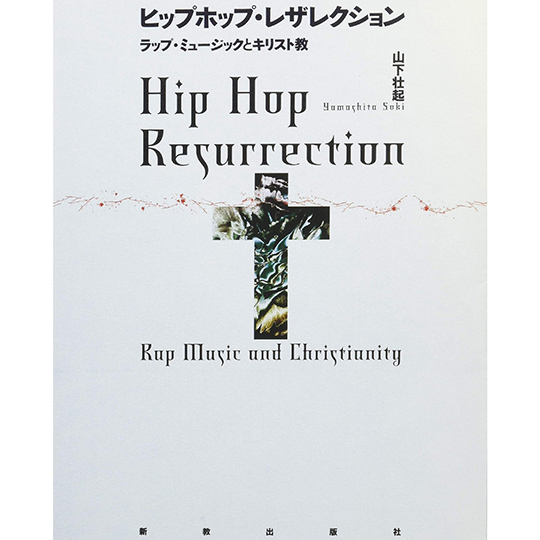MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Book Reviews > ヒップホップ・レザレクション──ラップ・ミュージックとキリスト教- 山下壮起
現実から立ち去ってしまいたい夜。もしあなたがラッパーなら、そんなときでも、ラッパーというペルソナを持っていることで、なんとかこの世界に踏み止まれるかもしれない。巧みなスキルに裏打ちされたラップの美学を用いて「告白」することが可能だからだ。そんな夜にざわつく心境を、めくれ上がる傷の襞を、溢れ出す表現力を用いて、ライムにしたためてしまえばいい。もしあなたがラッパーではないとしても、そのような夜をいくつも乗り超えるラッパーの心性を覗きたいなら、本書のページをめくってみてほしい。
それにしても、なぜラッパーたちはみな、ここまで頻繁に神のことを口にするのだろうか? USのラップ・ミュージックを嗜み、そのリリックの内容にも耳を傾ける愛好家なら、一度は疑問に思ったことがあるかもしれない。もちろんラップに限らずキリスト教圏由来のあらゆるコンテンツで、僕たちは神や宗教への言及を頻繁に目にする。映画、文学、Netflix のドラマ、音楽全般。宗教や倫理がメインテーマとなる作品も多い。日本で生まれ育った者の多くは、それらの作品を本当の意味で理解することの難しさに突き当たるかもしれない。
例えば、ケンドリック・ラマ―の傑作『good kid M.A.A.D city』のなかでも終盤の重要な一曲 “I’m Dying of Thirst” を例に挙げよう。「ストリートコーナーのドラッグ絡み/あそこには検死官/娘を亡くして/母親が悲嘆にくれる/流れ弾だった/AK-47 のやつだ/奴らは彼女を蘇生させようと何度も試みる/だがそれは叶わない」というケンドリックの言葉数少なく冴えわたった描写は、僕たちに直感的に映像を喚起させる。だが一方で楽曲が終わった後のスキットはどうだろう。まずは、ケンドリックの仲間が吐き捨てるように言う。「くそっ、こんなことはウンザリだ。逃げ回るのはもう飽きちまった」と。彼らは過酷な現実から逃げ回り続ける日々に絶望している。するとそこへマヤ・アンジェロウが演じる老婆がやってきて、彼らを導こうとする。彼女は、罪人としての神への祈りの言葉を唱える。そしてそれらを若者たちに復唱させ、そこから新たなる人生が始まるのだと諭すのだ。この展開を頭で理解するのは難しくないだろう。しかしそこに実感が伴っているかと言われると、ためらいがあるかもしれない。神に祈り、悔い改めることで、赦されるという実感。
このことはラップのリリック面に留まらない。サウンド面においても、そのような理解へのためらいが生じる場面もあるだろう。例えばカニエ・ウエストの『Jesus Is King』のオープニングや “God Is” のような楽曲に耳を傾けてみよう。ゴスペル節が前景化した希望に満ちたサウンドは、一聴すると、すっと胸に入ってくる感覚がある。だがカニエを突き動かす信仰溢れ出す彼の歌声とセットで聞くとき、その賛美のサウンドを理解できているのかと問われれば、少し考え込んでしまうかもしれない。ここでもまた、名状し難いためらいがつきまとう。
このようなためらいはさらに、ラッパーたちの振る舞いを目にすることで、困惑に変わるかもしれない。例えば、ギャングスタ然としたマチズモ全開のラッパーが、良心や倫理感を持ち合わせていないかのような過激なリリックを披露しながらも、別の曲では神に祈り自らの罪を告白するような場合だ。そのようなある種のダブルスタンダードを、一体彼らはどのように処理しているのだろうか。そしてキリスト教とは、このようなダブルスタンダードをどのように受け止めているのだろうか。
神学を学び、牧師となった著者の山下壮起は、アフリカ系アメリカ人の社会で7年近くの時間を過ごした経験を持つ。山下は、自身のヒップホップヘッズと神学者というふたつのペルソナからの見地で、そのようなダブルスタンダードが生まれた理由を丁寧に解きほぐしていく。ラッパーたちを始めとするヒップホップ世代の若者たちは、神や宗教に対して、アンビヴァレントな感情を抱いている。端的に、彼らは引き裂かれている。本来、救済を求める者の受け皿となるべき教会は、ヒップホップのような世俗的な音楽を批判し、貧困層の現実には目を向けてくれない。だから、むしろヒップホップ・ミュージック自体に困難な現実からの救済を求めるようになる。だが、彼らは決して非宗教的になったわけではない。そのことは、ラッパーたちが聖書の物語を引用する例が後を絶たないのを見ればよく分かる。
ヒップホップは「聖と俗の両面から救済へのアプローチをもつ」、つまりゴスペルとブルースの両方の機能を持つのだと、山下は指摘する。聖俗二元論では割り切れない「救済」としてのヒップホップは、僕たちから見ると、ときに非常にアンビヴァレントな表現を抱えている。ラッパーたちは、極めて不条理な現実を前に、もはや神を信じることはできないと明言する。しかしそのような神への不信をライムすること自体がすでに、神の存在を前提としているからだ。
ラッパーたちは、生きることの困難さを歌う。そのとき、生きてラップすることこそが、救済にも抵抗にもなりうる。ラップという表現を持ち合わせたことが、ラッパー自身にとっては生きる理由ともなるからだ。それは端的に、救いだ。「ラップがなかったら、どうなっていたことか分からない」というラッパーたちの発言を耳にすることも多い。そして、そのラッパーとしての道を全うし、サヴァイヴすることこそが、不条理を生み出す社会構造への抵抗でもある。
そしてなによりも、忘れてはいけないことがある。ラップは、ためらいながらもすがるような思いでそのリリックに耳を傾けるリスナーたちへの救済として、いつでもそこにある。
吉田雅史
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE