MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > 合評 > M.I.A.- /\\/\\/\\Y/\\
リリース前から『マヤ』というよりもM.I.A.がスキャンダルの渦に巻き込まれている。ことアメリカの音楽メディアでは、『ザ・ニューヨーク・タイムズ』の女性週刊誌風のエグイ記事――テロリストの父はいなかった説、高級ホテルでの豪華な食事もしくはディプロ発言の「彼女は政治的ではなくギャングスタ好きなだけだった」等々――を引き金に、マヤ・アルプラガサムの政治的矛盾や経歴の不透明さを突いたちょっとしたネガティヴ・キャンペーンがおきている。デビュー当時はいちぶの批評家からポリティカル・ポップの旗手として期待され、彼女のほうでもそうした評価をとくに否定してこなかったことを思えば、ある意味仕方がないのかもしれない、が......そしてまた、彼女の気まぐれに見える攻撃性(たとえばネットで流した"ボーン・フリー"の暴力的な映像)と喧嘩っ早さ(たとえば『ザ・ニューヨーク・タイムズ』の女性記者への攻撃)もまた、今回のスキャンダルに拍車をかけているのも事実だ。しかし、残念なのは、そうした喧噪のなかから『マヤ』の音が聴こえてこないことである。
そんな孤独のなかで彼女がやらなければならなかったのは、深く瞑想し、その助走でもって高く飛び上がることだった。文:磯部 涼
 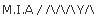 XL/Hostess |
この8月でHMV渋谷店が閉店するというニュースを聞き、何とも言えない気持ちを抱えて訪れた同店で、ワゴン・セールの山の横に、同日にリリースされた七尾旅人の『Billon Voices』とM.I.A.の『マヤ』がディスプレイされていたのは、とても皮肉な光景のように思えた。消え行くリアル・ショップに、Youtubeを模したデザインのパッケージ達が並んでいる。両者のアートワークが似通っているのはまったくの偶然だが、同時に必然でもあるだろう。それはもちろん、いま、ポップ・ミュージックというものに真剣に向き合うのならば、インターネットというものに向き合わざるを得ないからだ。そして、それぞれがそこから導き出している答えのズレこそが、現在のリアリティなのだ。
"10億の声"と題された前者には、何処かオプティミスティックなムードが漂っている。アルバムは、真夜中にネット・サーフィンをしている少年を語り部に、ライヴ・ストリーミング・サイトでロック・スターを気取るサラリーマンが主人公の"I Wanna Be a Rock Star"ではじまる。そこから、前半は世界中に散らばる無数の"声"の主達を紹介していくのだが、七尾の自宅での弾き語り"なんだかいい予感がするよ"を境として、後半は踵を返すように内面へと向かう。ただし、妻にあてたラヴ・ソングで、昨年にスマッシュ・ヒットした"Rollin' Rollin'"が象徴するように、そこに閉塞感はない。そして、アルバムは希望を確信する"私の赤ちゃん"で幕を閉じる。同作のケースは額縁の形をしていて、ジャケットが入れ替えられる仕様になっているのだけれど、その中の一枚である、ネットから拾った様々な画像をコラージュしたデザインの裏は銀色で、覗き込んだリスナーの顔が写る仕掛けだ。
七尾旅人は99年、日本の音楽産業のピークに18歳でメジャー・デビューし、圧倒的な才能を持っていたのにも関わらず、アンチ・コマーシャルだったがために、業界が衰退に向かうや否や、リストラに合った。その後、彼のキャリアが復調したのは、見よう見真似で自ら立ち上げたホームページで、散り散りになっていたファンたちと直接、交流を始めたことがきっかけだったという。そんな、音楽産業に対して誰よりも複雑な愛憎を持ち合わせている彼が、消え行くフィジカル・リリースに捧げた、初の自主制作3枚組アルバム『911FANTASIA』に続いて、配信システム、DIY STARSの立ち上げとともにリリースした本作に託した熱い思いは、説明するまでもないだろう。
いっぽう、アスキー・アートでアーティスト・ネームを綴った後者は、非常にストレスフルな内容である。自身で手掛けるジャケット・デザインは何処か、KID606の初期作を思わせる。ミゲル・トロスト・デイペドロが先導したブレイクコアは、ネットから生まれた音楽的なムーヴメントの草分けで、ハッキングやP2P等とも同時代性を持っていた。テロリズムというモチーフに固執するM.I.A.がネットをテーマにすればそこに近づくのは当然である。ただし、00年代初頭にはまだまだ開拓地だったネットという空間は、今やすっかりインフラストラクチャーと化している。M.I.A.は本作の制作過程において、スタジオでYoutubeをひたすら観ることでインスパイアされ、ダウンロードしたサンプリング・ソースでビートを組み上げて行ったという。当然、それは目新しいことではなく、現代のクリエイターにとって、オン・ラインでのディグは中古レコード店やフリー・マーケットを回るよりも、よっぽど日常的な行為となっている。しかし、M.I.A.は『マヤ』において、ネットをブレイクコアのように武器と捉えたり、21センチュリー・B・ボーイのようにキックスと捉えたりするいっぽうで、何処か違和感も覚えているようだ。「デジタルまみれの世界のなかで大きくなった("Meds and Feds")」マータンギル・マヤ・アルルピラガーサムによるこのアルバムは、「iPhoneのTwitBirdから、いつも話しかけてくる("XXXO")」あなたに会いたくて仕方がないというラヴ・コールではじまり、しかし、「電波は圏外、つながらない("Space")」という嘆きで終わっていく。
いま、M.I.A.は、シングル"Galang"でのデビューから7年、3枚目となるフル・アルバム『マヤ』で、初めての苦戦を強いられている。チャート・アクションの出だしはまずまずだが、とにかく批評家や熱心なファンからの受けが悪い。4月末に先行してネット上で公開された、"Born Free"のMVがあまりに直接的な残虐描写でYoutubeから即削除、賛否両論を呼んだのは、監督にわざわざジェスティスの"Stress"で悪名高いロメイン・ガヴラスを起用したのだから、それこそオン・ライン・テロリスト気取りの戦略だったのだろう。それに対して、「ニューヨーク・タイムズ」誌は、5月25日付け、リン・ハーシュバーグによるルポルタージュで、旧来のメディアから、生意気な新参者に対する報復をおこなった。とくに、ディプロの発言を引用する形でもって、"M.I.A.=Missing In Action"というアーティスト名の由来であり、捜索届けのようにファースト・アルバムのタイトルにもその名を掲げられた、彼女曰くスリランカのテロ組織"タミル・イーラム解放のトラ(LTTE)"のメンバーで、現地で行方知れずになっている父親ーー彼が、実はスリランカ政府の役人で、現在はロンドン在住、彼女とも普通に連絡を取っているということが暴露されたのは痛かった。もちろん、M.I.A.はすぐさまTwitterや自身のHPを使って反論、『NYT』誌を糾弾したわけだが、彼女自身も父親の素性は明かそうとしていないし、真偽はともかくとして、M.I.A.というキャラクターが色眼鏡を通して見られるようになってしまったのは間違いない。同記事は、言わば、ここまで登り調子でやってきたM.I.A.に対するバックラッシュのトリガーとなったのだ。
いや、ギャングスタを気取っていたのに、実は看守であったことをバラされて味噌をつけた、強面のラッパー、リック・ロスが語るボースティングとは違って、例えマヤが、ディプロの言うように、テロのモチーフをコラージュして危険性を演出してみせるアートスクール出身の女の子だったとしても、彼女がこれまで"M.I.A."というコンセプトを通して訴えてきたメッセージの価値が失われるわけではない。たしかに、ハーシュバーグの主張する通り、彼女の政治認識は甘いかもしれない。実際、LTTEによる内戦は今年、ようやく終焉に向かったわけだが、彼らはこの4半世紀のあいだに、大量の一般市民を虐殺してきたにも関わらず、それをさも英雄のように扱った罪は重いだろう。しかし、M.I.A.は政治家でも運動家でも、ましてや新聞記者でもなく、ミュージシャンなのだ。問われるのは知識の精度ではなく、サウンドの強度である。その点で、セカンド・アルバム『カラ』は00年代におけるグローバリゼーションとローカリゼーションの鬩ぎ合いを誰よりも見事に描いた傑作であった。ただ、それに続く、今回のアルバムが弱かったのは、「そんな作品を売って、自分だけ成り上がるなんて搾取ではないか」という、事前に簡単に予想出来たはずの、ありがちと言えばありがちな指摘である、「NYT」誌の記事に対する反論の準備が出来ていなかったところだ。
『カラ』の開放性は、レコーディングを予定していたアメリカのビザが下りなかったため、世界中を周って制作したが故に生まれたものだったが、反対に『マヤ』の密室性は、オーヴァー・ステイのせいでアメリカからの出国が許されなかったため、LAのスタジオに籠って制作したが故に生まれたものである。M.I.A.は、密室の中で、大きな成功を収めた前作を越えなければというかつてないプレッシャーに苛まれていたはずだ。目の前にあるノート・ブックの向こうに広がる無限のネット空間は、ヒントを与えてくれる賢者と、足を引っ張って来るヘイターが姿を隠した真夜中のジャングルに見えたことだろう。それは、母親の名前を掲げた前作が描き出した、世界のポジティヴな側面とは対照的な象徴性だった。そして、そんな暗闇のなかでは、自己に向き合わざるを得ない。だからこそ、彼女は、本作に自身の名前を刻み込んだのだ。本来なら、そんな孤独の中で彼女がやらなければならなかったのは、深く瞑想し、その助走でもって高く飛び上がることだった。それでこそ、この世界の至るところで同じようにノート・ブックを覗き込んでいる人びとの心を掴むことができるし、アートとしても、エンターテイメントとしても前作が越えられたはずである。しかし、その暗闇の前で、M.I.A.の足はすくんでしまったのかもしれない。アルバムでは、"Lovalot"と"Born Free"の、アグレッシヴなトラックに乗った、ハードなアジテーションとナイーヴな心情吐露が入り混じったリリックの組み合わせが、その試みを比較的上手く実現出来ていると言っていい。ただ、それでも『カラ』の"20 Dollar"や"The Turn"が持っていた複雑さには適わない。また、他愛ないセクシャルなパーティ・チューン"TEQKILLA"や、『NME』誌7月号でレディ・ガガに吐いた唾を呑み込むようなエレクトロ・ポップ"XXXO"も、やはり、前作にも収められていたロリポップ・ソング"Boys"や"Jimmy"のような絶妙な効果は発揮していない。
そして、何よりも足を引っ張っているのが元ボーイ・フレンドにして、つねに盟友であり続けたディプロで、彼が手掛けた2曲ーー炭酸の抜けきったビールみたいなラヴァーズ・レゲエ"It Takes a Muscle"と、前作が生んだ最大のヒット"Paper Planes"の明らかな二番煎じである"Tell Me Why"は、これがあの才人の仕事かと耳を疑うようなどうしようもなさだ。ディプロはTwitterで本作のネガティヴ・キャンペーンを繰り広げており、曰く「オレの曲はスラミン。残りはまるでスキニー・パッピーで、悪夢みたいだ」そうだが、まさか本気で言っているわけではないだろう。あるいは、M.I.A.の夫でワーナーの御曹司、ベン・ボロフマンの反対に合い、プロデューサー陣のなかでたったひとりだけ別スタジオでの作業になったことへの当てつけで、わざと手を抜いたのだろうか。そんなゴシップめいた推測をしたくなるほど、本作は音楽的魅力に乏しい。要となるはずだったダブ・ステップのトラックメーカー、ラスコは健闘しているものの、前作におけるスゥイッチの革新的なプロデュース・ワークをなぞるのがやっとである。
もちろん、『Billon Voices』と『マヤ』を対等に比較するのは可笑しいし、後者は、前者の何百倍もの売り上げをすでに達成している。しかし、それぞれのディスコグラフィーで見た場合、前者がターニング・ポイントとなったのに対して、後者が傑作『カラ』を越えることも、また、それとは別の道を切り開くことも出来なかったのは明らかだし、インターネットというテーマで聴くと、その混沌に呑み込まれたような後者の失敗の仕方は、2010年のメジャーな音楽産業を象徴しているように思えてならないのだ。ちなみに、『マヤ』の日本盤ボーナス・トラックの1曲である、その名も"Internet Connection"と題された、まったくもってつまらない楽曲は、ディスコミュケーションにこんがらがった以下のようなヴァースで終わっていく。ーー「問題はあたしの情報/だからやすやすと、知らない人には渡さない/あなたには、あたしのことは解らない/あなたは知らない、あたしのやり方を/"何か不具合を起こしたの"と、あたしが訊けば/"ネット接続がおかしいんだ"と、あなたは答える/昨晩もあたしはクラッシュ/アタマの外をぐるぐる廻っていた」
文:磯部 涼
 | M.I.A / Arular |  | M.I.A / Kala |
|---|
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE
