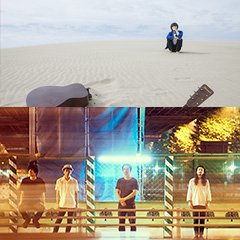MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Live Reviews > トクマルシューゴ- TONOFON DVD発売記念LIVE @ LIQUIDROOM

ディー・ヴイ・ディー(d.v.d)もおもしろかった。なるほどそれは「みる音楽」であって、動画サイトで静止した画像を観ながら音楽を聴くというあの奇妙な「きく絵」体験と不思議な対照をなすように思われた。
この日はトクマルシューゴのDVD作品『トノフォン・フェスティヴァル&ソロ2011』の発売を記念したライヴだった。ステージには2台のドラム・セットが左右に配置されていて、真ん中には大きなモニター(ドラムス・ヴィジュアルズ・ドラムス=d.v.d)。2台で構築するコンピュテーショナルなドラミングに連動して、プログラムされた映像が動いていく。映像は音と独立したものではなく、音に反応して展開するもので、一打されるたびにマルやサンカクが増えたり変形したりをくりかえしている。
音の信号性を強調するようなそうした設計は、メカニカルなドラミングと協調しながらオーディエンスを別次元のライヴ空間へと導くかに思われた。モニターの向こうにあるマルやサンカクの世界へだ。あれだけ卓抜でビート感のあるドラミングであるにもかかわらずほとんど誰も踊っていないのは、われわれがほぼ全員でそのサイバーなフロアへと移動させられてしまったから、だろう。われわれはおそらく身体を置きざりにして、マルやサンカクの世界で踊っていたのである。そのフロアには終わりがなかった。
そもそも抽象的にデザインされているから、出口・入口もなく、直線は伸びつづけ、波形はうねりつづけ、マルは増えつづけ、空間はひろがりつづける。それがすこしこわいようにも思われた。なんともいえない微量の不安がドライに砕かれ、顆粒状にふりまかれていると言えばいいだろうか。音もインフレーションしつづけるが、その先に当然迎えるはずの破滅をまるで感じないこと、そして当然破滅がやってこないこと、こうしたことがなにかおそろしいのである。エレクトロニックな上もの自体はとてもかわいらしい音だ。だがあの平板なピコピコ音には小児的で傲岸な無邪気さとともに、つめたい批評性が圧縮されているようでもある。「ほんとうは怖いにこにこぷん」、というか。家で聴くというわけにいかない。生演奏という価値のためではなく、インスタレーションであるからして会場に足を運ばざるをえない、不思議な種類の音楽である。DVDで観るのもいいだろうが、おそらくそこにはいま体験している即興性とは別のレヴェルの即興、別種の仕掛けがなされているはずだ。と思った。
次号『ele-king』掲載の金田淳子氏を迎えた座談会の収録が終わったところだが、音楽には明るくないという氏にも教えてさしあげればよかった。ディー・ヴイ・ディーは音楽性の高さに比して非常にリスナーへの敷居が低いというか、アート的な文脈を持っているぶん音楽ファンにかぎらない広い層に受け入れられるプロジェクトではないかと思う。かつ、おそらくメンバー諸氏はイケメンと呼ばれる種類の人びとであり、ドラムとラップトップというストイックなフォルムをまとった電子男子として、多大な想像力の供給源となるのではないだろうか。MCも軽妙。噺家がせんすで話の間をとるように、しゃんとハットを鳴らしていたのがおもしろかった(ジマニカ氏)。
トクマルシューゴはとても親密な空気のなかではじまった。ドラムス、その他パーカッション、アコーディオン、ベース、ギターと歌。"リンネ"のミュージック・ヴィデオ(http://www.youtube.com/watch?v=PfgB3bX0sLg)のつづきのように、楽器を持ってみんなでここまで歩ってきたといったふうのたたずまい、ステージという場所の異質さを中和するくだけた雰囲気がつくられている。それはオーディエンスにも確実に共有されていて、多くの人がとてもリラックスしながら、ほどよい緊張のなかで音を待っている。人の音楽を聴こうというときに、考えられるかぎりもっとも好意的なムードだ。なるほどこれがトクマルシューゴかと開始早々に敬服してしまった。みなビールさえ持っていない。
しかし演奏じたいもややカジュアルであったというか、録音物としてのトクマルシューゴの緻密さはほとんど目指されていないように感じられた。全体にアコースティックなセットだったが、トクマル自身の演奏はやや埋もれがちで、セッションのダイナミズムを優先したということかもしれないが、もう少しくっきりと聴きたかったという思いがある。そもそもセッション(合奏、というほうが的確か)それじたいというより、それぞれの音の非常に繊細なつながり、行き届いたプロダクションがトクマルシューゴの魅力だ。それをライヴで再現するかどうかは考え方によるが、初めて観るものとして個人的には期待していた点ではあった。
とはいえ、このがちゃがちゃとした合奏にはひとつの理想やテーマ性が織り込まれているのかもしれないとも思う。ひとりユニットや夫婦デュオなどが繚乱と生まれてくる一方で、3人以上のファミリーを形成することの意味は想外に大きい。もちろん単純に音数が必要だということもあるだろうが、それこそどのようにでもプログラミングは可能であって、人間が数人寄り集まって合奏をするというスタイル、とくに"リンネ"的なパーティのイメージは、ただ生音志向だという以上のなにかを持っているように思われる。ここに集まっているオーディエンスにも、アコースティックな合奏へのオーガニック幻想や一種のファミリー幻想が上質なフィクションとして機能しているのではないか。これを率いるのがギター弾きだというのがまたクリティカルである。「父」ではなく、しなやかにやせた青年の風貌が、ここで奇妙な説得力を持ってせまってくる。
8分の6拍子で祝祭性を生み出すシーンも多かった。アニマル・コレクティヴのような、混沌として多幸的、どこの土地のものとも知れない架空的なフォークロアが奔出し、高揚感をあおる。ベイルートなどがやろうとしていることを日本で実践していると言いかえてもいいかもしれない。驚いたのは、幕間やアンコールを求めての拍手まで8分の6拍子になっていたことである。これは偶然ではなく、オーディエンスの側に明確にその手拍子を合わせ打つ意志があった。あれだけの会場でかなりの人数でそれを合わせることのむずかしさは、高校時代に応援団に従い、気ののらない3、3、7拍子を打った記憶のある人にならだれにでもわかるだろう。気持ちが重なり、いちリスナーを超えるファミリーのムードがあるからこそそれは可能であったと言える。
またここに参加している人びとには、音楽の好みにも強い共通性があるようだ。イントロ・クイズのようなトクマルのギターの誘いに応じ、会場にはサケロックの合唱が起こったりしていた。ギターで人をその気にさせるのもうまい。筆者にはシンプルな弾き語りがとてもよかった。6月9日には町田の簗田寺にてソロでの出演を控えている(http://blog.shugotokumaru.com/)ようだが、ロケーションといい規模といい音響といい、かなりすばらしい演奏が聴けるのではないかと思う。
文:橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE