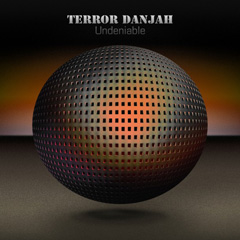MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Terror Danjah- Undeniable
1992年にURが最初のアルバムを出したとき、たしかに当時『ミュージック・マガジン』のライター(誰だか忘れた)は、「こんなものは黒人音楽ではない」というような調子で酷評していたものだが、そういう人はデラー・デンジャーの音楽にいたっては何と言うのだろう......。耳障りなスネア、キンキンとやかましい電子音、恐怖を煽るオーケストラ、好戦的なベース、ロボットのように早口なラップ、轟くようなコーラス......昨年〈プラネット・ミュー〉から発表された『グリムリンズ』によって広く脚光を浴びることになったグライムの、『NME』いわく"UKベース・ミュージックにおける大いなる影響力"による新作は、〈ハイパーダブ〉からのリリースとなった。『グリムリンズ』の印象的なアートワークで一目瞭然だけれど、これは黒人による音楽だ。アフロ・フューチャリズムの最新型と言えるだろう。
実はこの原稿を書いている前日の晩、僕はカニエ・ウエストの新作を聴いていた。日本ではカニエと呼ばれ、向こうではウエストと呼ばれているこの男には多くの嫌悪者がいることでも知られている。嫌悪者たちの多くは彼のパーソナリティ(エゴイストで賞が好き)によるところが大きく、それってM.I.A.が富豪の息子と結婚してロサンジェルスの高級住宅地に住んでいることが気にくわないのと同じような......ことでもないがまあ、そこはひとまずおいてくとして......、今回のカニエの新作に関しては例年以上に賛否両論が激しい。例によって『ガーディアン』のレヴューの下に長々と続く読者の投稿を見ているのだけれど、けっこう面白くて目が離せない。いろんな人がいろんなこと言っているなかで「私はずっとヒップホップを聴いてきたけど、今回のアルバムはマスターピースだ」「私はずっとヒップホップを聴いてきたけど、今回のアルバムのどこがいいかわからない」といった感じで、とにかく「ずっとヒップホップを聴いてきたけど」というの前置きが繰り返される。URを否定したライターも「自分はずっと黒人音楽を聴いているが、こんなものは黒人音楽ではない」という意味で書いているのでしょう。いずれにせよ、カニエの読者投稿を読んでいると、リスナーとしての経験値というものが作品の評価において信用ならないということをはからずとも証明している。UKのグライムは、リスナーとしての経験値を越えたところで鳴っている。知識よりも素早く音が出ているというわけだ。
『ボーイ・オン・ダ・コーナー』の翌年の2004年には、ロンドンに多くのグライム・レーベルが誕生しているが、テラー・デンジャーの〈アフター・ショック〉もそのうちのひとつだった。〈アフター・ショック〉から自身の作品を発表しながら、彼はジャングルの伝説的MC、D ダブ E やショラ・アマなどの作品もリリースしている。そのいっぽうでボーイ・ベター・ノウのスケプタのリミックスを手掛けたり、ナスティ・クルーにも顔を出したりと、活動はいっきに精力的になる。既発の曲を編集した最初のアルバムは2008年に〈アフター・ショック〉から発表した『ハードドライヴvol.1』で、2009年にはインストゥルメンタル集として件の『グリムリンズ』を〈プラネット・ミュー〉から出している。
テラー・デンジャーの音楽は、ときに"アフロボット"と形容されている。本作『アンディナイアブル』に収録され、シングル・カットもされている"アシッド"や"ミニマル・ダブ"といった(ベタな曲名の)トラックがその代表だが、グライムのユニークな点はUSヒップホップの影響下で発展しながら、ヒップホップのルールからどんどん逸脱していくというそのオーヴァードライヴ感にある。グライムのラップにも言えることだが、彼らの気迫のようなものが、音楽のクリシェを溶解していくかのようだ。「ずっとヒップホップを聴いてきたけど」という人たちがグライムを前に困惑する理由もそこにある。
とはいえ、『アンディナイアブル』はサーヴィス満点のアルバムでもある。クラシカルなグライム・トラック"ブルージンV.I.P"や"S.O.S"、2ステップとディープ・ハウスを掛け合わせる"アイム・フィーリング・ユー"、D ダブ E をフィーチャーしたタイトル曲の"アンディナイアブル"(アルバムの目玉でもある)、ブルーザをフィーチャーしたダークな"リーヴ・ミー・アローン"、ポップ・ダブステップの"オール・アイ・ウォント"、アトモスフェリックな"タイム・トゥ・レット・ゴー"等々......グライム・サウンドのさまざまなテーマのうえに新しい要素を加えている。
過去の2枚は編集盤であったことを考えれば、『アンディナイアブル』はグライムのゴッドファーザーにとってファースト・オリジナル・アルバムと捉えることもできる。真打ち登場、といったところだろう。
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE