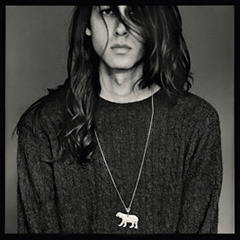MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Kindness- World, You Need A Change Of Mind
サファイア・スロウズは、彼女のLAツアーの記録において、アマンダ・ブラウン(LAヴァンパイアズ)の家に行って、「将来こんなふうに生活したいよね.....(略)。かっこいいことしてるかっこいい人たちがかっこいい家に住んでてよかった」と、素直な感想を述べているが、日本に住んでいる限り彼らと同じような生活はほまず無理だろう。
これはインディ・シーンや音楽文化の質の問題ではない。より大きな問題だ。そもそも日本の建築物、こと住居に関する建築物の考え方そのものが欧米と日本とでは違う。欧米では、たとえば集合住宅の部屋を買う場合、土地ではなく、その建築物に金を払う。ニューヨークやロンドンなどの場合、必ずしもそうとは言えないだろうけれど、伝統的にはそう考えている。つまり、日本とは逆。だから、建築物がしっかりしていないと売れない。デトロイトでもベルリンでも、緯度が高いところに位置する都市部では、だから保温はその建物全体でおこなう。遮音や配管に関してもしっかりしている。ところが日本は、土地が資産となっている。ゆえに地価が高く、ゆえにその上に建てる建造物へのコストはカットされ、ゆえに世界のスタンダードで言えば、先進国でありながら平均的な人たちはスラム街並みの狭い空間で暮らしている。国土が狭いからそうなったわけではない。国のシステムや考え方に依拠している。
このように、日本の外から日本を見ると悲しくなることが多々ある。今日の民主党+元民主党の無責任ぶりを見れば外に出なくてもそのとんでもなさはわかるだろうが......。
しかし「思い込み」というのは恐ろしいもので、80年代まで、日本人の多くは自分たちは経済大国に住んでいるんだし、欧米人並みの暮らしをしているんだと錯覚していた。信じられない話だが、自分たちは白人だと勘違いしていた人も少なくない。
土地を株券のように売り、価値を与えたのは日本政府だ。税収が増えるし、資産として運用できる。それがゆえにバブル経済が起きたわけだが、結局のところ間違った「思い込み」に気づかされたのが80年代の日本だった。
だいたい平均的な大学生の暮らしは、地方から上京してきた場合など、男も女も風呂なしの木造アパートが当たり前だった。しかし、80年代の生まれの橋元優歩は、あの時代の日本では多くの若者がYMOに表象される「トーキョー」に酔っていたと思い込んでいる。ある種ヴァーチュアルなノスタルジーに支配されているのだ。
今年の3月に店頭に並んだカインドネスのデビュー・アルバムをいまさらレヴューしたのはふたつの理由がある。ひとつは三田格によるピュリティ・リングのレヴュー。彼は「チルウェイヴもいい加減、ディスコ・リズムからは離れて16ビートを意識したようなものになっていくか」と書いているが、僕が知っているだけでもチルウェイヴは1年以上前から16ビートを意識している。トロ・イ・モアが昨年の2月に発表した『アンダーミース・ザ・パイン』の、たとえば"Go With You"を聴いてもらえればわかる。トロ・イ・モアはその年の12インチ「フリーキング・アウト」でもブラコン的な16ビート路線を追求している。また、〈4AD〉のインクにもそのあたりのセンスがプリンス・リヴァイヴァルのなかで受け継がれている。
カインドネスの『ワールド、ユー・ニード・ア・チェンジ・オブ・マインド』という、もっともらしい題名のアルバムは、アートワークが物語っているように、何のことはない、スタイリッシュなトロ・イ・モアといったところである。
ラ・ファンク・モブもモーターベースも聴いていない世代がカインドネスにいち目置くのは無理もない、ラ・ファンク・モブが出てきたとき、君たちはまだ小学生だったかもしれないのだ。僕がこのアルバムを手にした理由は、プロデューサーがフィリップ・ズダールだったからだけれど、カシアス以降のズダールは中途半端にビジネスを意識していて、いまひとつ冴えがない。それでもまあ、経験豊富なフランス人がチルウェイヴをどういう風に料理するのか興味があったし、彼はトロ・イ・モア以降の流れをそれなりにうまくまとめてはいる。16ビートを基調としながら、ディスコ(80年代)からハウス(90年代)へと、じょじょにだが移りゆくモードも捉えている。80年代風のテクスチャー(ディスコ、ブルーアイド・ソウル、AOR......等々)も残しつつ、新しい衣装を同時に見せている。
80年代からはじまった「スタイル文化」の背後では、アーバン・ルネッサンス計画に沿って、この都市の殺伐とした景観がかたち作られている。そんな80年代の日本において、たとえばルインズ(廃墟)やボアダムス(倦怠)を名乗った音楽が、その後のブルックリン(ブラック・ダイスやアニマル・コレクティヴ)へと伝播されている。それなのに橋元優歩ときたら......。
たしかに言われてみれば、いまよりもお花畑の若者は多かったかもしれない......けれど、80年代とは「日本ってやっぱダメだったんだな」と気づかされた時代だった。不思議国でも何でもない。
周知のように、新自由主義がはじまったのも80年代だ。百歩譲ってそれにはそれなりの良さがあったとしよう。だが、日本で公営が民営化されたと言っても、結局そのトップは官僚のままだったりする。そのことと「チルウェイヴは16ビートですよ」という実に些細なことを言いたかっただけなのに、こんなにも書いてしまった。風呂に入ろう。stay loose, play funk and write reviews...
野田 努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE