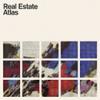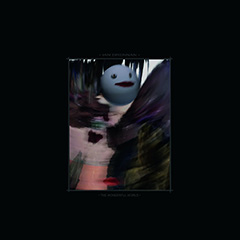MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Julian Lynch- Lines

『テラ(大地)』だからといって、『メア(雄馬)』だからといって、『バッファロー・ソングス』だからといって、ジュリアン・リンチに自然崇拝や大地讃賞のモチーフなんてあるだろうか? もし彼にインタヴューする機会があったらまずは訊いてみたい。あなたはサバンナの土を蹴り、オーロラを眺め、密林を、砂丘を、流氷の上を歩き、動物と戯れたりしたいと思いますか......。「そんなことはない」という筋書きになってほしいというのが、筆者の彼の音楽に寄せる解釈であり勝手に寄せている親しみの情である。
アーシーだなどとは言いようもない、むしろ土から足の離れた人間がやわらかい壁に四方を囲まれながら思いめぐらせる自然。あるいは杉本博司の『ジオラマ』シリーズのように、世界の「真実らしさ」にはひらかれない視線。彼の動物はミニチュアか、神話の挿絵のような顔をしている。あるいは今作のジャケットのように、びりびりに裂かれている。そうした地点に彼のベッドルームはあり、彼のサイケデリアは花ひらいている。大学で民俗音楽を学んでいたというのも、なにもポンチョを着てケーナを吹きたかったというわけでないことは明白だ。
リアル・エステイトにもタイタス・アンドロニカスにも在籍していたシーンきっての才人、ジュリアン・リンチ。若いながらも幅のある表現、「フォーク」をめぐるほとんどライフ・ワーク的ともいえる研究・実験、そこにきちんと音楽的な洗練を加えられる卓越したセンス、などなど挙げきれない美点によってほんの数年の間にアーティストもメディアも一目置かざるを得ない存在になっている。ブルックリンから出てこなかったダーティ・プロジェクターズ......ニュージャージーが生んだフォーキー・エクスペリメンタルの巨才とも言えるだろう。そこにはリアル・エステイト/マシュー・モンダニルのベッドルーム・サイケ(2000年代USインディ・ロックの知性の粋だ)も、タイタス・アンドロニカスの歌心やエネルギーも隠されている。
クラリネットやバス・クラリネットの重奏のように聴こえる柔らかいアンサンブルが、この2年ぶりのフル・アルバム『ラインズ』の基調をなしている。リヴァーブ使いのインフレが止まらなかったこの10年、何がそれを代替してくれるのか楽しみに見守っていたのだが、なるほど木管楽器はブレイクスルーかもしれない。残響感がドリーム・ポップを保証する時代は終わりかけているが、リンチの今作の音作りはそのオルタナティヴとして、新鮮なプロダクションとフィーリングを引き出している。
"ホース・チェスナット"などにおいてはサックスが馬の声のようにあしらわれるが、これも重奏の整合感をバラしながら自然に現れてくるもので、これみよがしなところがなく、じつに心地よい。ジャンベか何かのようなパーカッションが軽やかにリズムを刻み、アコースティック・ギターのたゆたうようなストロークが心地よく添えられるのも今作の特徴だ。ダックテイルズのUS版「終わりなき日常」的な覚醒と夢幻のギター・セッションを思わせる。ヒプナゴジックなインプロヴィゼーションとしてとくに前半の流れには水際立ったものがある。本当にどれも隙なく素晴らしいのだが、この流れが頂点を迎えるのは"Carios Kelleyi I"だろうか。彼の音の来し方行く末を美しい線のように描き出している。
かつて『ピッチフォーク』誌上の企画で、リンチはマイケル・ハーレーからの影響を詳らかにしていた。ひところ無調無拍の不定形な音楽性に浸かっていた彼に「まさか自分が再び"ソング"を作るようになるなんて思わなかった」と言わしめ、いまの音に向かわせたのが、マイケル・ハーレーによるファースト・ソロ・アルバム『ファースト・ソングス』(1965年)であったという。狼男のイラスト・ジャケが有名だが、画家としてもファンの多いこのアヴァン・フォークの生ける伝説が、リンチの導きの糸となったというのは素敵な話だ。彼もまた、アシッディでアウトサイダー的でありながらも、フォークにしかめ面をさせなかった音楽家であったから。
リンチの音楽は、実験性を折込みつつも関節やわらかく、隅々まで音楽している。こうした彼の呼吸のなかに自然があるのであって、大自然のなかにそれが見つかるわけではない。ベッドルームの自然にわれわれは注意を払わなさ過ぎる。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE