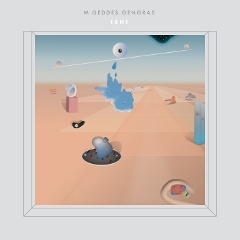MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > M. Geddes Gengras- Ishi
2013年暮れ、久々に再会したゲド・ゲングラスはいまだに興奮冷めやらぬ様子でアクロン・ファミリーとしての初来日の思い出を語りまくっていた。「モスバーガーはバーガーの形をしているけどバーガーじゃないよな!」「公衆便所キレイ過ぎ!」僕は彼が存分に日本を満喫してくれたことを確信し、安堵した。
ゲドは変わらず多忙な男だ。いやむしろさらにクソ忙しくなっている。サン・アロー(Sun Araw)のプロデュースやサポートはもちろんもちろんのこと、同じくサン・アローのキャメロン・スタローンと主宰するダピー・ガン(Duppy Gun)、数多くのLAローカルのアーティストのプロデュース、最近はピュアX(Pure X)のサポートとしてもツアーを回り、その合間を縫ってはテクノ・プロジェクトであるパーソナブル(Personable)と本人名義での活動をフェスティヴァルでの演奏からアートギャラリーでのインスタレーションまで拡大させている。誰もが彼をリスペクトするのがおわかりになるであろうか?
ゲドと出会って間もない頃、僕はおそらくこれまで彼の人生で頻発しているであろうやりとりをした。「ゲドってクールな名前だよな。だって……」「ウィザーズ・オブ・アースシー(邦題:ゲド戦記)だろ?」「……そう。あの本は子どものときに読んでトラウマになったよ」「ありゃドープ・シットだぜ」なんたらかんたら……。
マシューデイヴィッド(Matthewdavid)が主宰する〈リーヴィング・レコーズ〉より今月末にLPがドロップされる『イシ(Ishi)』は、『ゲド戦記』の著者であるアーシュラ・K・ル=グウィンの母親、シオドラ・クローバーの著書『イシ 北米最後の野生インディアン』を下地に彼のモジュラー・シンセジスによって紡がれた壮大なアンビエント叙事詩だ。高校生のゲド少年がこの著書に出会い、衝撃を受け、後に自身のフレーム・ワークの中に落とし込んでいったというのはなんともロマンティックだ。いい意味で生半可でないニュー・エイジ思想をプンプンに感じさせる近年の〈リーヴィング〉からのリリースというのも納得だ。
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE