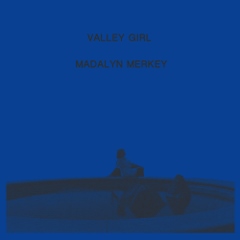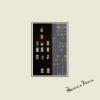MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Madalyn Merkey- Valley Girl
2年ぶり。2作め。前作と同じくダックテイルズのレーベルから。「待った」という感じは以前よりもなかった。サウンドクラウドに上がっていた音源を片端からダウンロードし、とりわけ「スリープ」を繰り返し聴いていたころはマテリアルに落とし込まれるかどうかも定かではなく、『セント(Scent)』がリリースされると知ったときは、自分の好きな音楽とレコード産業には接点があったのかという驚きのほうが大きかった。2作めはつまり、その「接点」が保たれているという保証のような感覚が先に立つ。それは音楽を聴くときにはむしろ雑音になる。ジャム・シティがかつてインタヴューで「(レコーディングのときに)いちばん難しかったのは、自分自身がクリアになること」と話してくれたけれど(『ele-king Vol.9』)、それは大なり小なりリスナーにも当てはまる。作家性ほど音楽自体にとって邪魔なものはなく、語るのに楽なこともない。それぐらい『ヴァレー・ガール』というアルバムを静かに聴きたいと願いながら、なかなか果たせない。かつてとは意識とマテリアルが逆の位置でズレている。
最初に感じたことはアンビヴァレンスな志向性を持っているということだろうか。この1月に妙な予感でも働いたのかオランダで『セレクティッド・ アンビ ヴァレント・ワークス'05-'12』というアルバムを出した人がいたけれど、実際にはそれほどアンビヴァレントな価値観をプレ ゼンテーションしていたわけでもなかったのに対し、『ヴァレー・ガール』はシンプルながらかつてのようにひとつの志向性に束ねられることはなく、ミュージック・コンクレートの時期によくあったような不条理感を通奏低音としながらも(それだけだと単純な模倣になってしまう)、不条理とはまったく異なるサウンド・エフェクトが微妙に采配されている部分はかなり新鮮だった(オープニングはとくに素晴らしい交錯を体験させてくれた→https://soundcloud.com/new-images/madalyn-merkey-archipelago-1)。そして、それが次第にかつての不条理モードをブラッシュ・アップしたかのように表情だけを変えて収束の方向性に傾き、最終的にはかなりアカデミックな領域に没入していく。ポップ・ミュージックの断片もない。これがミュージック・コンクレートを上書きするという意図のものならば、それを解析する力量は僕にはないので、これ以上は放棄するしかないけれど、せっかくのメデリン・マーキーなので、もう少し食い下がってみよう。だんだん自分がクリアになってきた気もするし。
このアルバムは「農業と景色」にインスパイアされたものらしい。農業といっても素朴な側面もあれば、モンサントの遺伝子組み換え作物をインドや中国が追放し、アメリカに30億円以上のダメージを与えたとか、思いつくフェイズがさまざまで、どの部分を指しているのかぜんぜん感得できないものの、『ヴァレー・ガール』というタイトルや全体のサウンドから察するにどこか神秘的ながら労働の辛さを感じさせるようなところもある(だから不条理?)。はじまりは「アーキペラーゴ(群島)」だけど、締めくくりは「プルート(冥界)」だし……(農業から「死」が見えてくるとは?)。ちなみにモンサントは昔ながらの品種の改良に立ち返り、新種の野菜でまたしても注目を集めている。ヴェトナムに撒かれた枯葉剤の会社だけに、ホントに逞しいというか。
ティム・ヘッカーが『ヴァージンズ』(2013)のインスピレイションは新藤兼人監督『鬼婆』(1964)だというなら、『ヴァレー・ガール』はそれこそ同監督による代表作『裸の島』(1960)で、同作でも濃厚に描かれていたように農業にはハレとケの「ケ」を強く意識させるところがある。「ケ」、あるいは、ストレートに「退屈を音楽にしたい」と言ったのはフィッシュマンズで、日常性にも地域によって相当な差があるだろうから一概には言えないとしても、ミュージック・コンクレートの再現として聴いても『ヴァレー・ガール』はここではないどこかへ移動するという感触はなく、積極的に「ハレ」を遠ざけているといえる。もっといえば人間の感情を通したものの見方もやめて、空気になりきろうとしているという感じだろうか。「描写」から「主体」を消すというのもミュージック・コンクレートの時期にはひとつの課題だったけれど。
あるいはレイヴ・カルチャー以降の身体性をドローンに持ち込むのがゼロ年代のスタイルだったとしたら、かつてブライアン・イーノがプログレッシヴ・ロックの狂騒から平凡な日常性を奪い返そうとしたように(詳しくは『アンビエント・ディフィニティヴ』序文)、USアンダーグラウンドをポスト・レイヴへ誘おうとするものにも聴こえなくはない。レイヴ的な身体の否定ではない。やはり呼吸の間隔などにはレイヴ以降の細切れな区切り方が目立つし、もう一息でトリップへ誘うギリギリのニュアンスは残っている。しかし、最後のところで没入させることを避けているようなところは確実にあり、チル・アウトでいえばワゴン・クライスト『ファット・ラブ・ナイトメア(Phat Lab. Nightmare)』(1994)が醸し出していた曖昧なムードを思い出させる。どこかストイックで、飛行機が墜落するようなことがあっても流れつづけることができるとした『ミュージック・フォー・エアポート』(イーノ)に対して、そういった意味での「無害なBGM性」を踏襲するところもない。なんというか日常でも非日常でもなく、僕には馴染みのない場所に連れて来られたというしかない。
ネオ・クラシカルのデヴィッド・ムーアが今年、ビング&ラス(Bing & Ruth)の名義でリリースした『トゥモロー・ワズ・ザ・ゴールデン・エイジ』(〈RVNG Intl.〉)はアカデミックな領域にありながら、掛け値なしに気持ちよく響き渡るサウンドを展開していた。モートン・フェルドマンやブライアン・イーノにインスパイアされたという触れ込みはむしろマイナス要因にしか思えず、それこそ今年だったらゴラ・ソウ(Gora Sou)やA・r・t・ウイルスンといったポップ・ミュージックと完成度を競い合ったほうがいいような気がするぐらいに。そう、デヴィッド・ムーアとメデリン・マーキーは立場を入れ替えた方がどちらもすっきりすることはたしかだろう。日本と違ってアメリカにはもはや在野とアカデミックに明確な線引きは存在していないというならば、それはもう、そうかというしかないけれど……。
三田格
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE