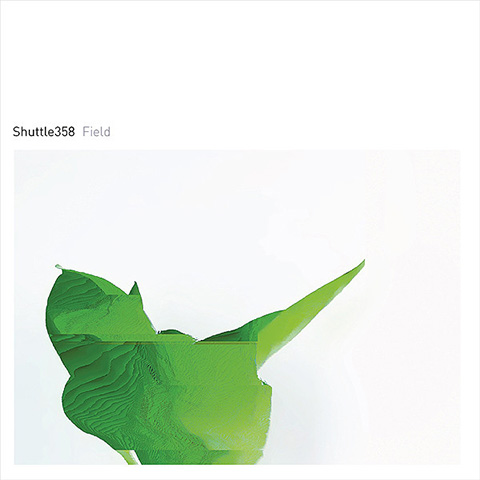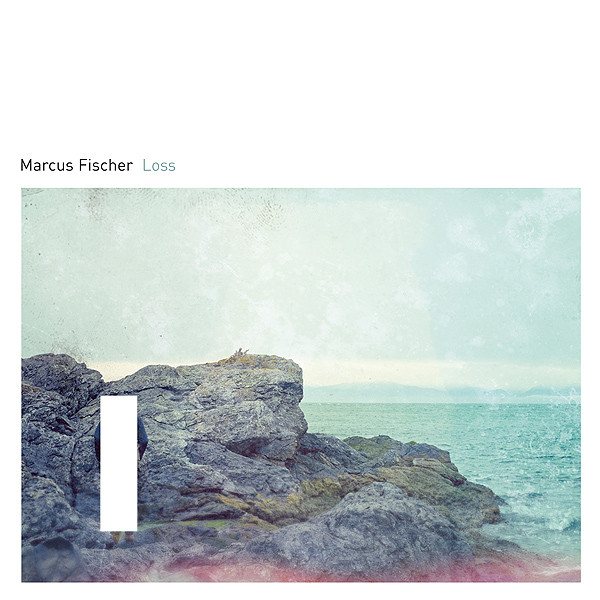MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Shuttle358- Field
エレクトロニカ/電子音響以降のアンビエント・ミュージックに「物語」は希薄だ。いや、「コンセプト」すらない。音の生成があるのみだ。むろん変化はある。生成/変化だ。しかしその変化はミニマルでなければならないし、音響のトーンはスタティックでなければならない。意味ではなく、音。その空白と音響のバランスの追求。空虚という存在ほど、人間社会への強い問いかけもないだろう。その意味でエレクトロニカ以降のアンビエントは反転した存在論的なサイケデリック音楽といえなくもない。
テイラー・デュプリーが主宰する〈12k〉がリリースするアンビエント作品を聴いていると、ふと「写真」のようだと思うときがある。むろん彼が優れたフォトグラファーで、その作品がアートワークに使われているからそう感じるのかもしれない。しかしそれは具体的なイメージというより記憶に一瞬だけ残っている光景/感覚に近い。記憶の音楽としてのアンビエントとでもいうべきか。物語性は希薄だが人間の繊細な感覚は封じ込めている。記憶。瞬間。反復。生成。
シャトル358の新作『Field』を聴いたときも、そのような感覚を持ったものだ(ああ、〈12k〉の音だと思った。それも00年代初頭の頃の……)。しかし人の記憶に「棘」があるように、その音もまた単に優しいだけではない。彼の音に美しい「棘」がある。これが重要だ。新しい彼の音は意外なほどに「硬い」。
シャトル358は、本名をダン・エイブラムスという。 彼は90年代末期から活動を始めたエレクトロニカ・アーティストだ。1999年に〈12k〉から『Optimal.lp』、00年に『Frame』、02年に『Understanding Wildlife』、04年に『Chessa』を継続的にリリースし、そのクリック&グリッチ・アンビエントな作風から初期〈12k〉を代表するアーティストと目されてもいた。また、ダン・エイブラムス名義では01年に〈ミル・プラトー〉から『Stream』という優れたグリッチ・ミニマルな作品をリリースしている。これもなかなかの名盤だ。
だが、04年の『Chessa』をリリース後、アルバム・リリースは2015年の復活作『Can You Prove I Was Born』まで9年間ほど途絶えることになる(14年に50部限定のシングル「CYPIWB.12"Lmtd」を〈12k〉からひっそりと出してはいるが)。この04年から15年までのあいだ、クリック&グリッチなエレクトロニカはアンビエント/ドローンへとその潮流を変えていった。グリッチがアンビエント化したのだ。それは時代の変化でもあったし、どこか寂しくもあった。まだまだ00年代初頭のエレクトロニカのミニマリズムには可能性があると思っていたから。
それゆえ『Can You Prove I Was Born』における「復活」は自分にとって、とても大きかった。ゼロ年代エレクトロニカの失われたピースが埋まったような気がした。じじつ『Can You Prove I Was Born』はオーガニックな響きのグリッチ・エレクトロニカ/アンビエントであり、多いに満足したのである。
と、ここまで書いてきて前言を翻すようだがシャトル358の音楽のルーツはアンビエント・ミュージックではなく、ミニマル・テクノであろう。そう、先に書いたようにドローン・ミュージックでは「ない」点が重要なのだ。
彼の音楽にアンビエント的なアンビエンスを感じられるのは、ミニマル・テクノを基礎としつつも、さまざまな音響(グリッチや環境音など)によって、その基礎となっている「テクノ」が多層的に存在する感覚があるからではないかと思う。とはいえ〈12k〉主宰のテイラー・デュプリーもミニマル・テクノ出身であることを考慮すると90年代/グリッチ以降のエレクトロニカ・アンビエントは、そもそも、ミニマル・テクノの一変形だったといえないか(そう考えみると今のテイラー・デュプリーのドローン音楽にも別の光が当てられるはず)。
シャトル358の新作『Field』もそうだ。ドローン・タイプのアンビエントではなく、さまざまなサウンド・エレメントがミックスされることでアンビエンスな音楽/音響を獲得するクリック&グリッチなアンビエント/エレクトロニカであったのだ。
アルバム冒頭の“Star”ではテクノの微かな名残のようなキックのような音が分断されるように鳴り、そこに何かを擦るような音、微かなノイズなどがレイヤーされる。加えて変調されたようなシンセのパッドや環境音も鳴る。その音のトーンとざわめきに耳が奪われる。
続く“Caudex”ではミニマルなベースに、柔らかいシンセとミニマムなノイズや環境音が折り重なり、覚醒と陶酔と睡眠を同時に引き起こす。以降、アルバムはシンセの透明な音とオーガニックな響きのサウンド、デジタルなサウンドと環境音のレイヤーが交錯しつつ、一定のスタティックなトーンで展開していく。
中でも特筆すべきはタイトル・トラックの“Field”だろう。ミニマルな電子音のループに、オーガニックな音の粒がレイヤーされ、光の反射のような電子音が鳴る。比較的短いトラックだがグリッチ・アンビエントの最高峰ともいえる出来栄えだった。
また、アンビエント/ドローン的な音響からクリッキーで微細なノイズや環境音が精密にレイヤーされ、オーガニックなムードで音響空間を拡張していく“Sea”、“Dilate”、“Waves”、“Divide”というアルバム後半の流れを決定付ける曲でもあった。
本作『Field』を聴くと00年代初頭のミニマルで、クリッキーで、グリッチなエレクトロニカ/電子音響の継承を強く感じた。まるで00年代頭の〈ミル・プラトー〉のアルバムのようである。これはむろん懐古ではない。あの時代のエレクトロニカ/電子音響(の方法論)は、決して古びることのない質感と情報量を持っていることの証明ではないか。ここにあるのは、大袈裟な「物語性」ではなく、サウンドの質量/質感を追及するソフト・ノイズな音楽である。何より大切なのは「音」そのものだ。それは空白のミニマル・サイケデリックともいえる音かもしれない。
そんなシャトル358の新作『Field』は、増殖する「意味」の中で、ある種の電子音楽が再び飽和しつつある今の時代だからこそ聴かれるべき音ではないかと思う。こういった空白のような音楽が、耳には必要なのだ。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE