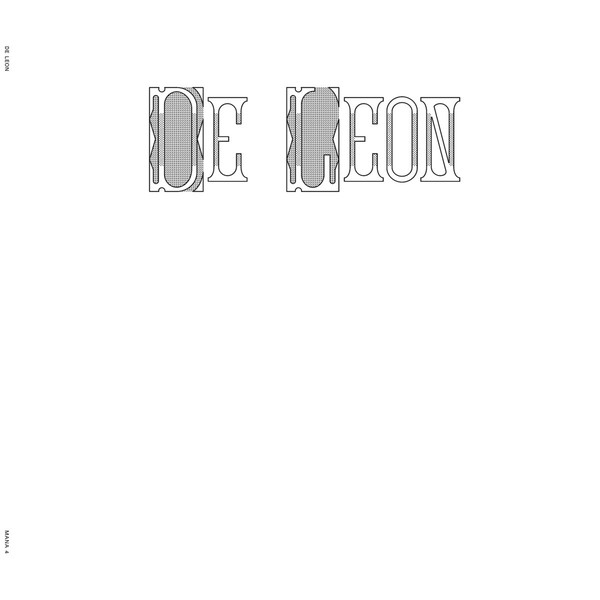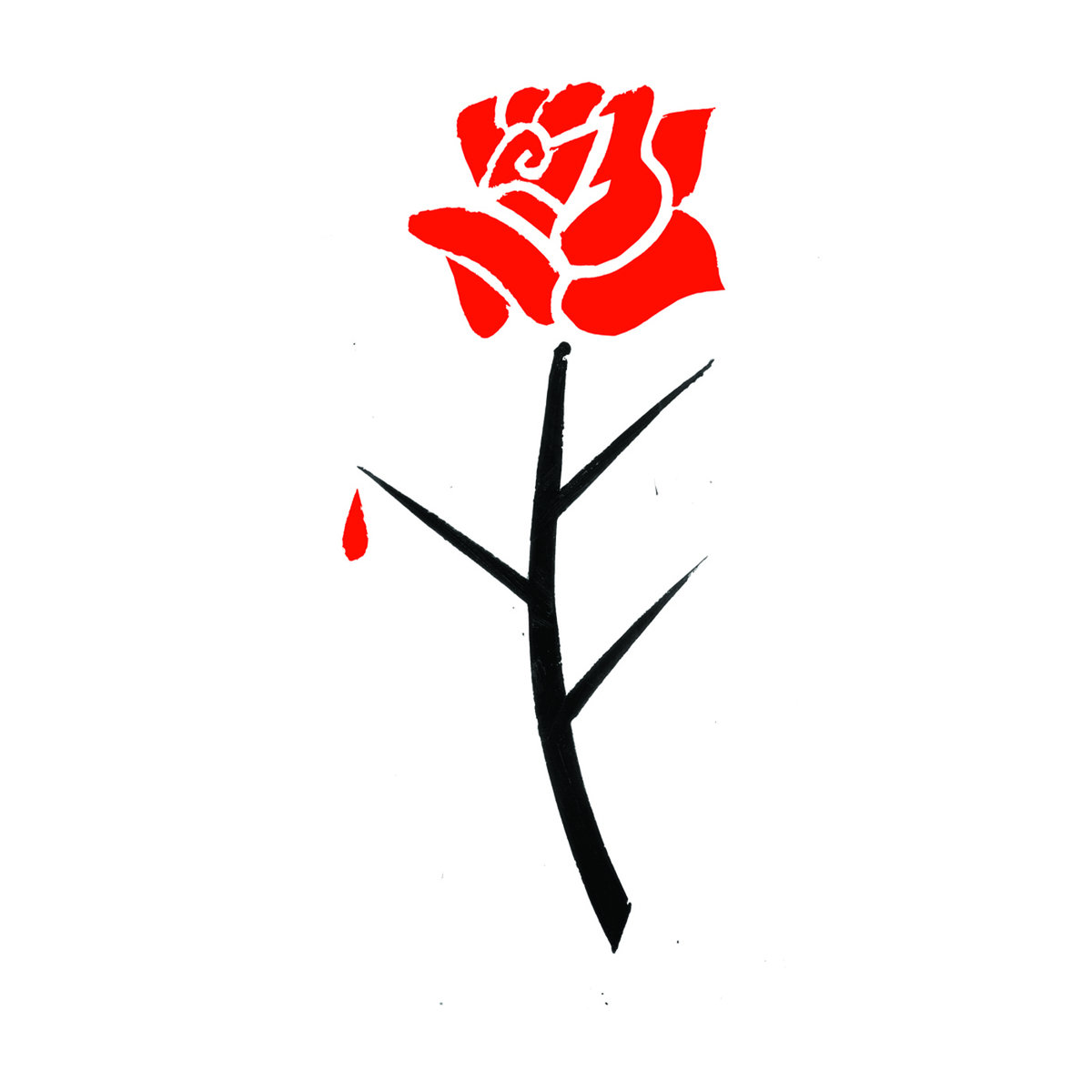MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > DJ Nigga Fox- Cartas Na Manga
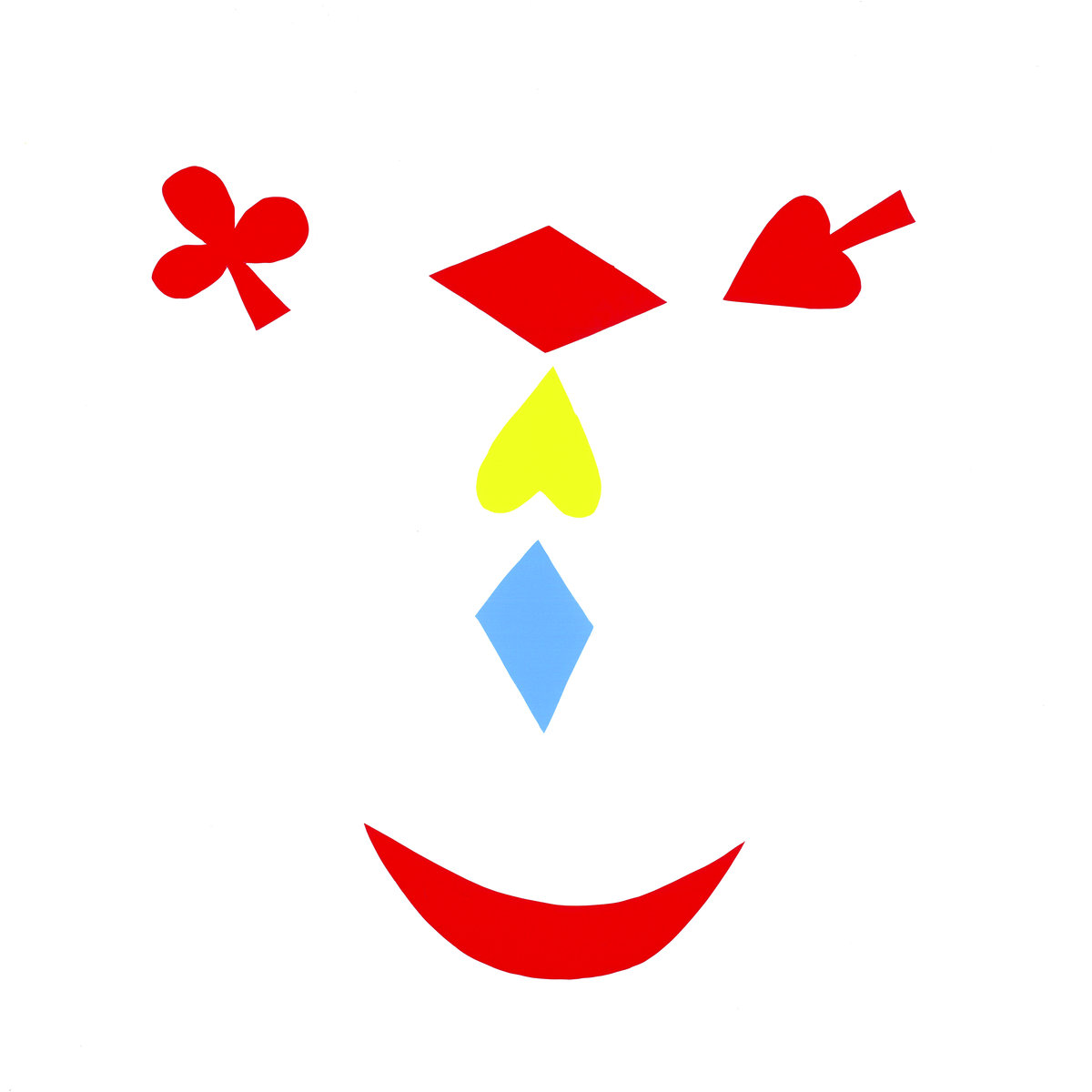
たしかにラフさやダーティさ、わけのわからなさみたいなものは後退してしまったかもしれない。「O Meu Estilo」の狂気はここにはない。だからといって歎く必要はまったくない。かわりに洗練度がバツグンに高まっているのだから。
アンゴラやカーボ・ヴェルデなど、おもにアフリカからの移民たちによって構成されるリスボン郊外の〈Príncipe〉の面々のなかで、テクノを好むのは自分だけだ、とニガ・フォックスはインタヴューで語っている。なるほどたしかにその要素はすでに「O Meu Estilo」にもはらまれていたわけだけれど、やはり「15 Barras」での冒険や〈Warp〉からのリリースを経験したことが大きかったのではないだろうか、ふたたび古巣から送り出されたこの初のフルレングスにおいて彼はその趣味を、より理知的なかたちでアフリカ由来のリズムやパーカッションと融合させている。洗練、ここに極まれり。
キイワードのひとつは「ジャジー」だろう。冒頭のトランペットからしてそうだ。そのムードは“Faz A Minha”のストレートな和音を筆頭に、“Talanzele”や“Água Morna”、“Vício”といった曲の断片から聴きとることができる。こんなにもメロディが頭に残るニガ・フォックスは初めてではないだろうか。“Nhama”のプリペアド・ピアノのキュートさといったら!
それと連動するかたちで、テクノのアイディアもふんだんに盛り込まれている。“Faz A Minha”ではアシッドやブリープがバティーダのリズムに華を添え、かつてないキャッチーさを演出しているし、“Sub Zero”や“Nhama”のアシッディな感覚は90年代のテクノを彷彿させる。“Pão de Cada Dia”におけるアンビエント・タッチのシンセや“Água Morna”の音声ドローンなんかもきっと、出所を探ればおなじような場所にたどりつくのではなかろうか。
とはいえもちろん、ニガ・フォックス流のポリリズムが失われてしまっているわけではない。“Sub Zero”におけるハンドクラップをすり潰したようなノイズ音や“Nhama”のパーカッションなんかが刻むリズムは、彼らしいもたつきを曲にもたらしている。バティーダ~クドゥーロも健在ではあるが、ただ、全体的に西欧のフロアが意識されているというか、たとえば実質的に4つ打ちに相当するキックのうえでパーカッションを思うぞんぶん遊ばせる“Talanzele”のように、シンプルなビートが鳴る空間を前提にしつつ、そこでいかに複雑な組み合わせを聞かせるかということが念頭に置かれているように思われる。各地でプレイを重ねてきた経験がフィードバックされているのかもしれない。
もっとも異彩を放っているのは最後の“5 Violinos”だろう。彼の手札にダウンテンポ的な着想があったことにも驚かされたけど、バックの旋律とは噛みあわない調性で披露される謎めいた歌(「ニガ・フォックスはヤバい」みたいなニュアンスらしい)は、リズム以外の面でも彼がマジックを発動できることを教えてくれる。
ようするに既知のセンスや勢い、あるいはいわゆる「初期衝動」みたいなもので押しきってしまわないところが本作最大の魅力で、それは良い意味で戦略と呼ぶべきものかもしれない。おそらくわたしたちはいま、これまでひそかに地下でうごめいていた稀有な才能が、一気に大舞台への階段を駆けのぼっていく瞬間に立ち会っている(驚くべきことにニガ・フォックスは今年、ハウ・トゥ・ドレス・ウェルのリミックスまで手がけているのだ)。〈Príncipe〉のボスであるマルフォックスは「眠りにつくいまこの瞬間も DJ Nigga Fox や Nídia や Nervoso が地球のどこかでDJをしている、と思えるのはとても幸せな気分だ」とインタヴューで語っているけれども、ニガ・フォックスがこの練りに練られたファースト・アルバムでさらなる飛躍を遂げるさまを眺めていると、どうしても「ブラック・アトランティック」ということばを思い出してしまう。アフリカからヨーロッパへ、郊外のゲットーから都市へ、リスボンから世界へ。この際もう思いきって言ってしまおう。これは、ディアスポラによる希望の音楽である。
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE