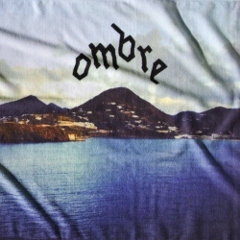MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Ombre- Believe You Me
夏の終わりを飾る企画モノだと、とても楽しみにしながらもどこか高をくくっていたのだが、反省しなければならないようだ。ジュリアナ・バーウィックとヘラド・ネグロ、〈アスマティック・キティ〉の提案した心憎いコラボレーションが、2年の歳月をかけて完成した。かたや自身の声を素材としてミニマルで即興的なサンプリング・パフォーマンスを試みる女性アーティスト、かたやアイデンティティでもあるラテン音楽をシックに活けながら、緻密な音響的アプローチを試みるプロデューサー。ツアーをともにしたことが直接的なきっかけであったようだが、なるほどそうしためぐり合わせでもなければ結びつかない、個性的な出会いである。
バーウィックのほうはイクエ・モリとのコラボが記憶に新しいが、基本的には自ら述べるように「ローン」なアーティストだ。ヘラド・ネグロことロベルト・カルロス・ラングは、プレフューズ73での活動でよく知られるが、多くのアーティストと関わりながらキャリアを編んでいくまさにプロデューサー型の才能。よっておおまかにはバーウィックが攻め、ラングが受けに回るセッションを想像していた。しかしことはまったく単純ではない。たがいの音に対する深いリスペクトと理解が、コラボという目的のもとにではなく、このアルバムという作品世界のもとに溶けあっている。相手の土俵を借りて自分の技をアピールするような、よくあるタッグマッチ的企画とは一線を画するものであることをまず強調しておきたい。
彼女と彼、1:1比のサウンド・デザインにぐっとくる。バーウィックがけっして歌姫ではあり得ないことを、ラングはじつに奥ゆかしいやり方で示す。アルバムは波状に、バーウィックの無時間的なアンビエンスと、ラングのコズミックな音響構築とを迎え入れ、エレクトロニカ、あるいはフォークトロニカの彼岸を描き出している。ジム・オルークらが拓き、多くの才能が耕してきたこの畑......研がれ、覚醒するように異常な鮮やかさをもってえぐり出されるアコースティックの響きを、ラングもまた受け継いでいるのだが、バーウィックとの出会いによって、彼の音響にはまた新しい角度がついたようだ。空間的な広がりを持ち、わずかな物音をも見逃さず、すべて巨視的なサイズへと磨き出し艶がけるかのような彼の方法は、すべての影を光でとばして同じ白色へと変えていくようなバーウィックの音作りとは、本来は相反するものであるように思われるのだが、両者は交互にあらわれ、またときに重なり、じつにミスティックなサウンド・プロダクションを生んでいる。
冒頭の曲ではバーウィックの音がラングによって思いがけない艶と奥行きを与えられて登場するし、"センス"のローファイ感、もしくはグリッチーなノイズ・センスはバーウィックの手になるものだと思われる。"ウェイト・ドーズ・ワーズ"は、ディヴェンドラ・バンハートの近作に濃厚な、枯れた味わいの洒脱なラテン・ポップスにバーウィックのコーラスをかぶせる。
彼女の声がポップス的なフレーズ感を持ちながら一定のビートの内に収まったこと自体がかなりの萌えを誘発したが、"トルメンタス"においてはふつうにヴォーカルをとっていて、なんというかこんな形でのデレを予想していなかった筆者には刺激が強すぎた......。この曲はラングのプロダクションのテリトリー下で、サム・アミドンにも通じるような独特の浮遊感を獲得している。こっそり何度も聴きたい。
そしてアルバムは先行して公開されていた"カーラ・ファルサ"へとつづく。白く飛ばされたバーウィックの音世界にクリアな電子音が介入し、機械的なビートを空気ポンプのようにゆったりとやさしく送りこんでいく。リピートされ重ねられていくバーウィックのいつもの呼吸に、それが慎重に同期していくさまがすばらしい。彼らはつきあっているのかもしれない。じつに心地よく波がかみあっている。
短い子どもたちの声のサンプリングが挿入されて終曲がはじまるが、すべての尊敬すべき抑制はここでようやく解かれ、彼はシンプルなギター伴奏を、彼女はシンプルなヴォーカルを披露する(筆者がここで2度死んだのは申し添えるまでもない)。これを最後までやらなかったことがこのアルバムのプライドと良心をよく物語っている。しかしまた、これがなくても完成はしなかったのだ。よくよくの注意をはらって編まれ、じっくりと対話とセッションを重ねたのだろう。すべては心地よく、万物に逆らわない。が、アート・ワークに色濃いオーガニックさともちがう、繊細な人工物ともいうべきものをここに見出すことができる。ぜひとも一聴をおすすめしたい名盤の誕生だ。
橋元優歩
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE