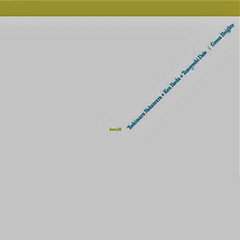MOST READ
- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ
- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー
- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演
- Actress - Statik | アクトレス
- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター
- 小山田米呂
- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント
- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう
- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024
- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏
- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場
- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト
Home > Reviews > Album Reviews > Tomoyoshi Date + Stijn Hüwels- Hochu-Ekki-Tou

漂うように流れ、人の生活の風景になる音楽。 芦川聡「波の記譜法」(1983)
このように環境音楽は以前とは異なったalternativeな感性回路を開き、目のまえに横たわる日常生活全体を組みかえる異化作業と共にある。 田中直子「環境音楽のコト的・道具的存在」(1986)
シティ・ポップはいまだにリヴァイヴァルが続いているようだが、それを追従するように、ここ1〜2年は、日本のアンビエント=Kankyo Ongaku(環境音楽)=J・アンビエントが流行りつつある。
いろんな要因があるようだ。高田みどりや清水靖晃の再発見、相変わらずの横田進人気、坂本龍一の『async』の衝撃と細野晴臣への再評価(not はっぴいえんど/not YMO)……、ヴァンパイア・ウィークエンドがサンプリングした細野作品は、入手困難なカセットブック作品で、そこには中沢新一による環境音楽に対する新たな解釈、〝観光音楽〟に関する文章があるわけだが、こうした解釈が生まれるほどに1980年代の日本ではアンビエントがひとつの大きな潮流としてあった。バブル期だからアンビエントが流行ったわけではない。70年代後半のイーノの影響が日本では大きかったことと、アンビエント的な発想がたとえば庭園という場所/空間に水の雫の音を加える日本人の感性には馴染みやすかったからではないだろうか。「閑さや岩にしみ入る蝉の声」──ジョン・ケージが松尾芭蕉を愛した話は有名だが、日本人が〝しずけさ〟と〝場の音〟を好んでいたことはたしかだろう。
なにはともあれ、アンビエントなるコンセプトに多くのひとが着目した80年代において、吉村弘と芦川聡はなかば別格の再評価を得ている。吉村弘にとってアンビエントとは環境のための音楽であるから、音楽それ自体がひとつの環境/風景となるよう志向したため、通常のレコード会社からのリリースではない形式でその作品は発表されている。こうした希少性がますますディガー心をくすぐるようだが、芦川聡にいわく「必要なところに必要なだけの最初の音がある」その作品は、「独特の透明感」があり、そして「メルヘンの世界で鳴っているオルゴールのような優しさがある」。ぼくは伊達トモヨシの音楽も、似ているんじゃないかと思う。
伊達の音楽を知ったのは、彼が寺でライヴをやったときだったが、寺院はおうおうにして日常とは時間の感覚が異なる場所である。水の雫の音のように、そこではたった1音が風景を変えることができる。伊達の音楽はそういう環境にハマる。
彼の新作はベルギー人の音楽家、スタン・フヴァールとの共作で、タイトルは漢方薬の補中益気湯から来ている。イギリス人のイアン・ハウグッドが主宰する〈Home Normal 〉からのリリースで、同レーベルはつい最近まで埼玉(ないしは東京)を拠点としていた。
コーリー・フラーとのプロジェクト、イルハの作品ではどちらかと言えば鑑賞向けのアルバムを作っている伊達だが、本作は、それこそがんばって鑑賞する必要のない音楽だ。空間を均一化するBGMやミューザックとは違う。ひとをトランスさせる畠山地平や中村弘二のシューゲイザー・アンビエント(あるいはドローン)やペシミズムをもってディストピアを描写するダーク・アンビエント、水パイプを仄めかすその名から連想されるようにトリップを志向するヴェイパーウェイヴ(あるいはスクリュー、あるいはウェイトレス)などとも違う。ドラッギーではないしサイケデリックという別世界志向の要素がほとんどない、あたかも風鈴のような、すなわち環境の一部になりうる音楽、生活のなかに根ざしながら無視して通り過ぎてもかまわない風のような音楽である。その空気のような音楽は吉村弘に近いのではないかとぼくは思うわけだが、本人がいちばん目指すところは、芦川聡の『Still Way』だという。そういうわけで、80年代の日本のアンビエントを継承するミュージシャンがここにひとりいると。
1曲目の“Hochu”はJ・アンビエントの真骨頂とも言うべき素晴らしい静寂がある。遠くでかすかに鳴っている抽象的な音像はあたたかい波のようにうねり、揺れている。2曲目の“Ekki”ではかすかに聞こえる最小限の音が鳴り,止み、それをゆっくりと反復する。ギターの弦による1音がながい“間”を取りながら響いている。フィールド・レコーディングからはじまる最後の曲“Tou”においてもギターの1音は早朝の自然音のなかで鳴っている。それは伊達らしい清々しさだ。イーノではないが、なるべく最小の音量で聴くべきアルバムだろうが、仮にいつもよりも音量上げて聴いても静かである。音はじょじょに重なるが、静けさはつねにキープされている。最後は曲らしくなってしまうのが少々残念ではあるが、それでもこのアルバムはただただ流しっぱなしにできるという“環境音楽”として成り立っている。ちなみに補中益気湯とは、自律神経を正常化するのに使われる漢方薬です。
過去を温ねることも大切だが、現在にも音楽は生まれている。J・アンビエントに目覚めたリスナーにも、ぜひ聴いてもらいたい。
※紙エレ24号の「日本の音楽を知るための14冊」からは敢えて外したが、1986年に時事通信社から刊行された、芦川聡のアンビエント論集からはじまる『波の記譜法』は、1980年代の日本におけるアンビエントの高まりを知るうえでは貴重な資料だ。高田みどりや吉村弘も寄稿している。なぜ敢えて外したかと言えば、これは意外と知られていないようなので、こうしてネットを通じて広く知って欲しいからである。さらにもう1冊を加えるとしたら、細川周平の『レコードの美学』だ。細川周平もまた芦川聡や細野晴臣らのように、1980年代にアンビエントついて深く考察したひとりである。
野田努
ALBUM REVIEWS
- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta
- Actress - Statik
- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant
- High Llamas - Hey Panda
- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -
- KRM & KMRU - Disconnect
- Cornelius - Ethereal Essence
- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated
- Martha Skye Murphy - Um
- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme
- Taylor Deupree - Sti.ll
- John Cale - POPtical Illusion
- Amen Dunes - Death Jokes
- A. G. Cook - Britpop
- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands


 DOMMUNE
DOMMUNE